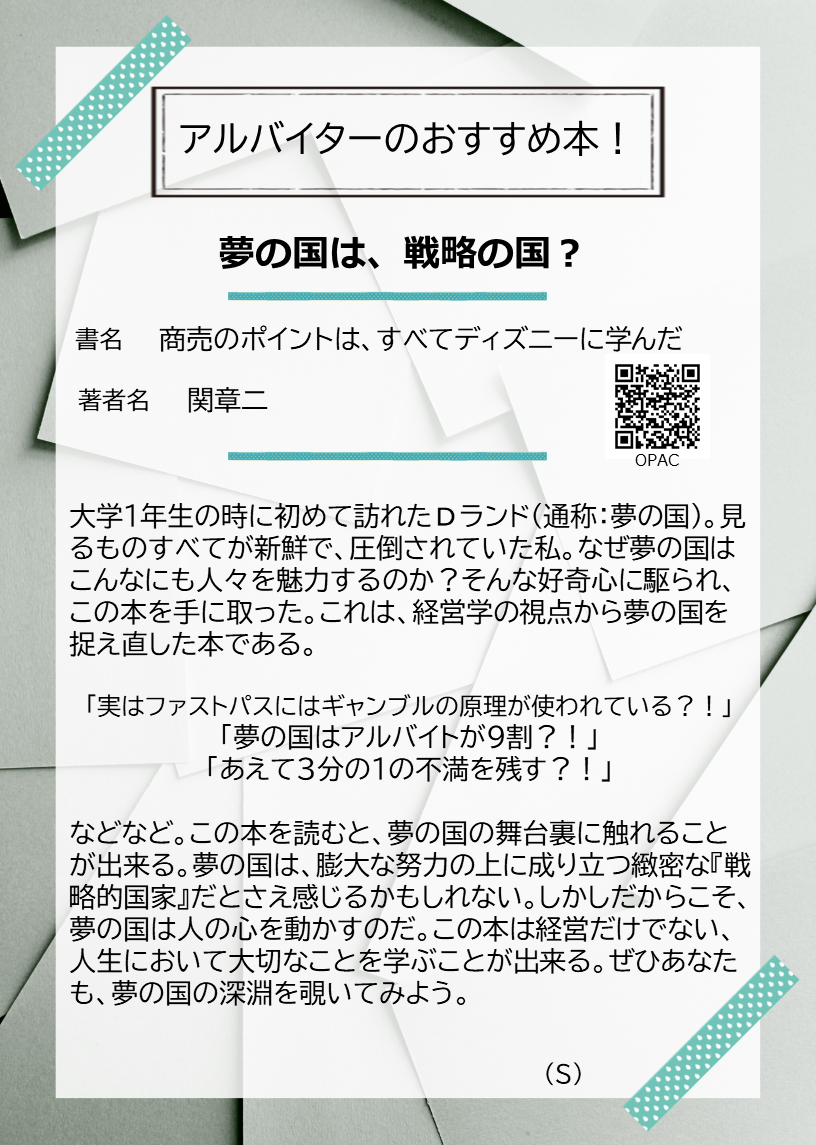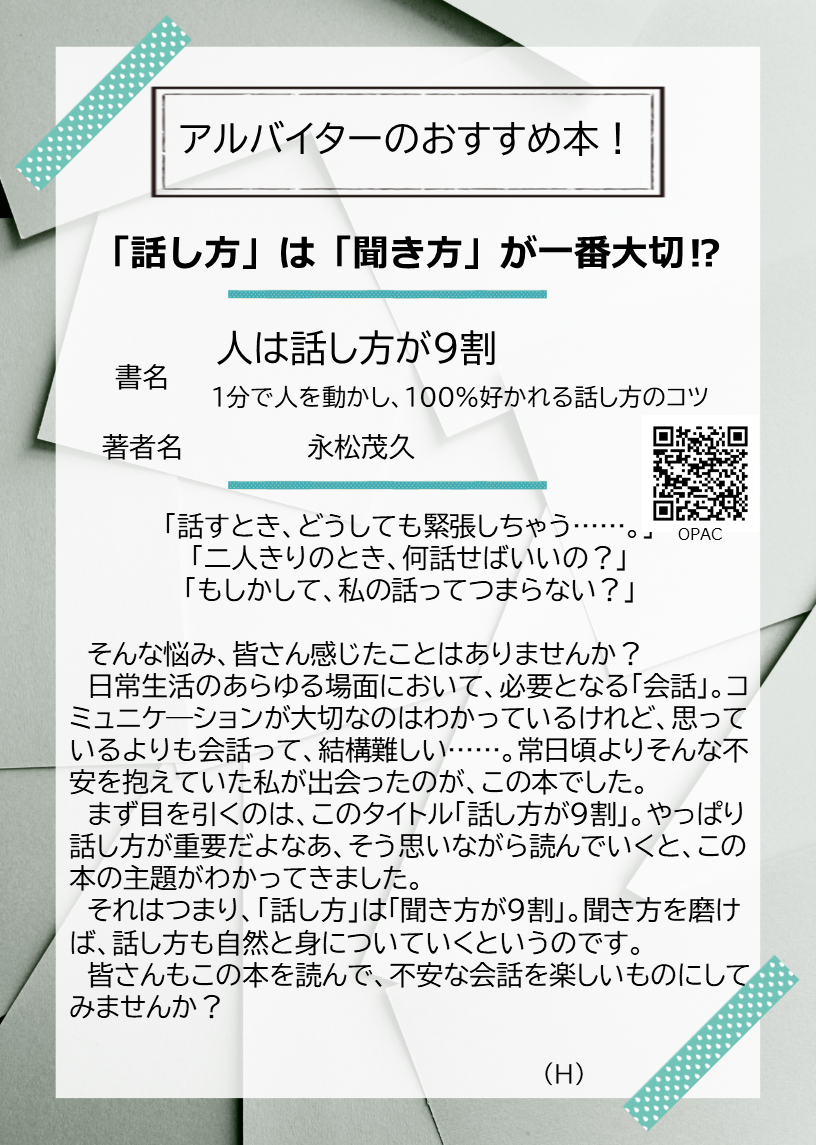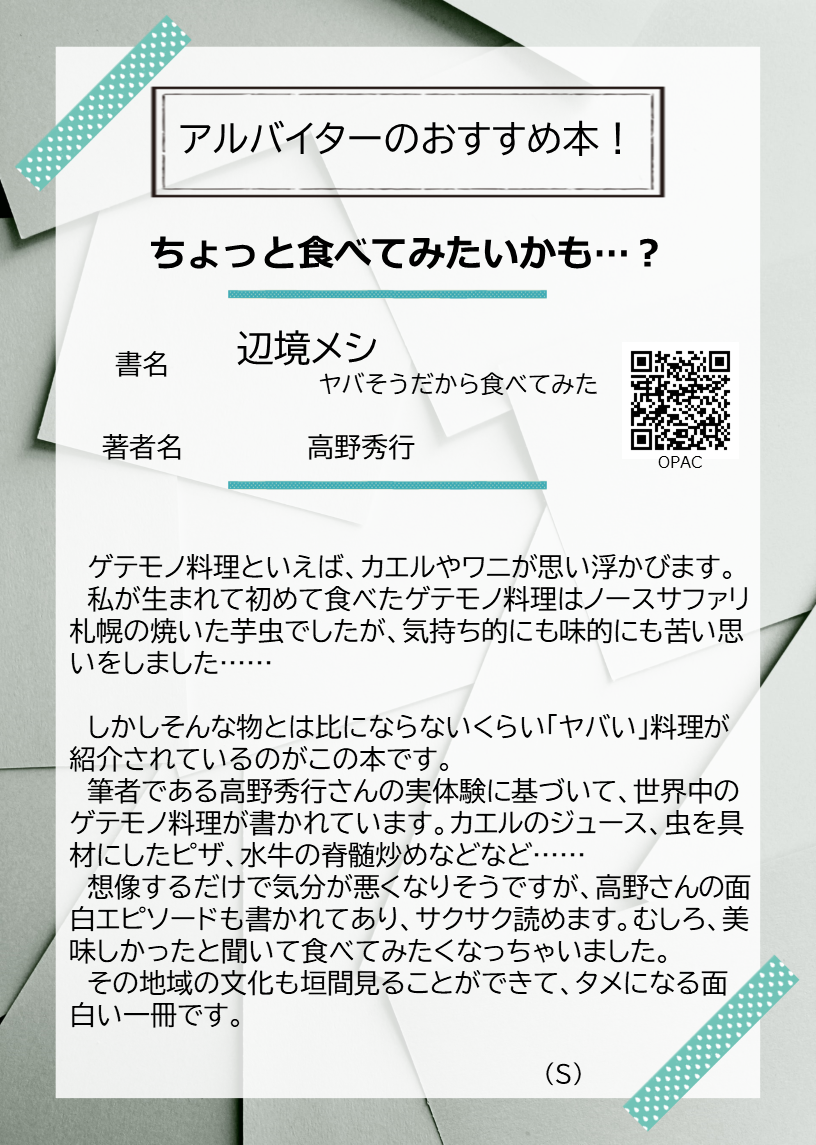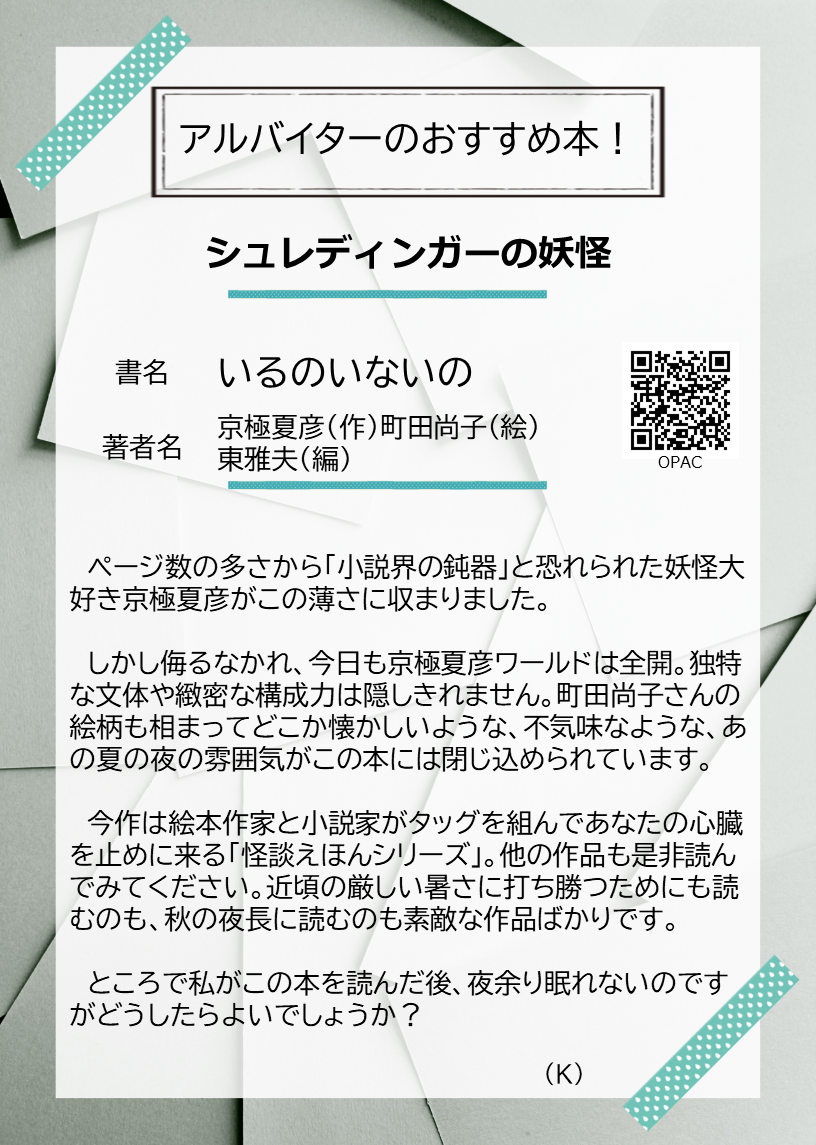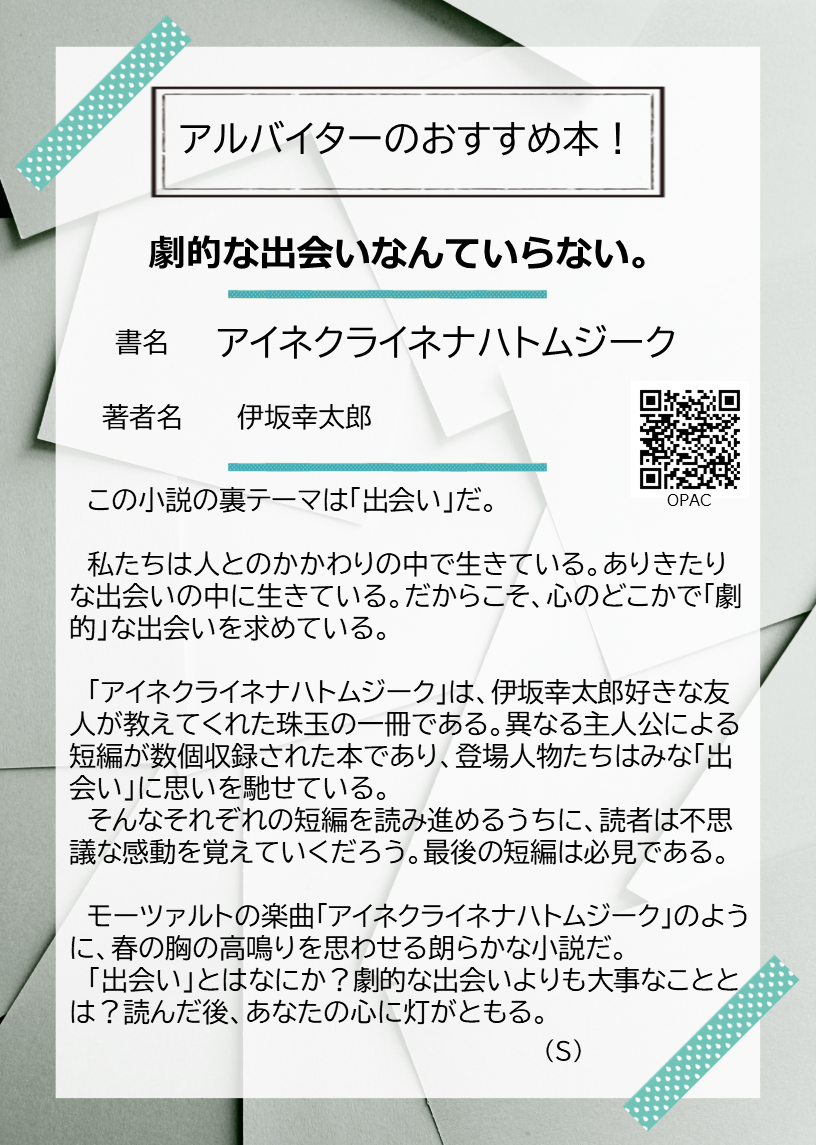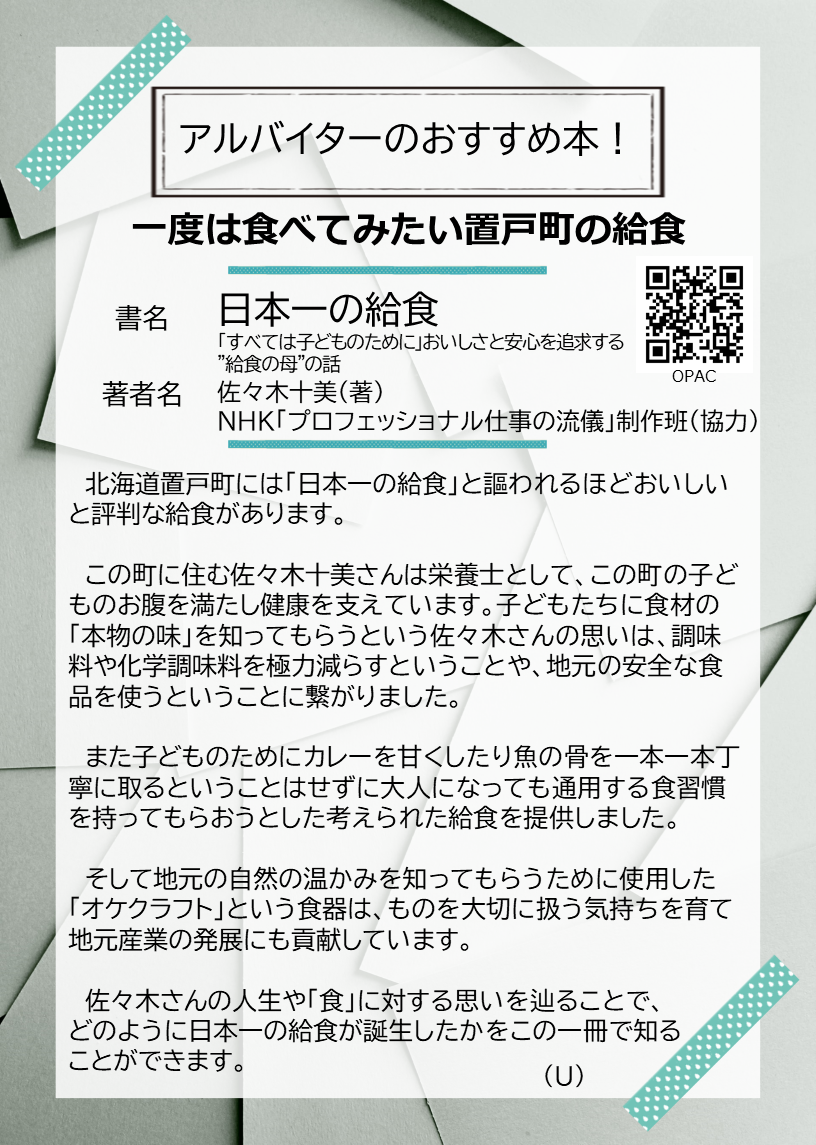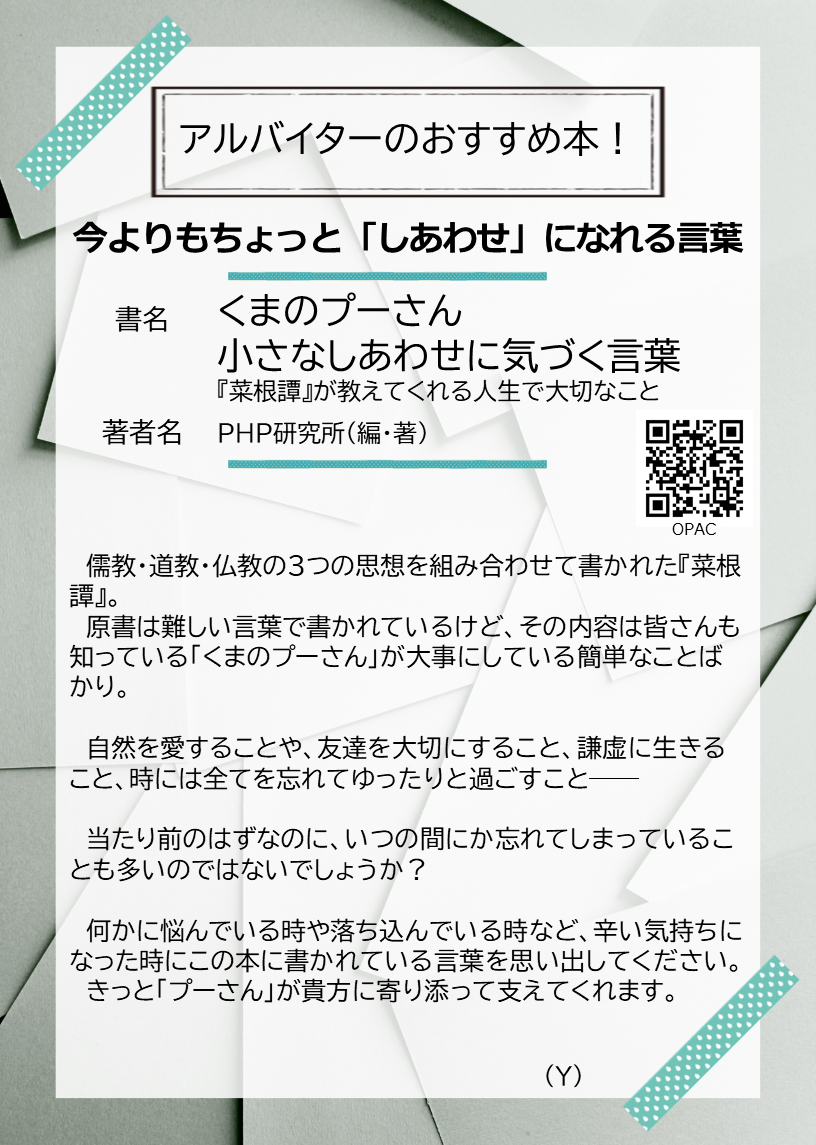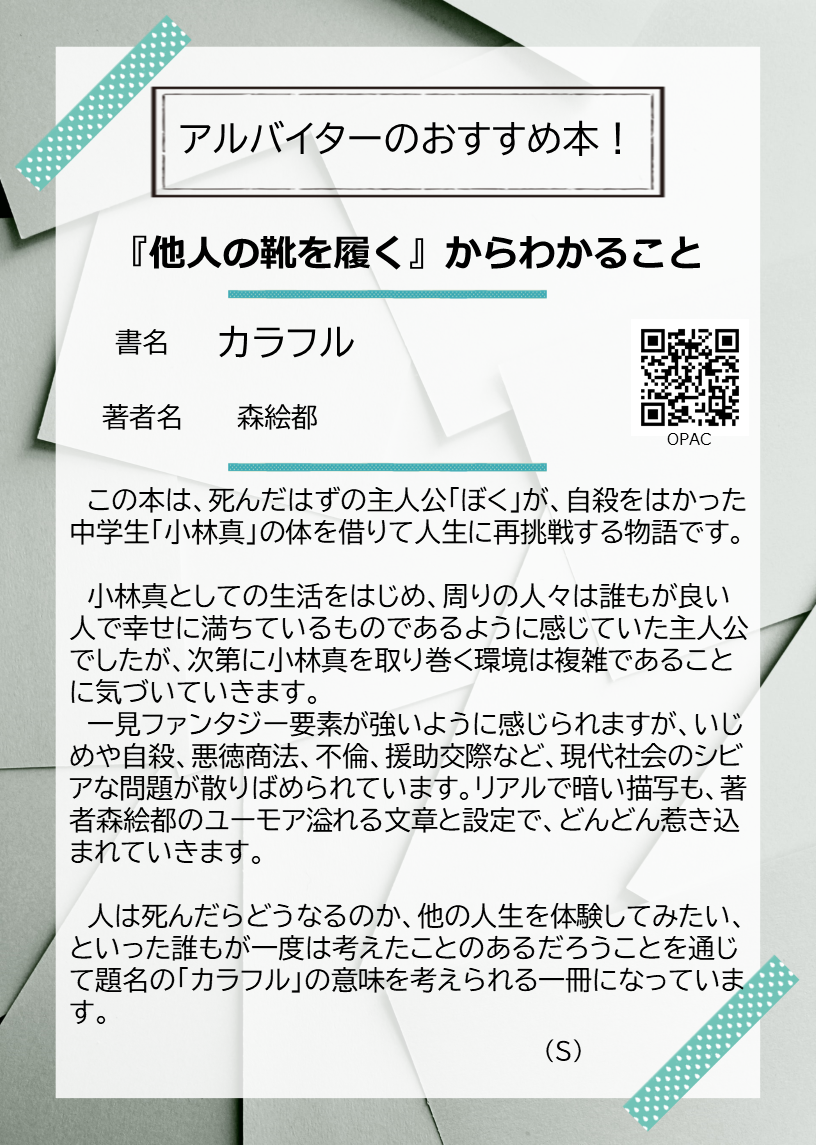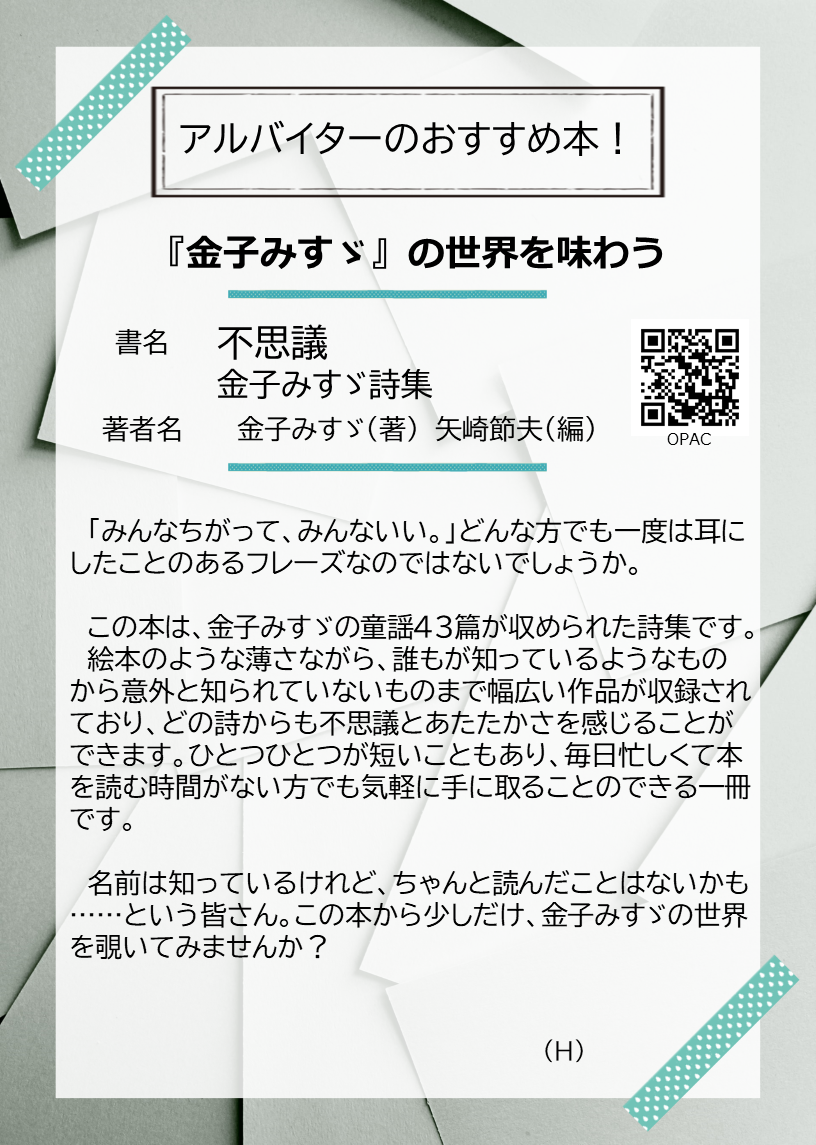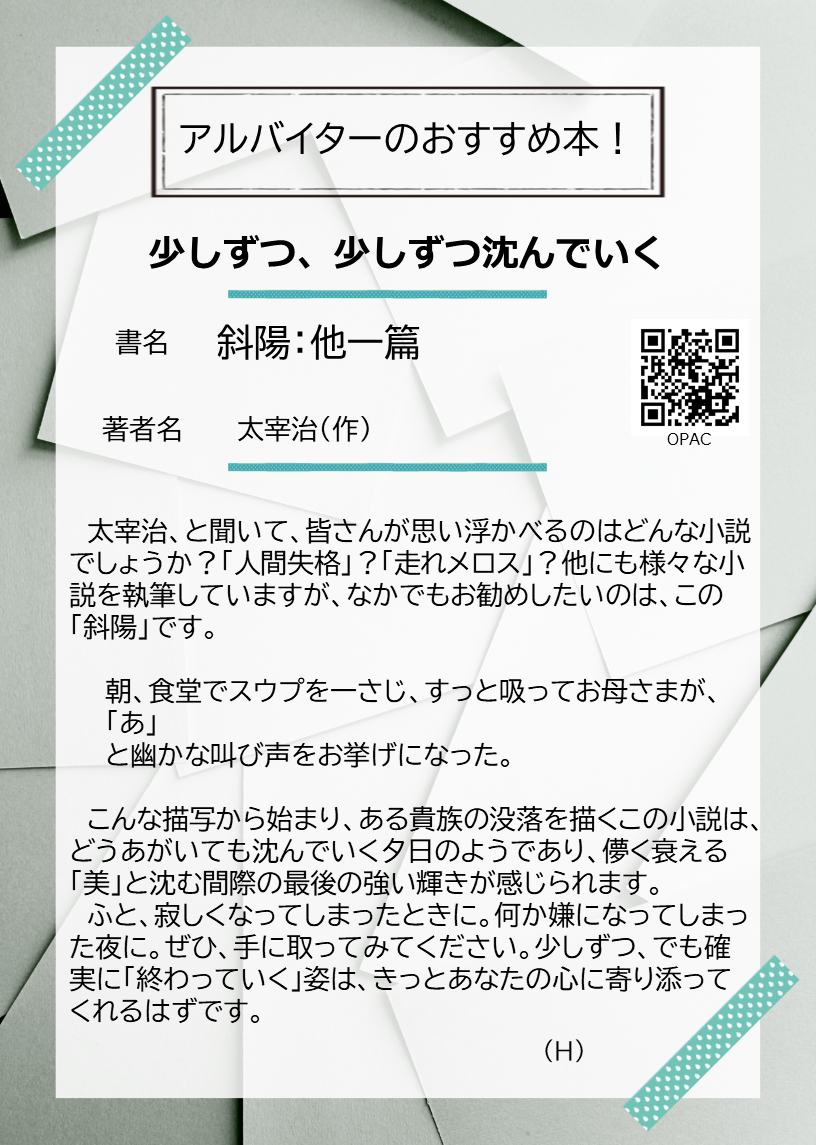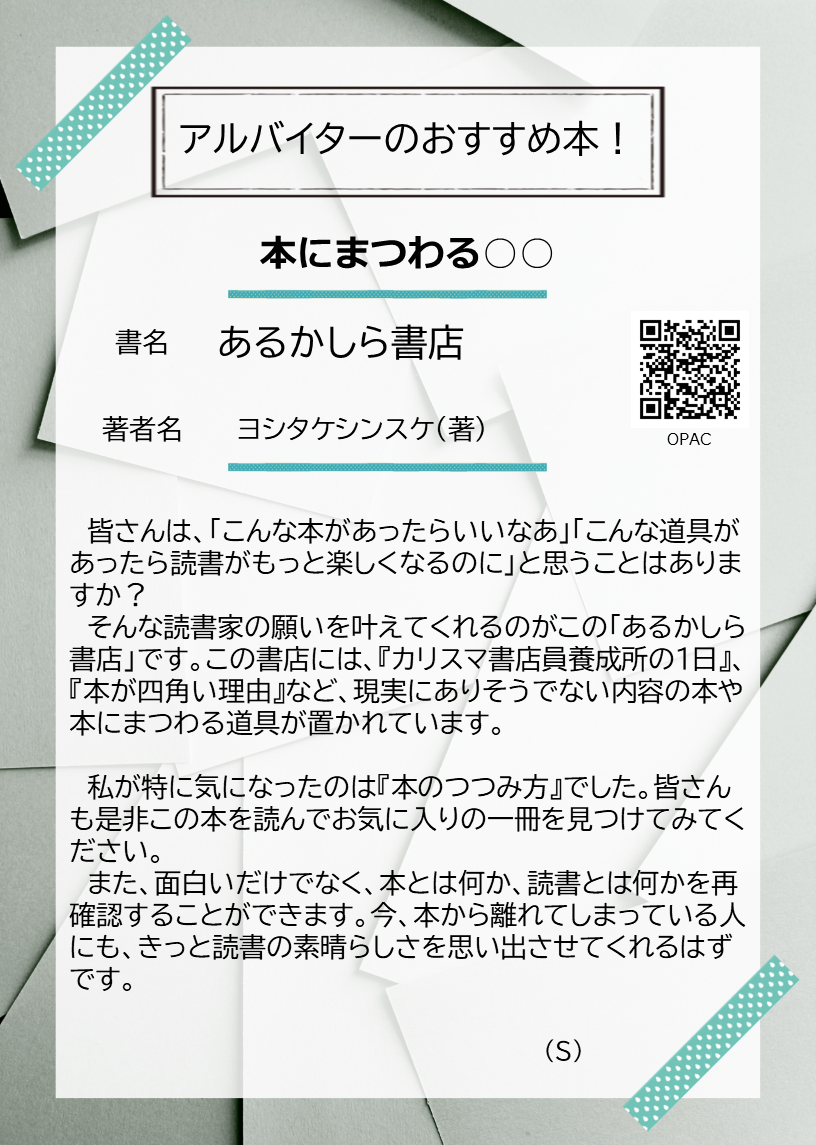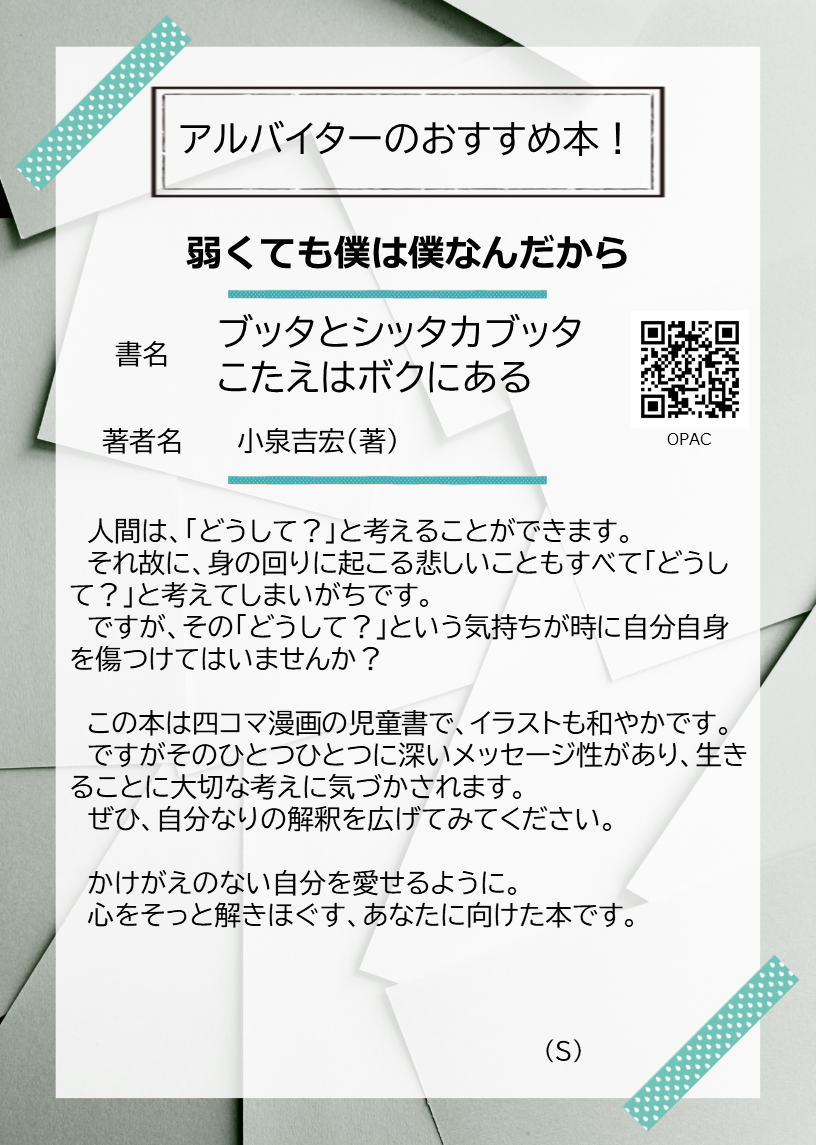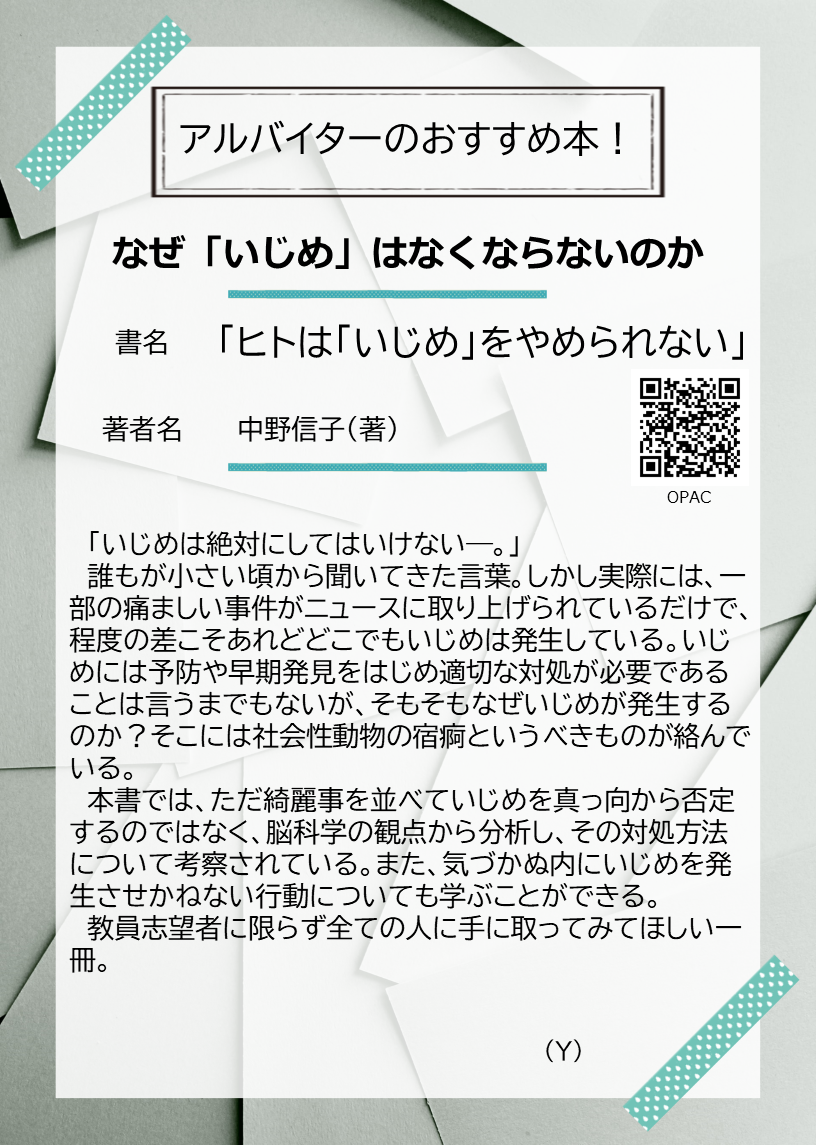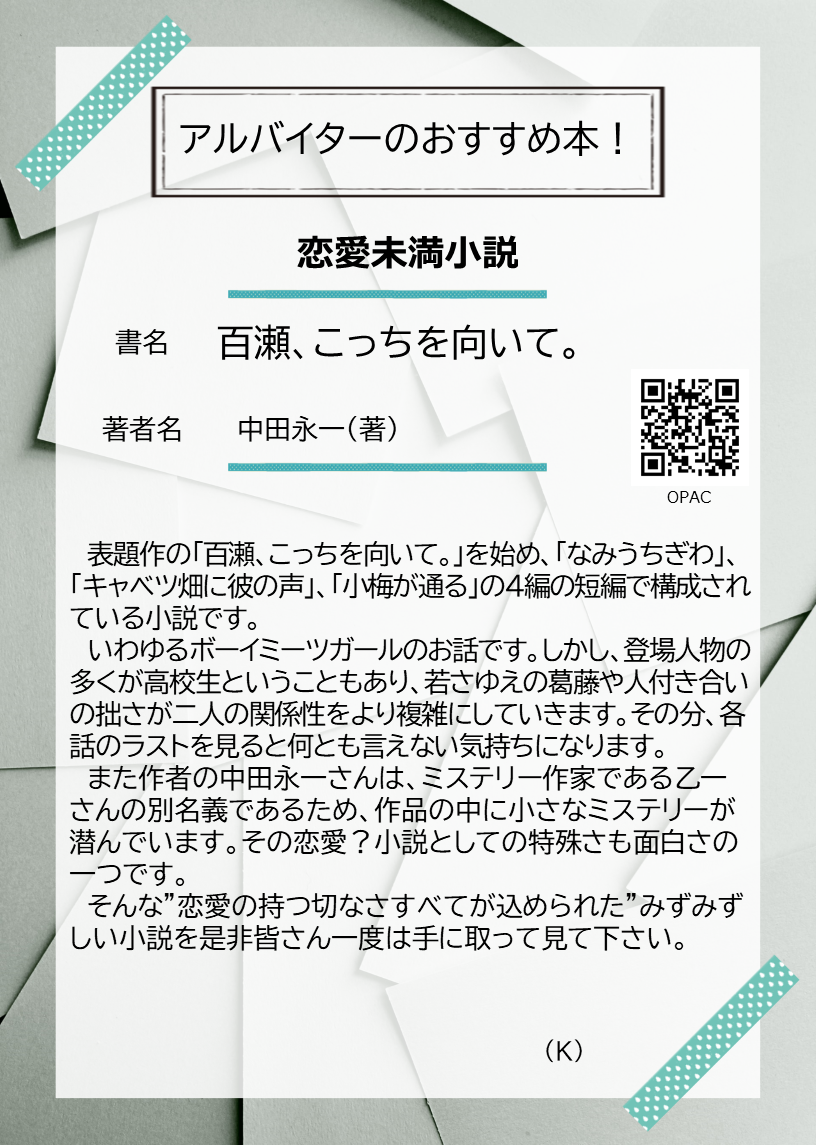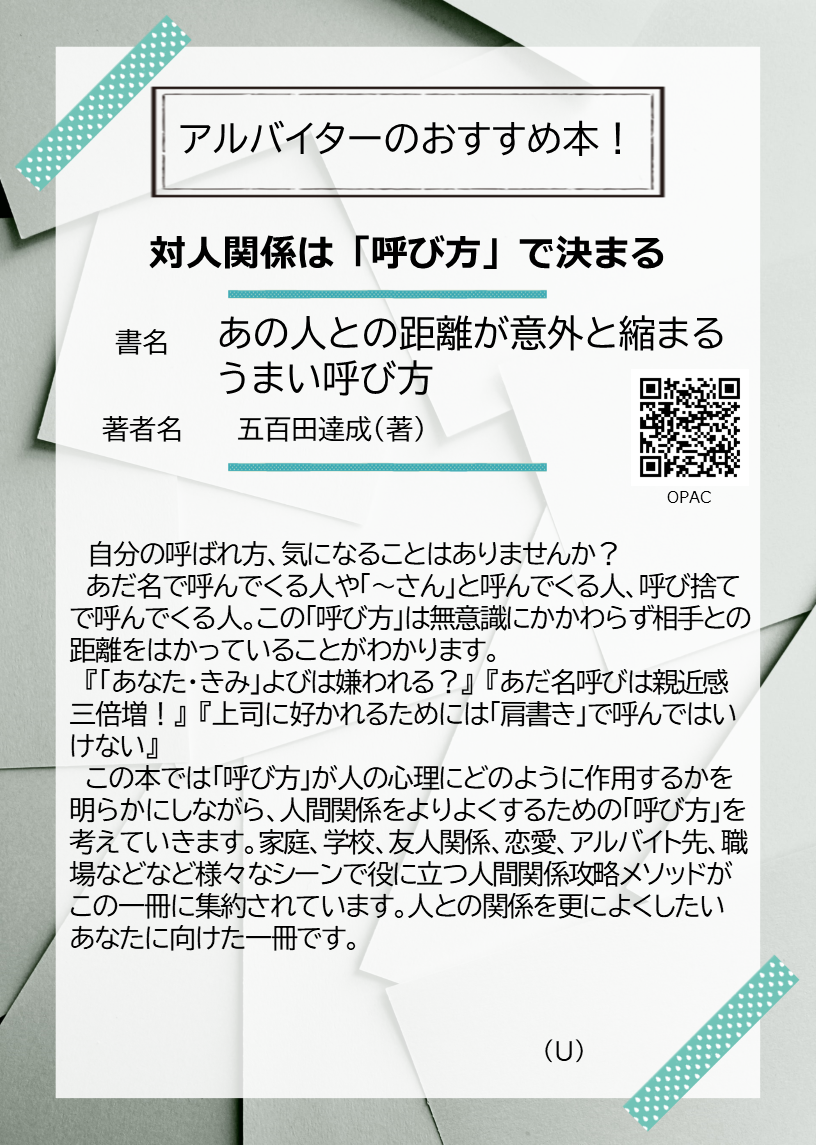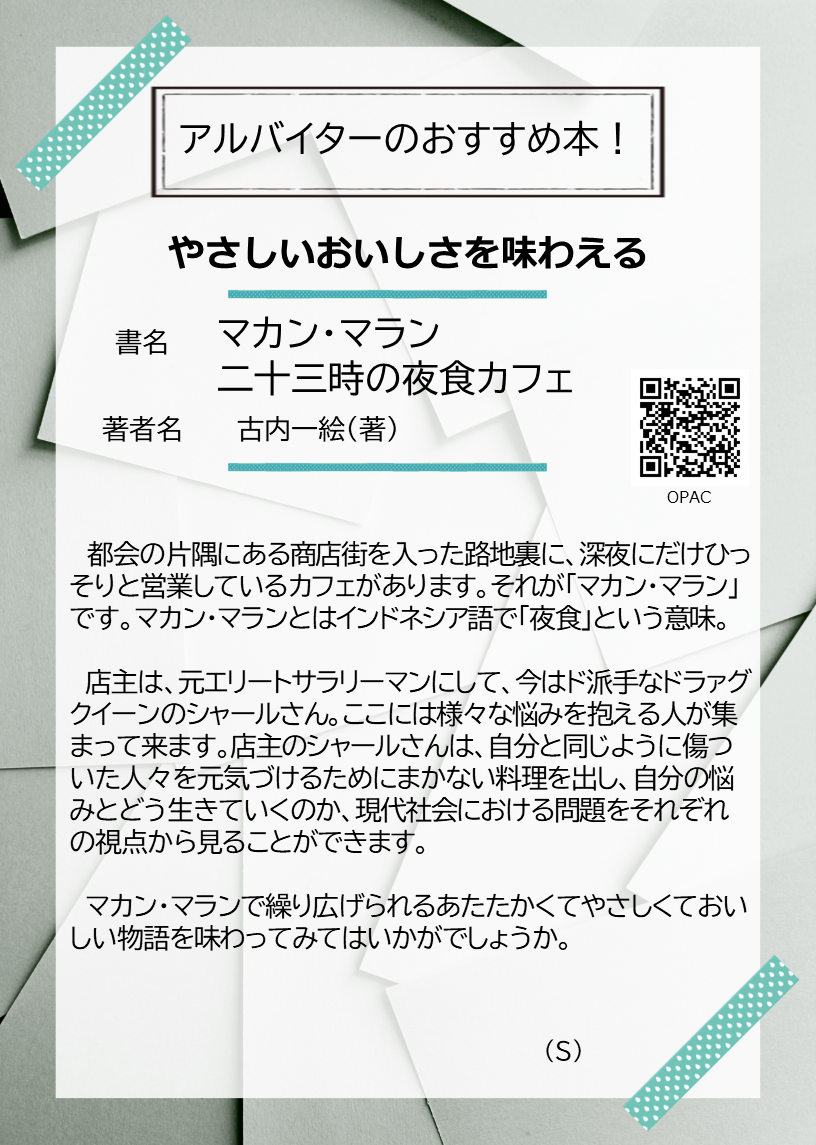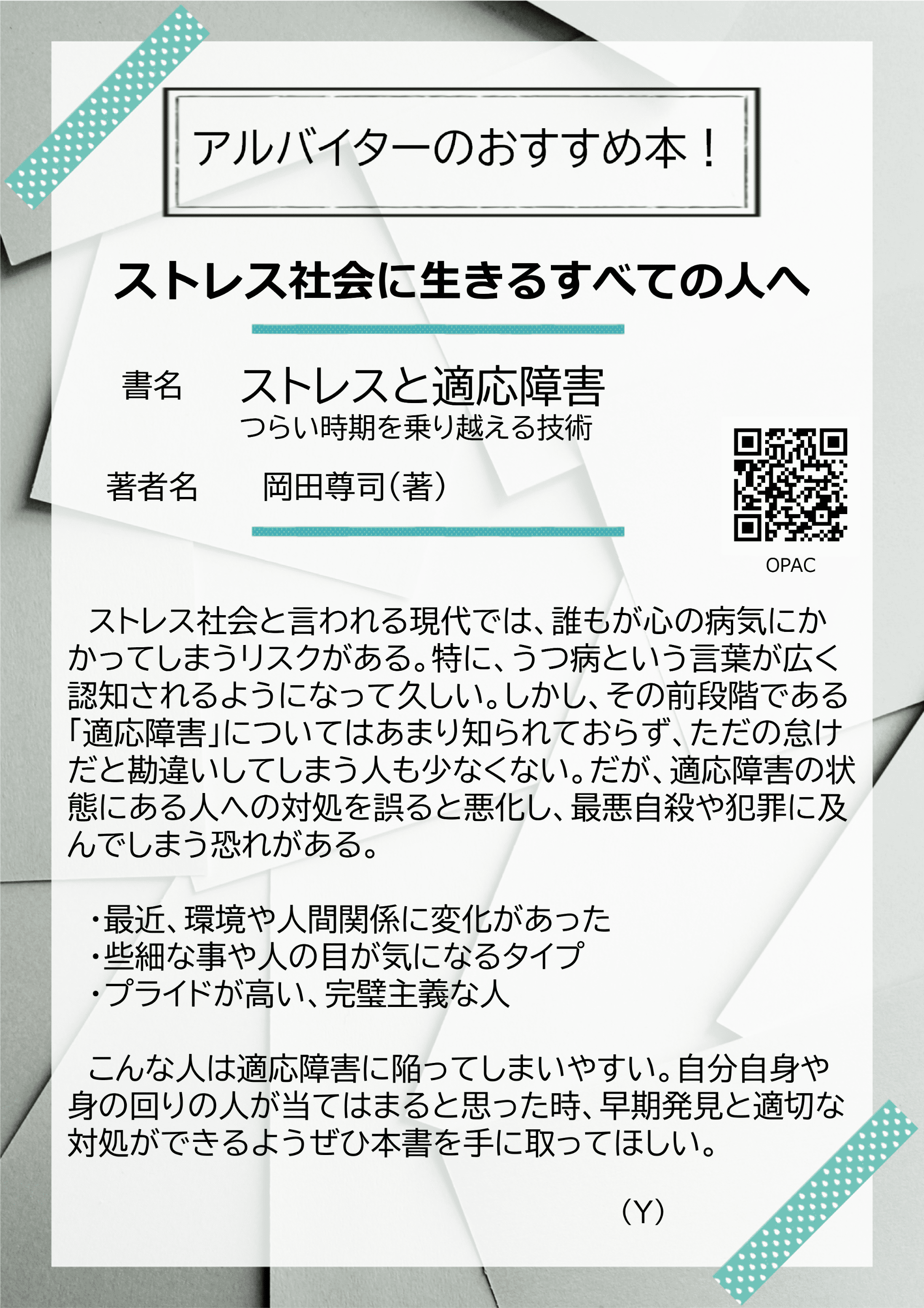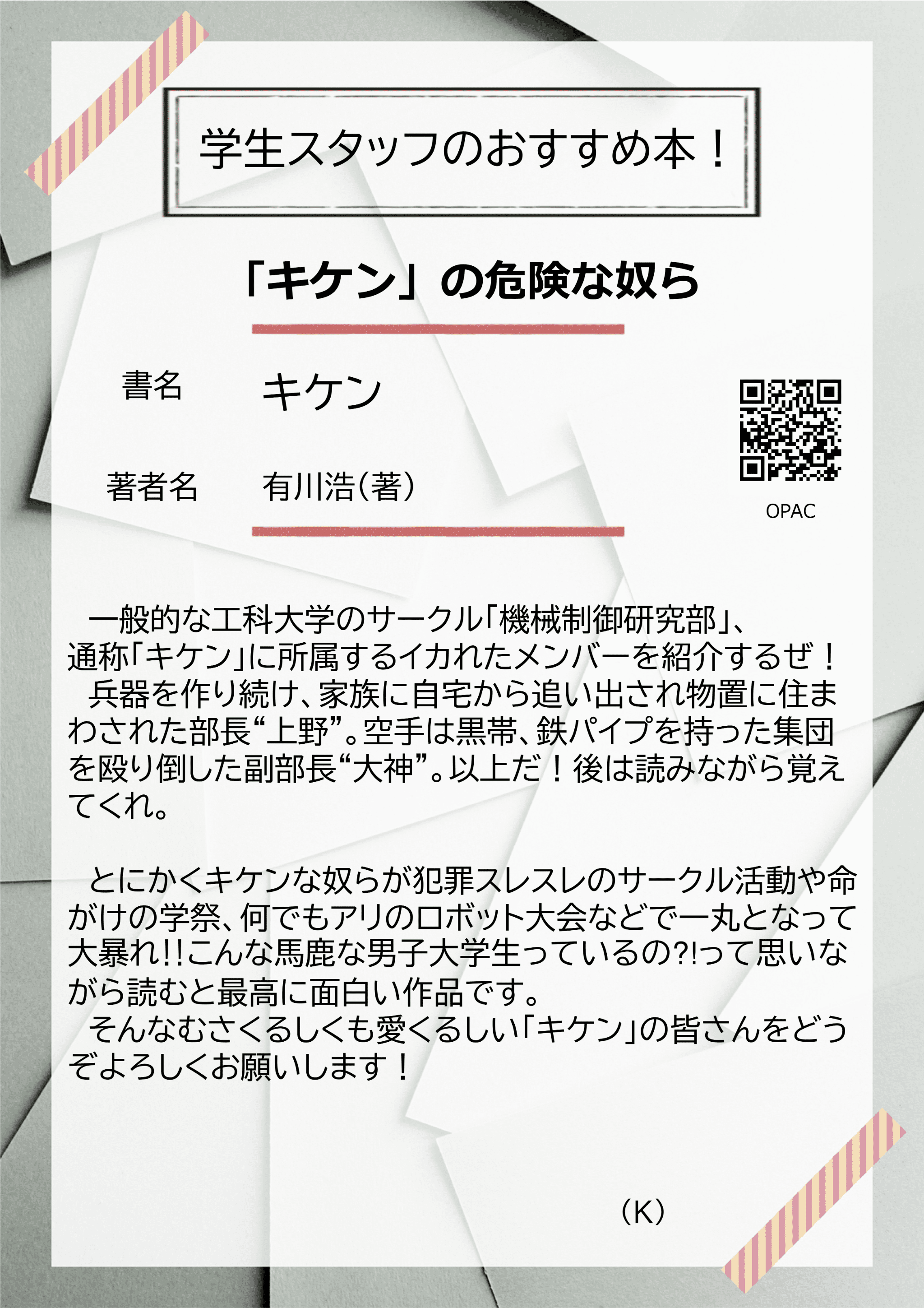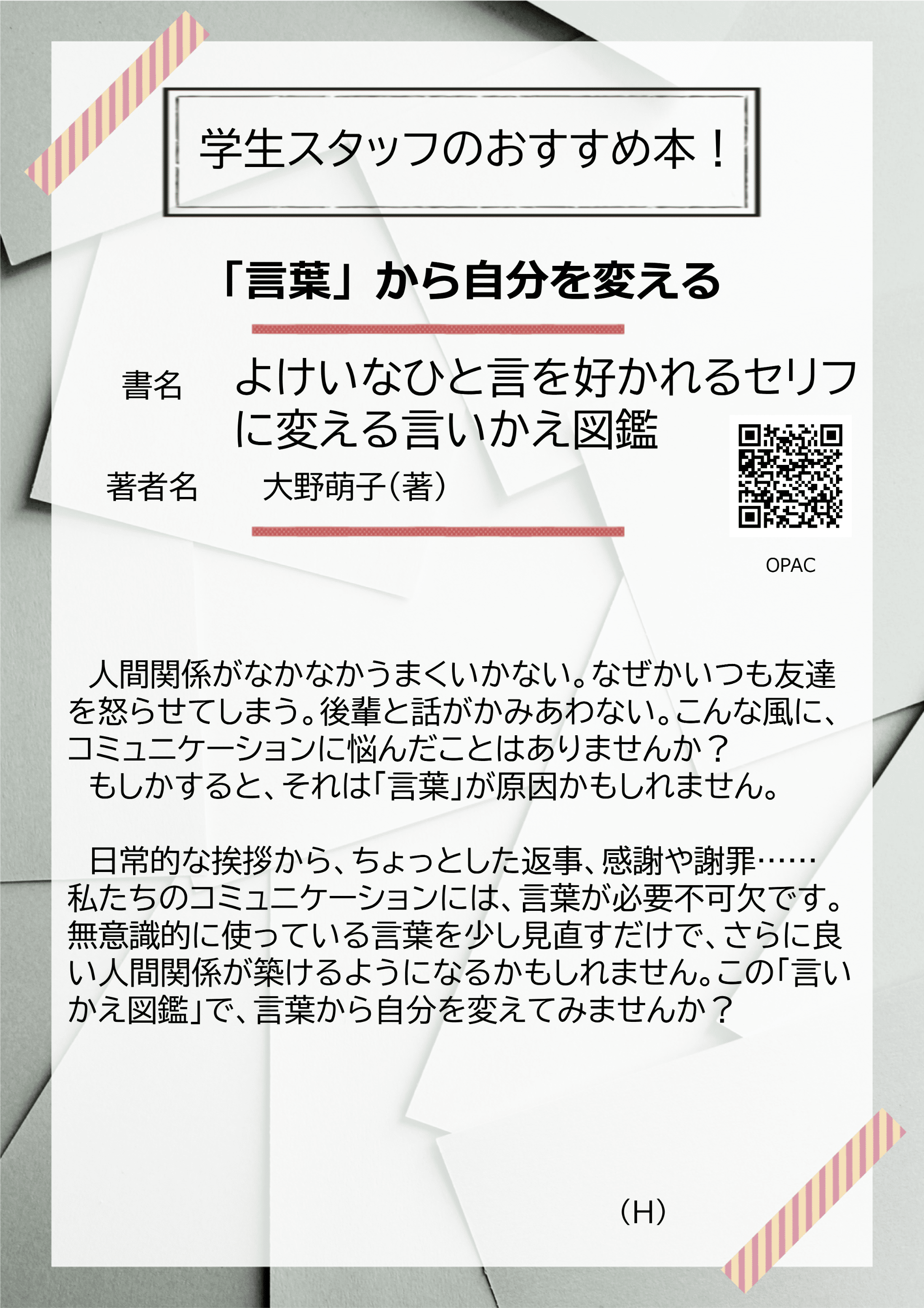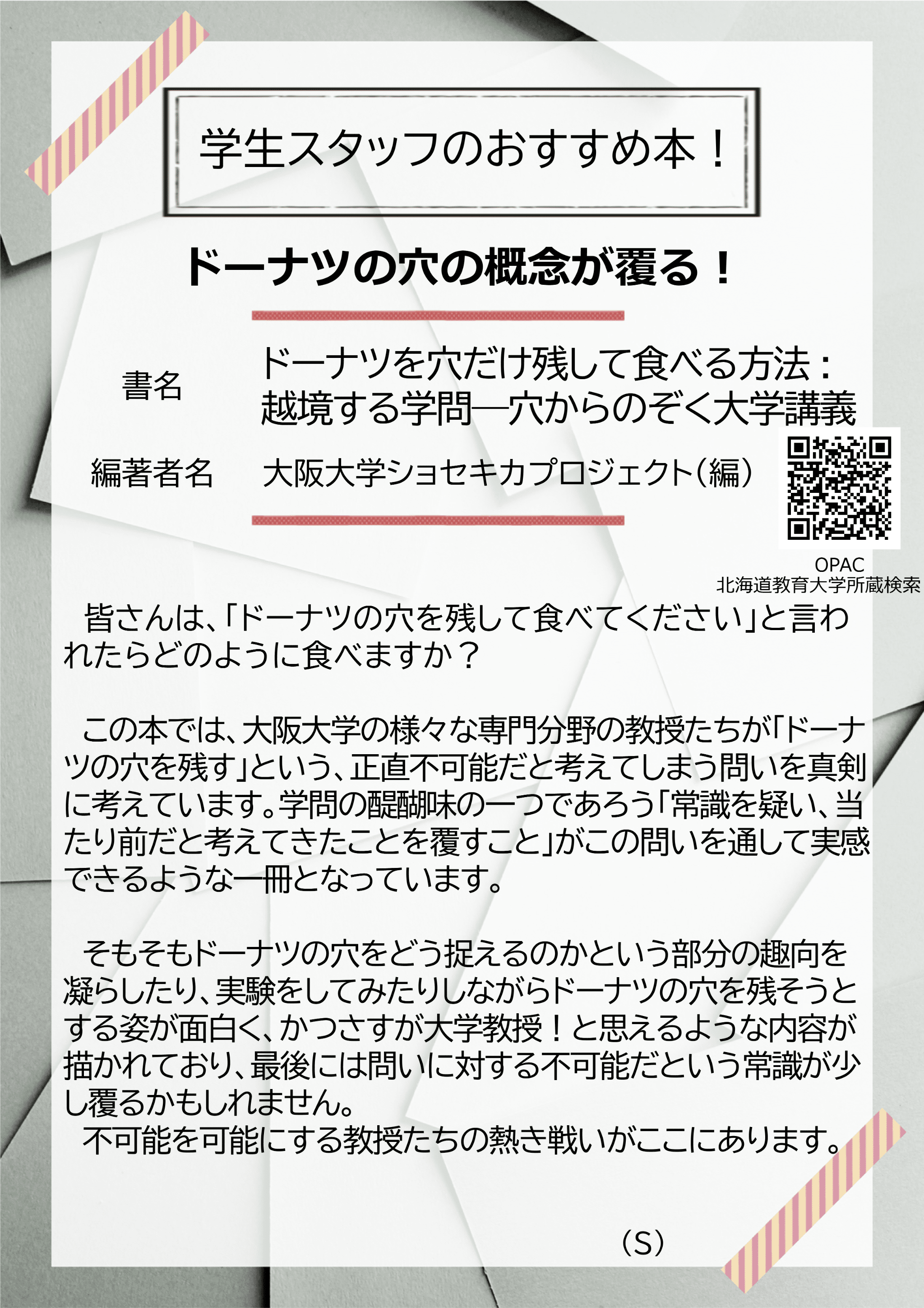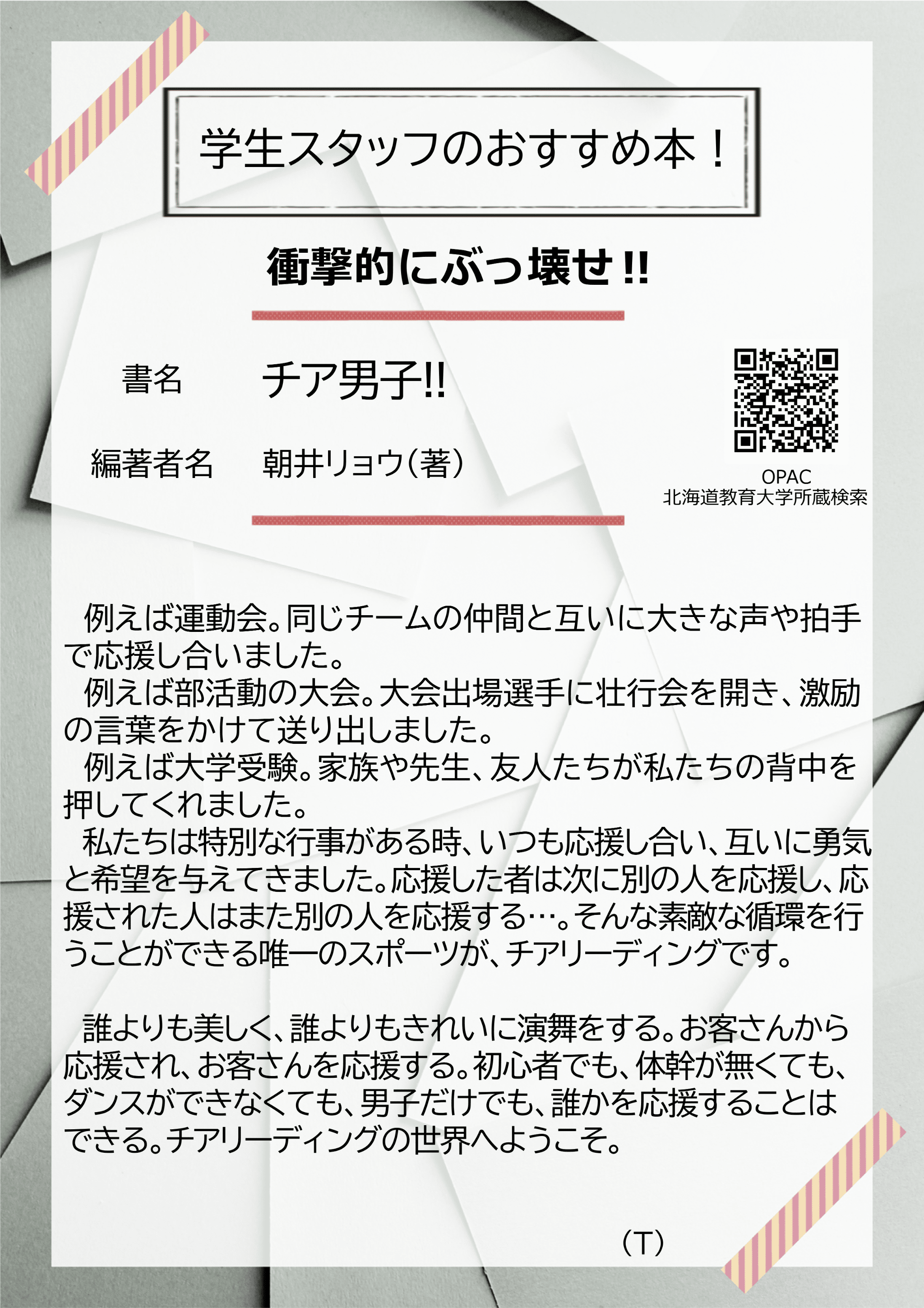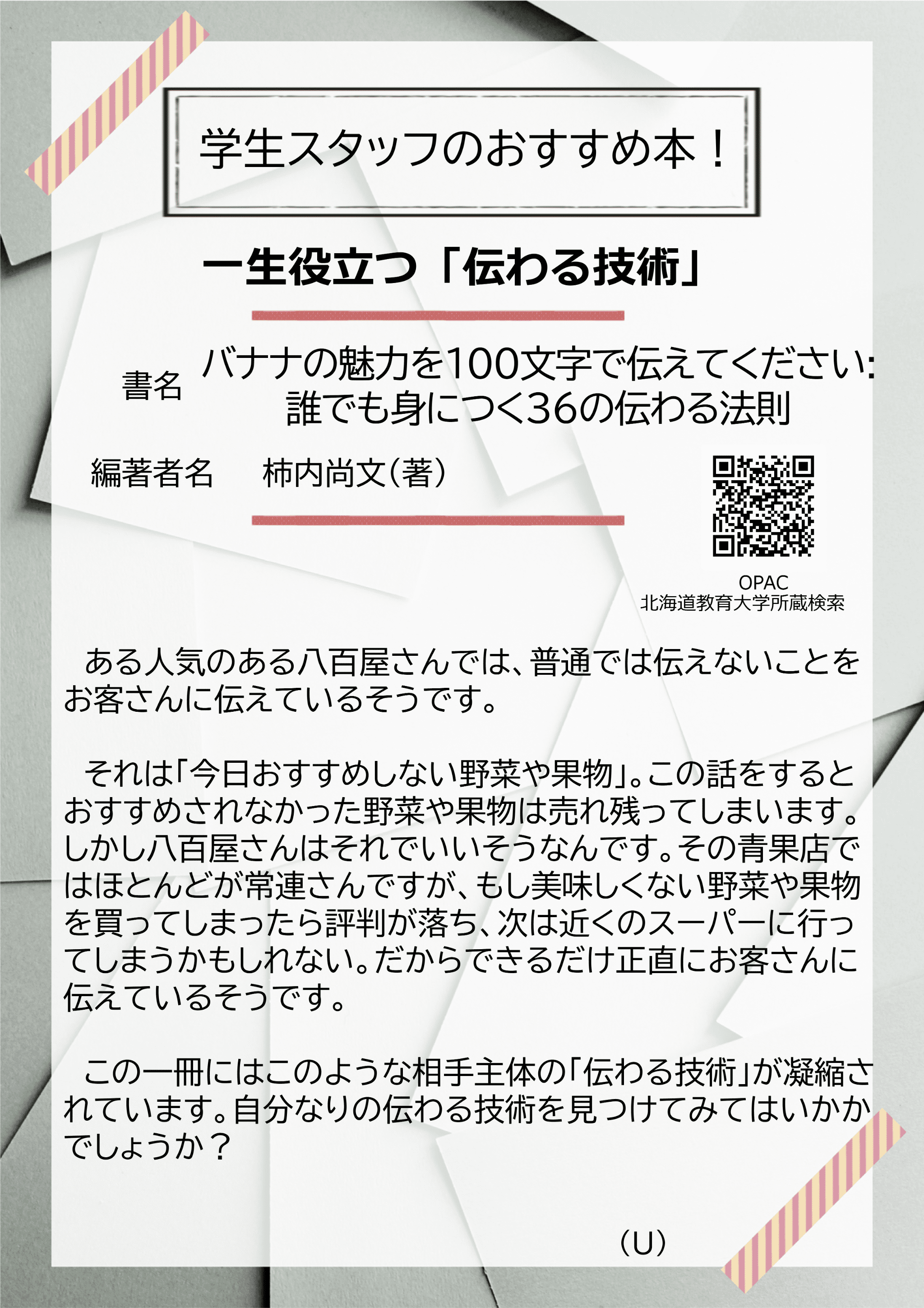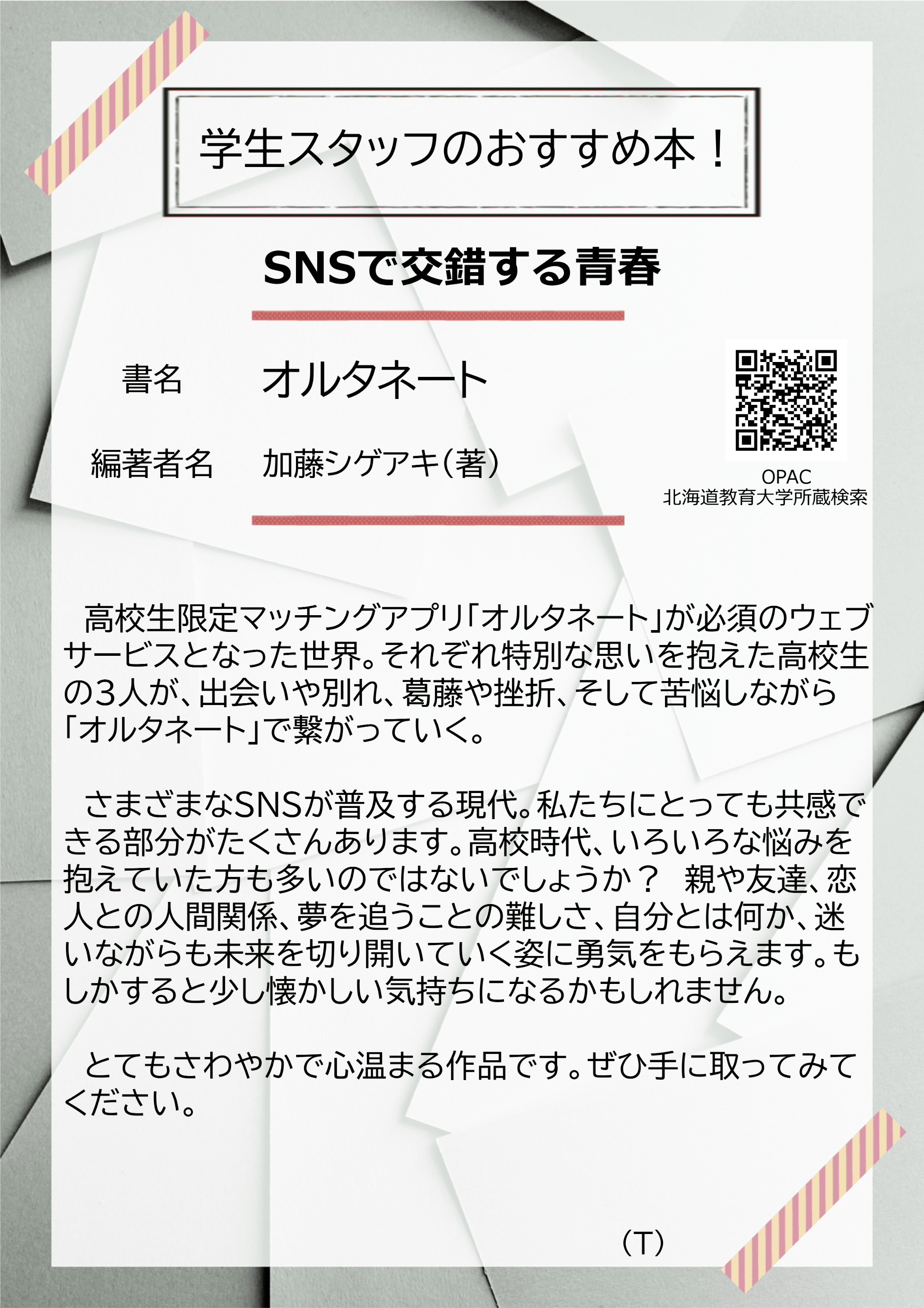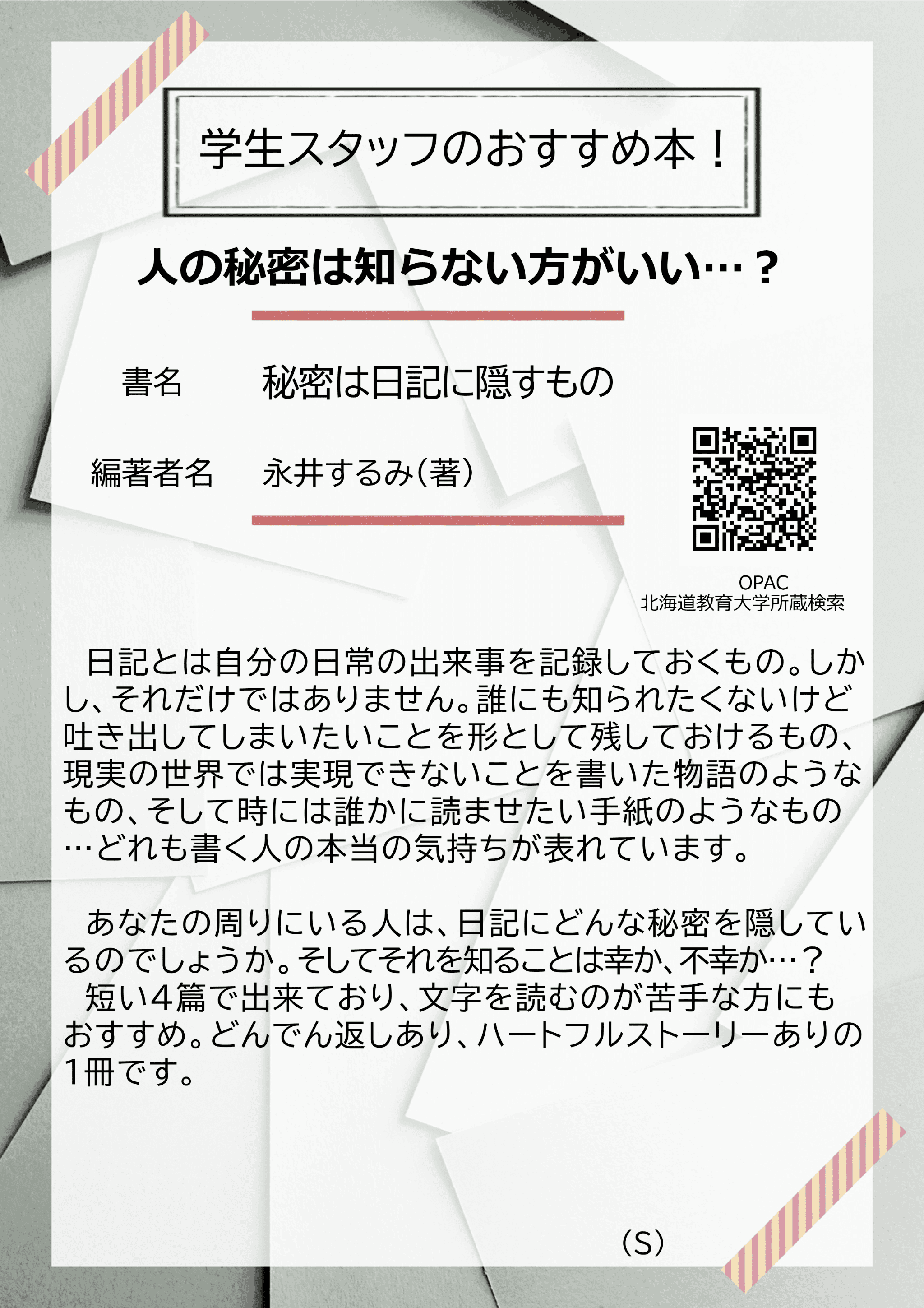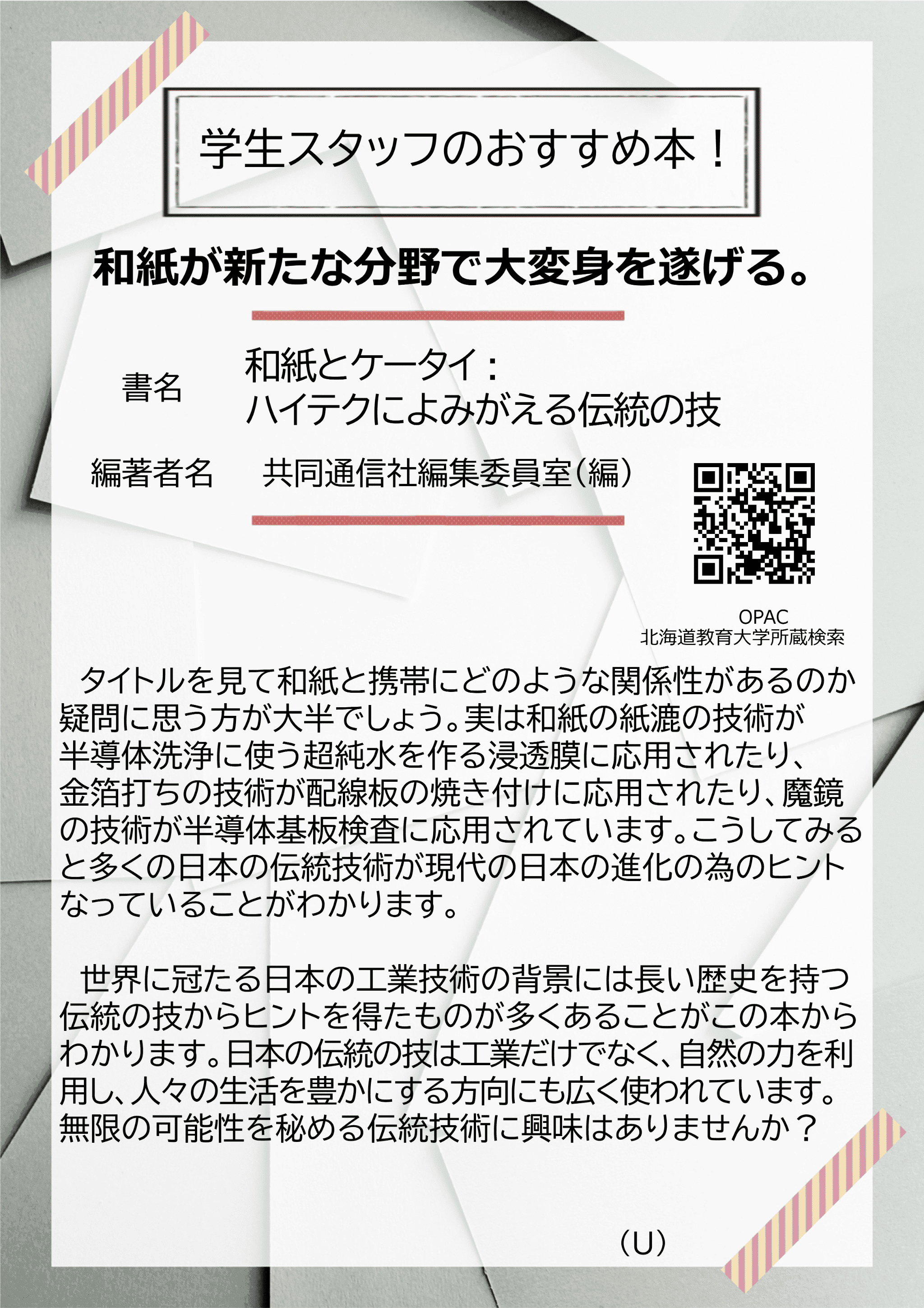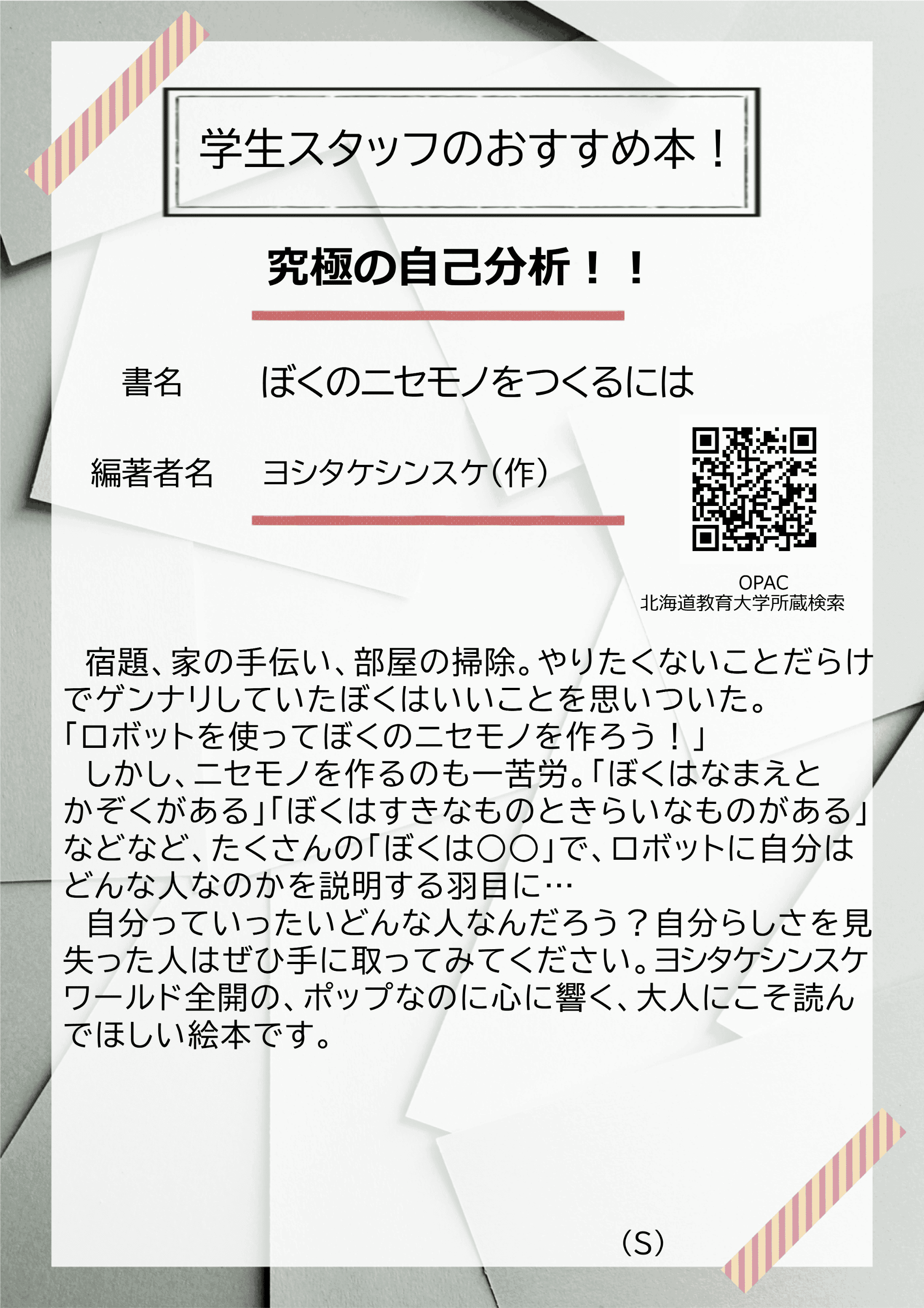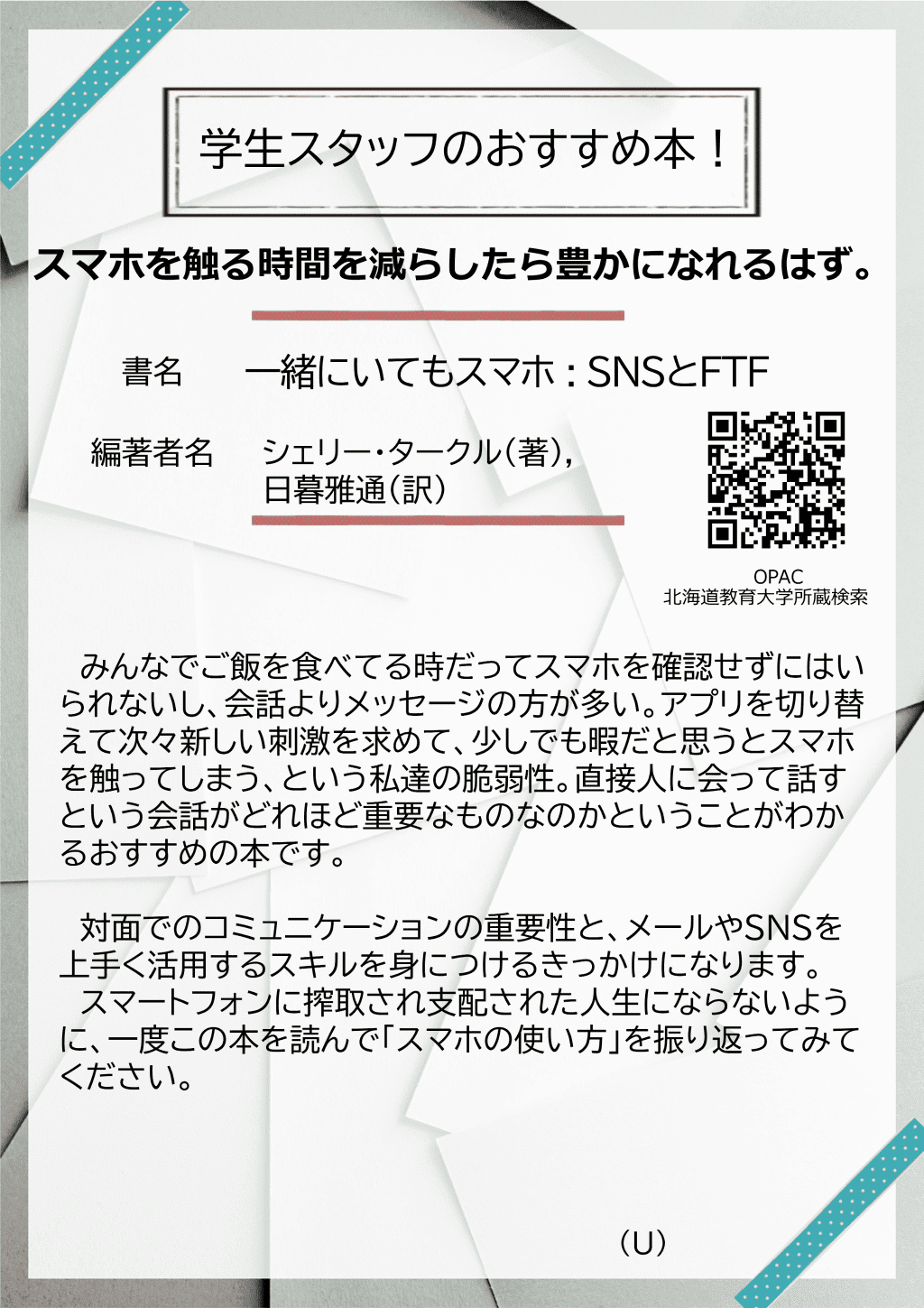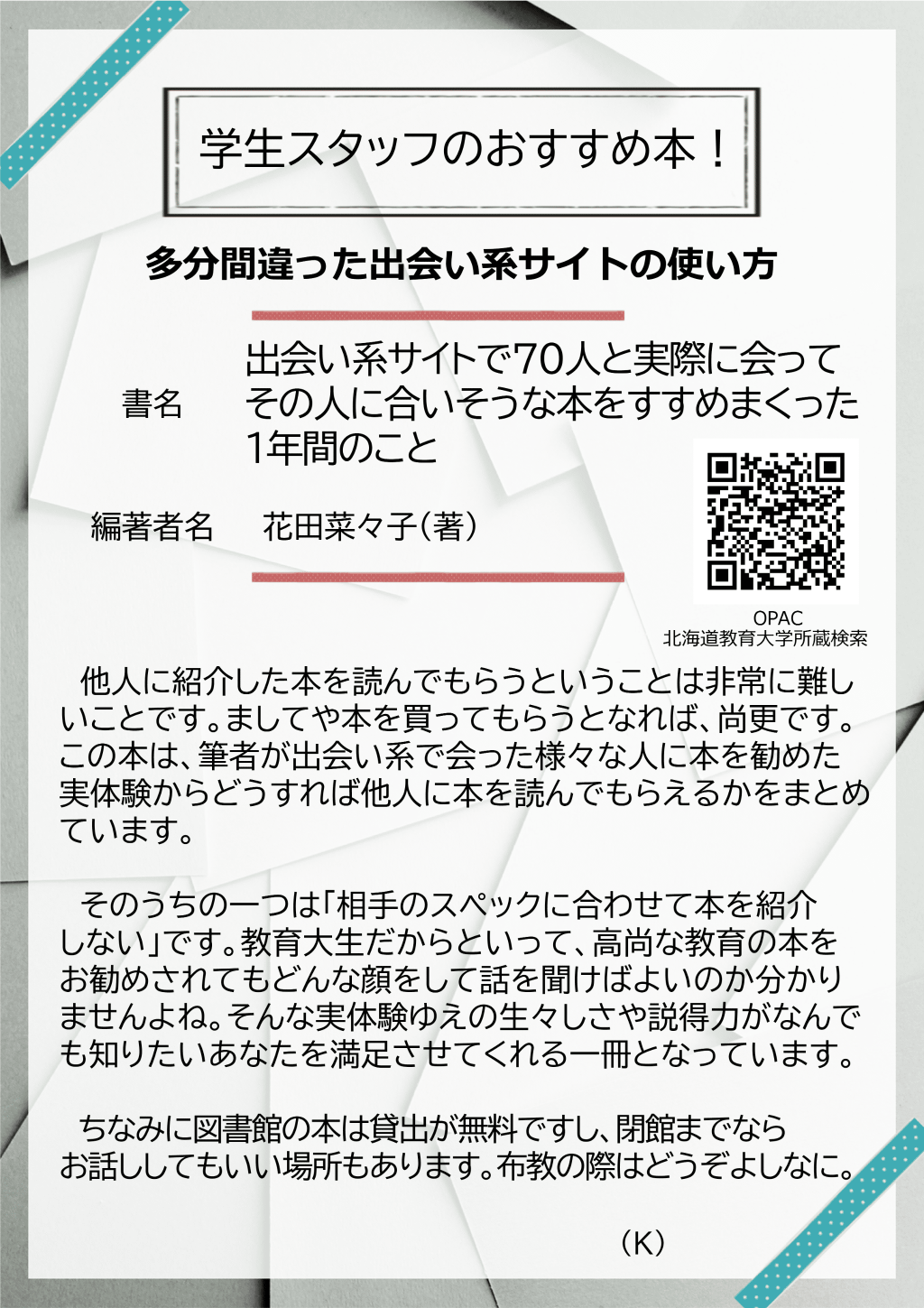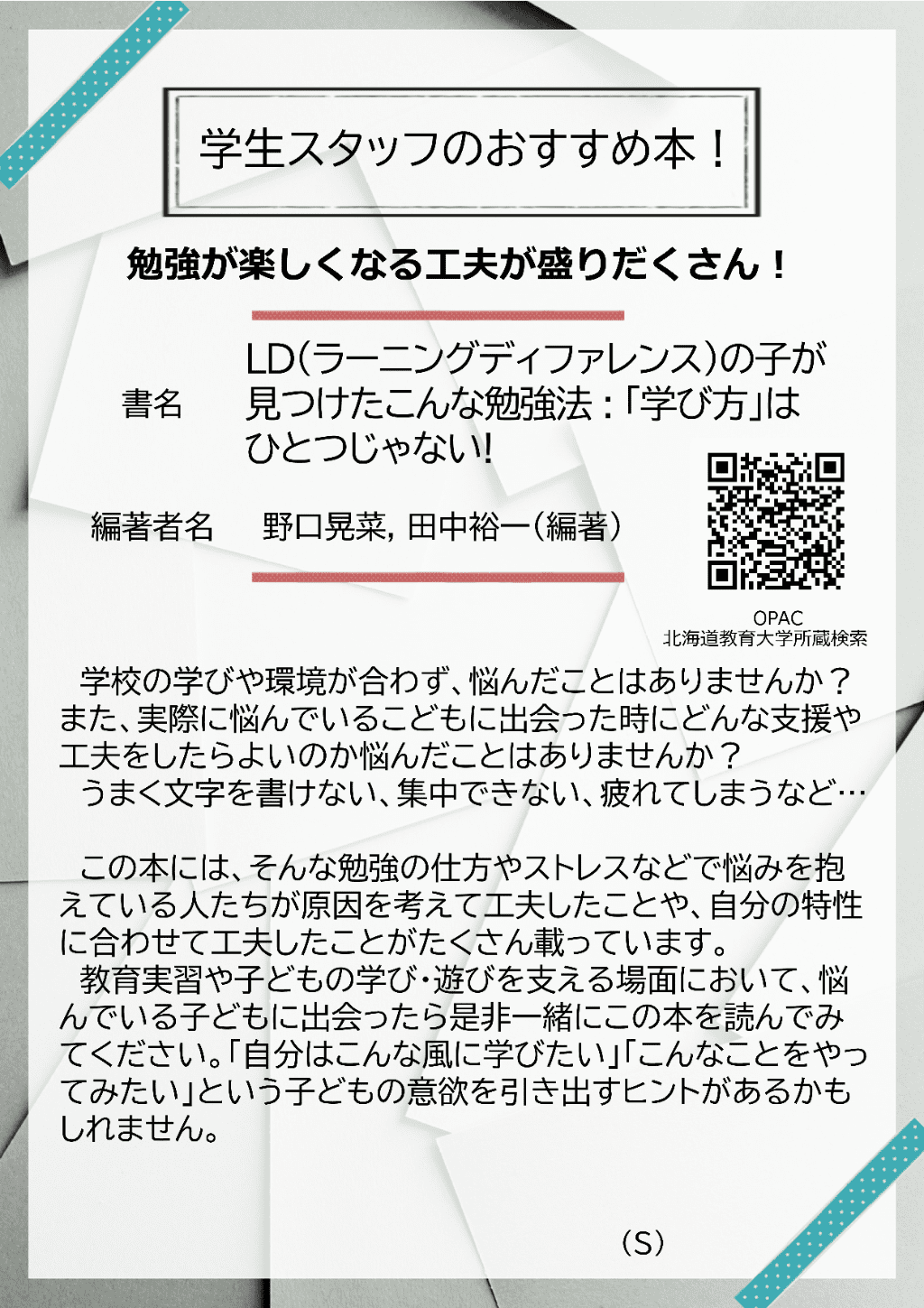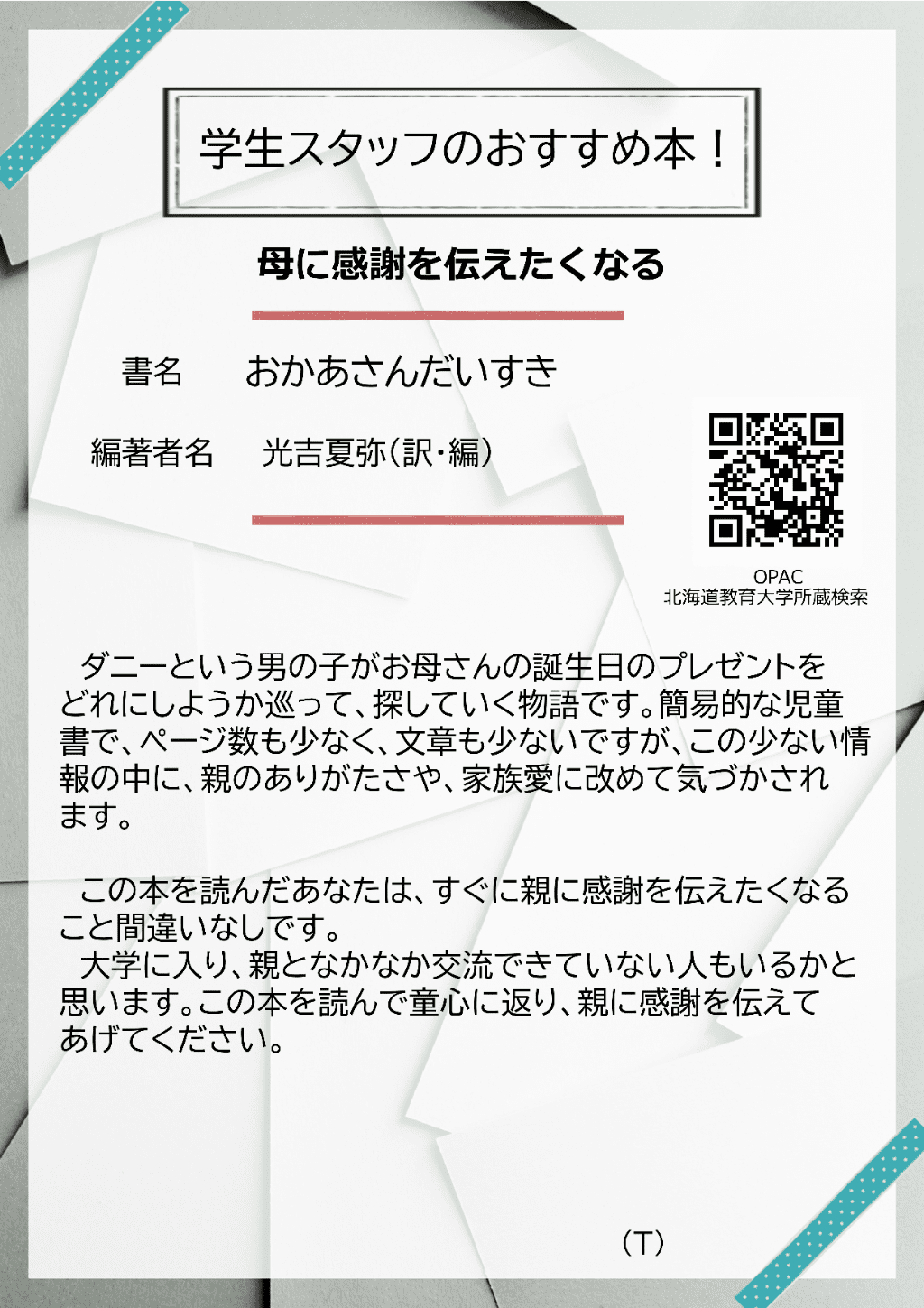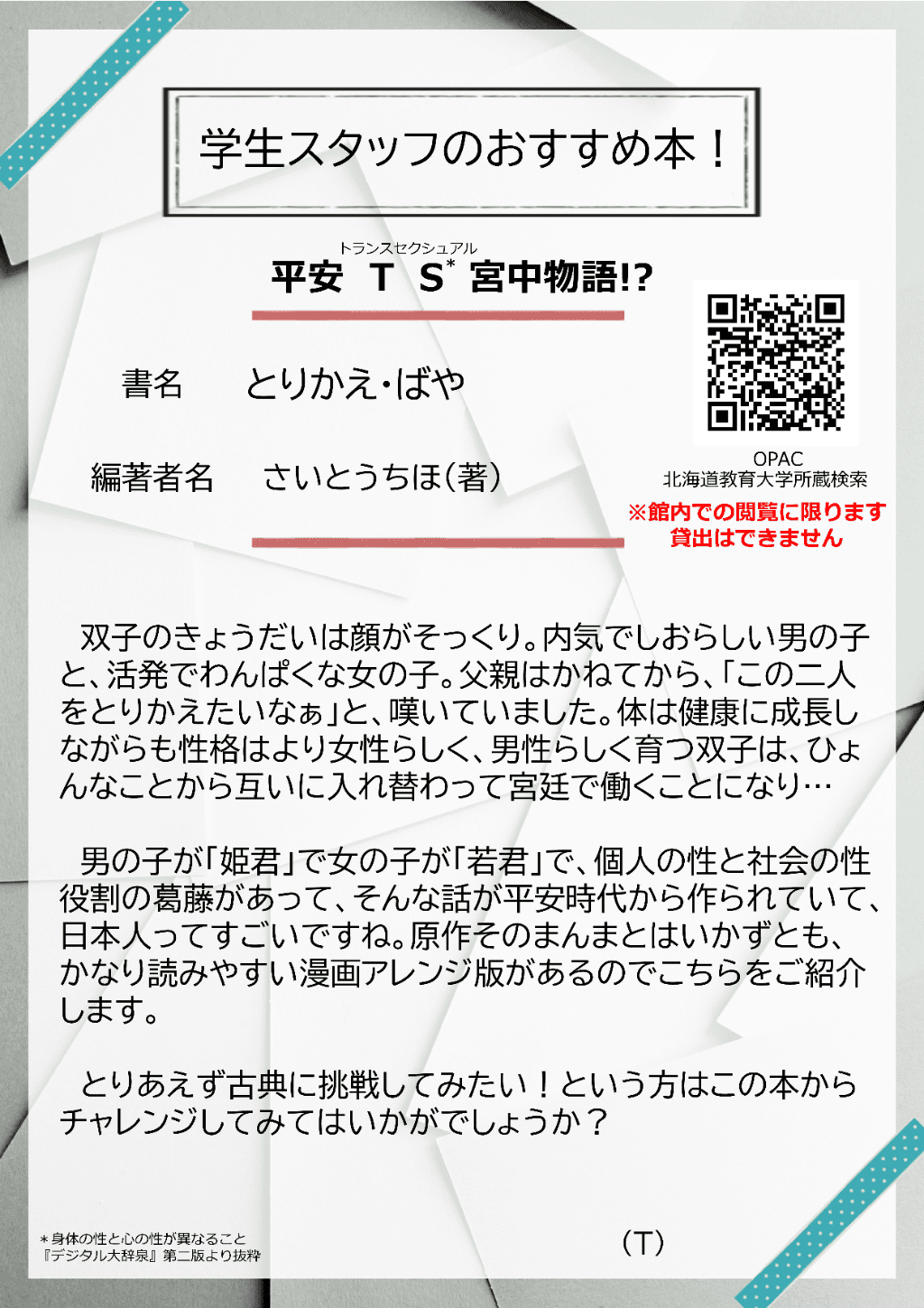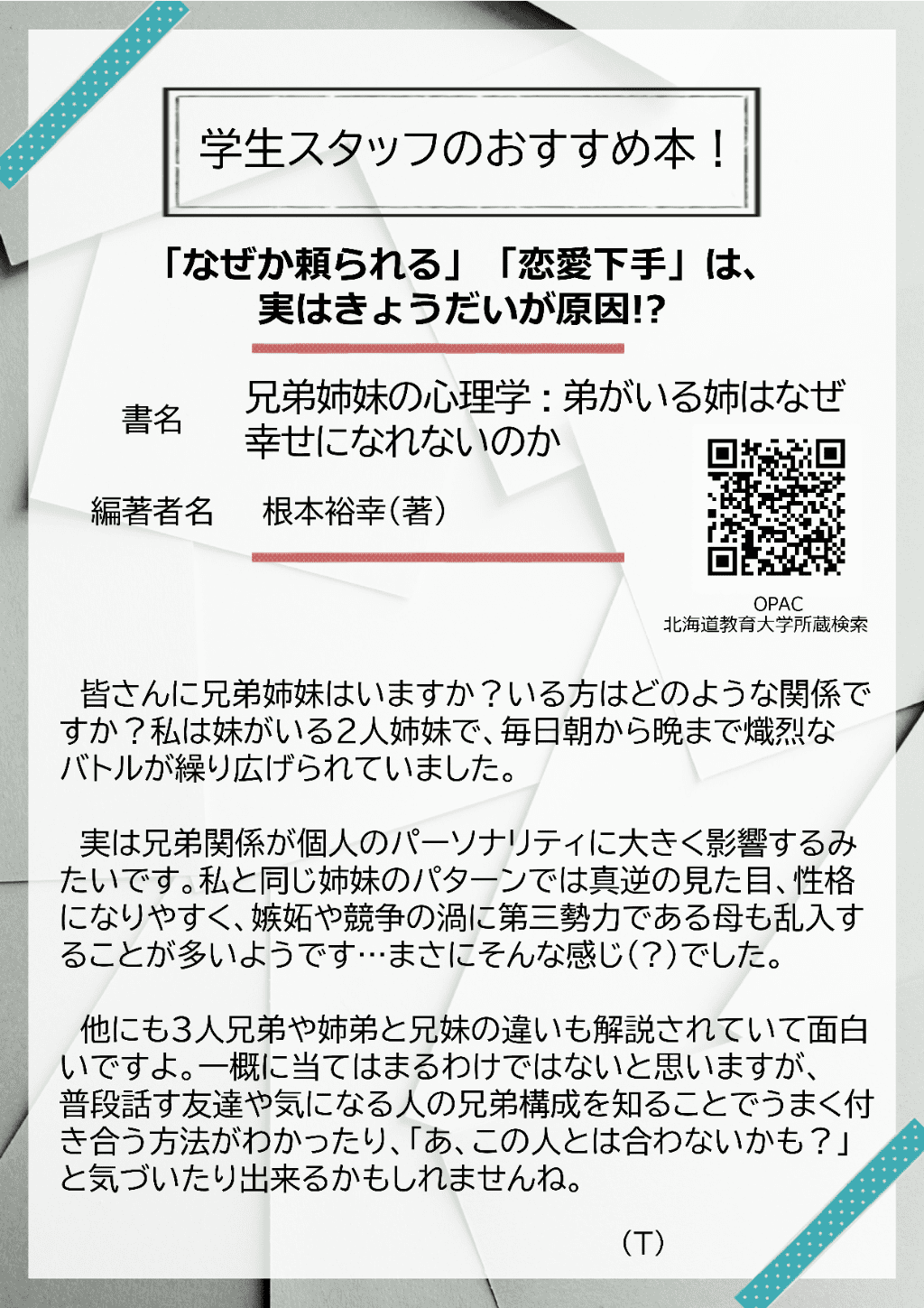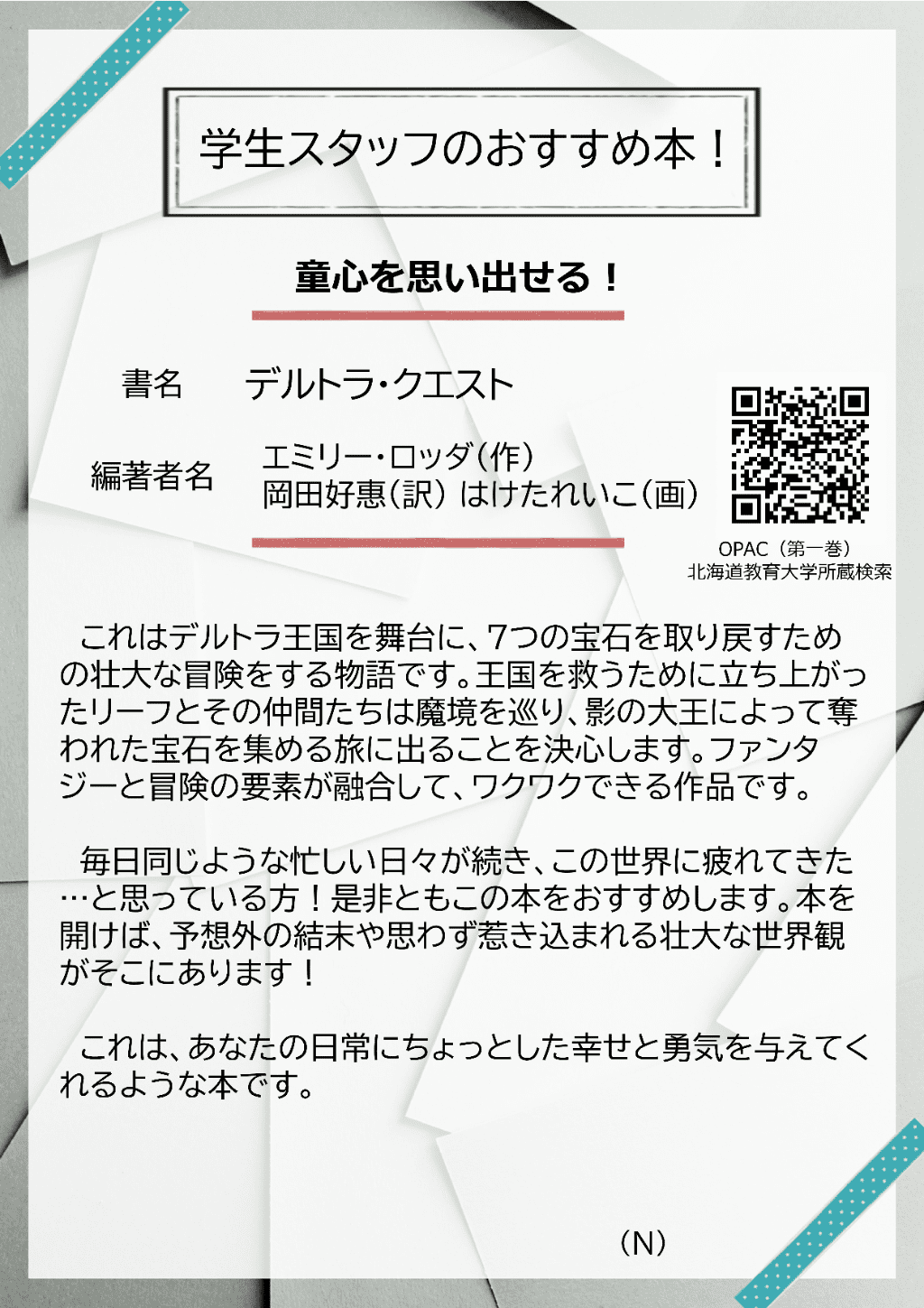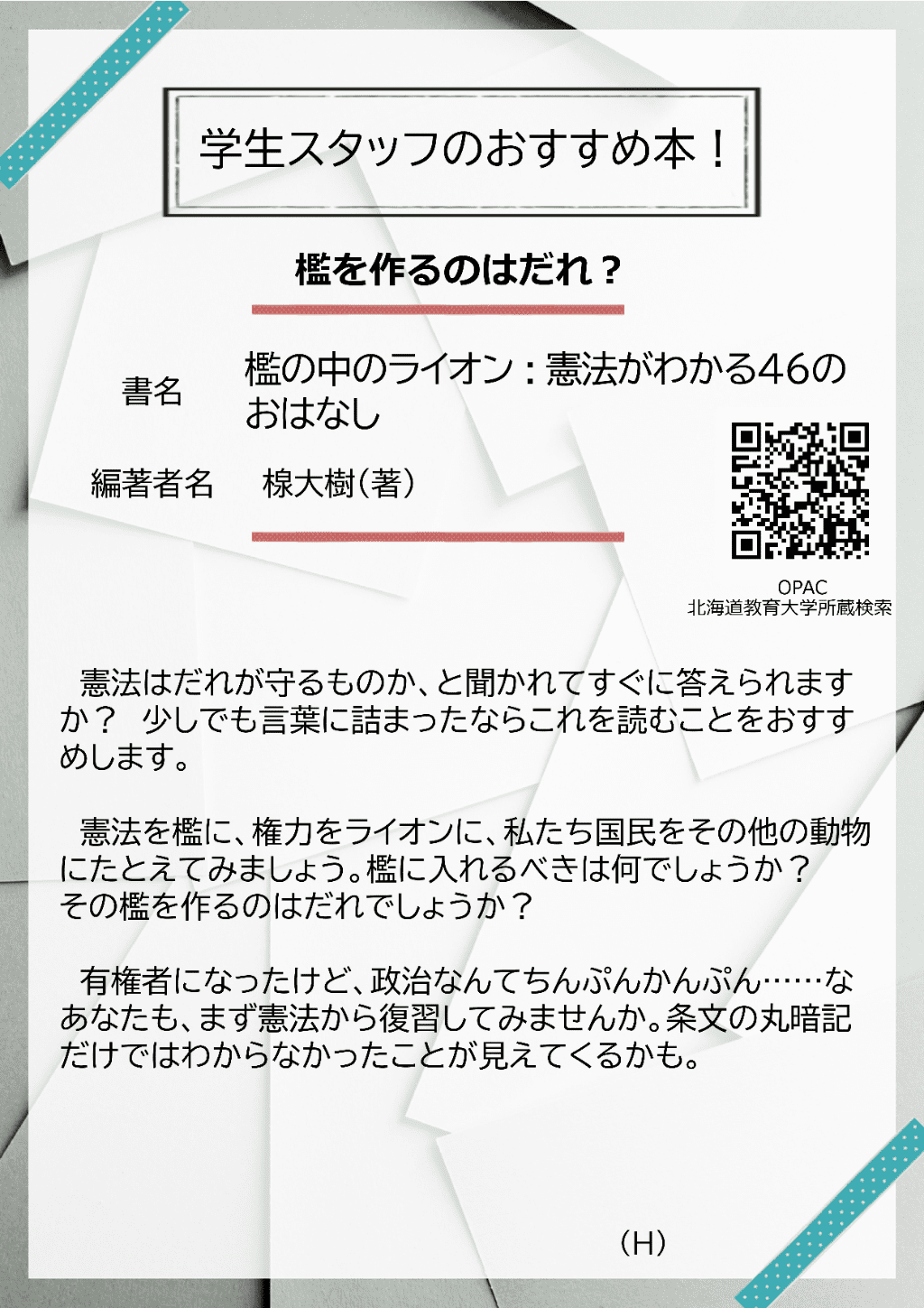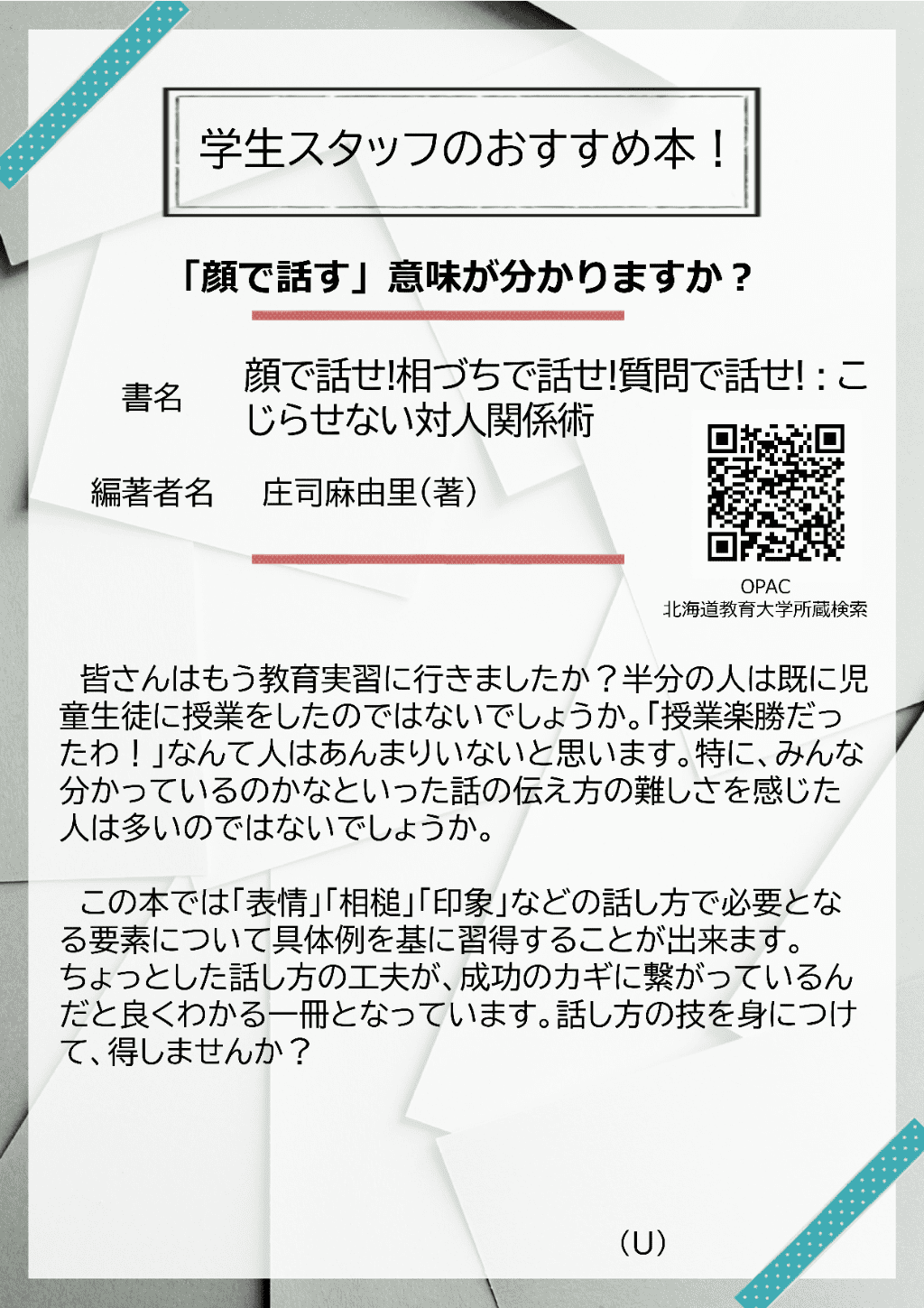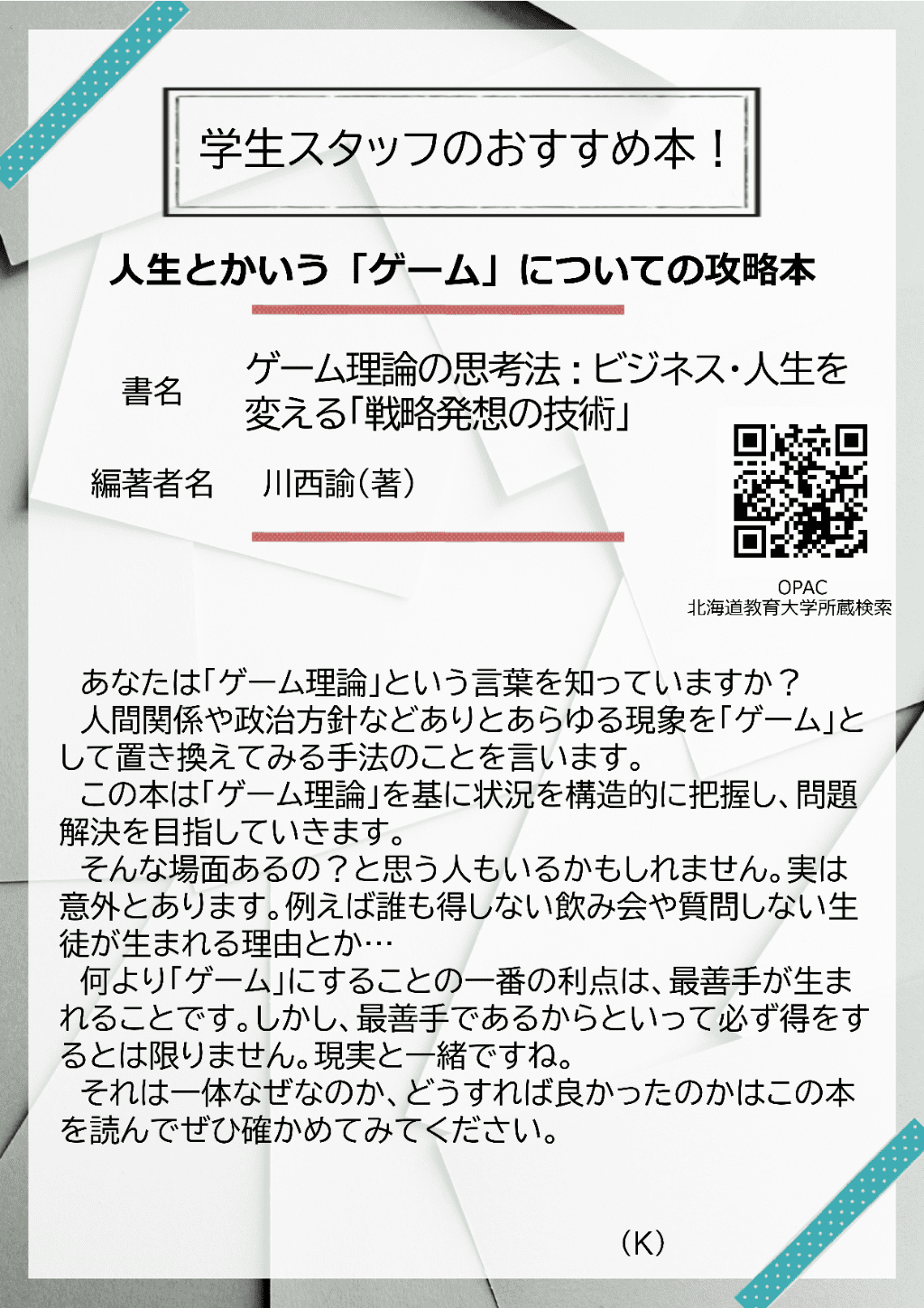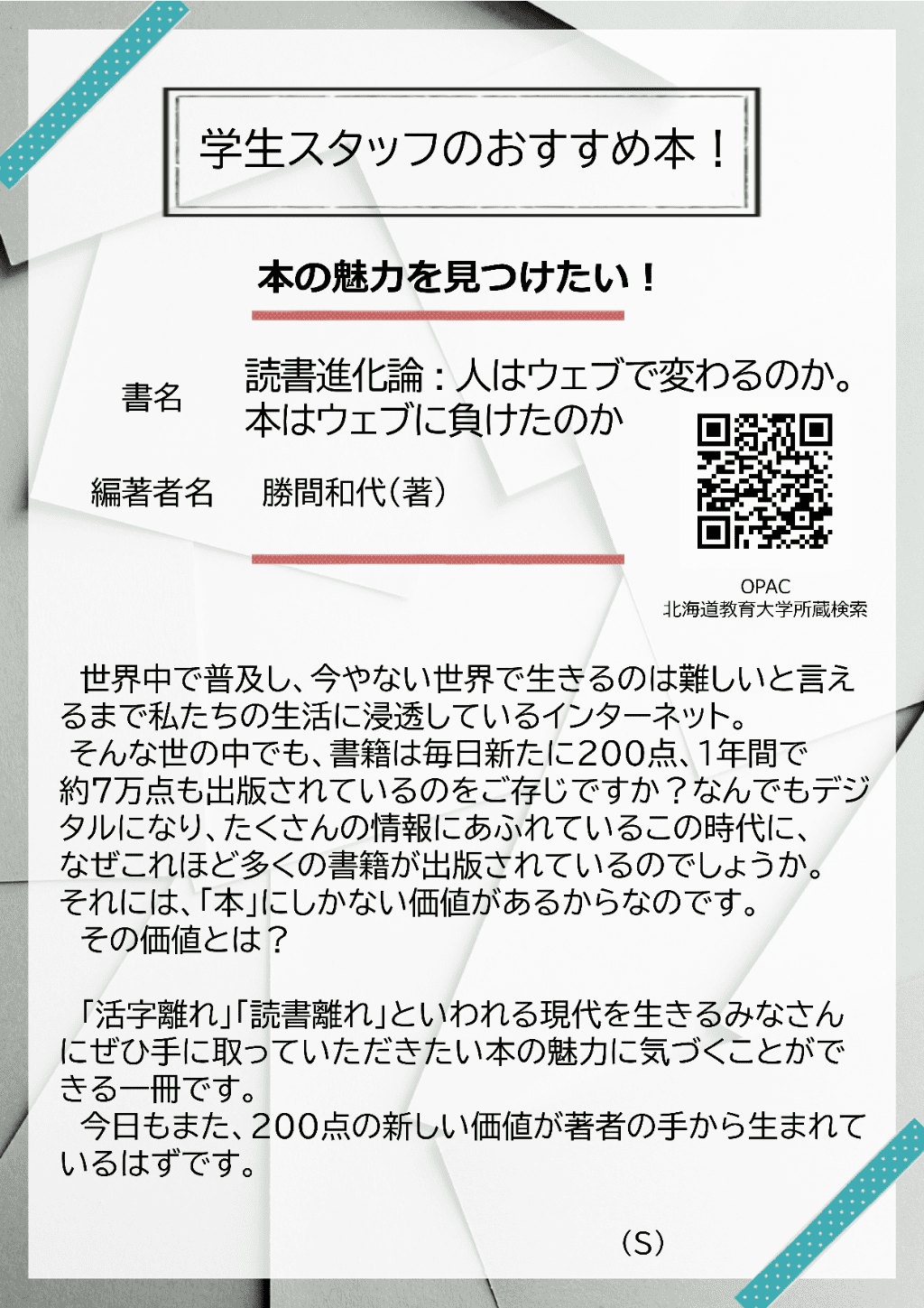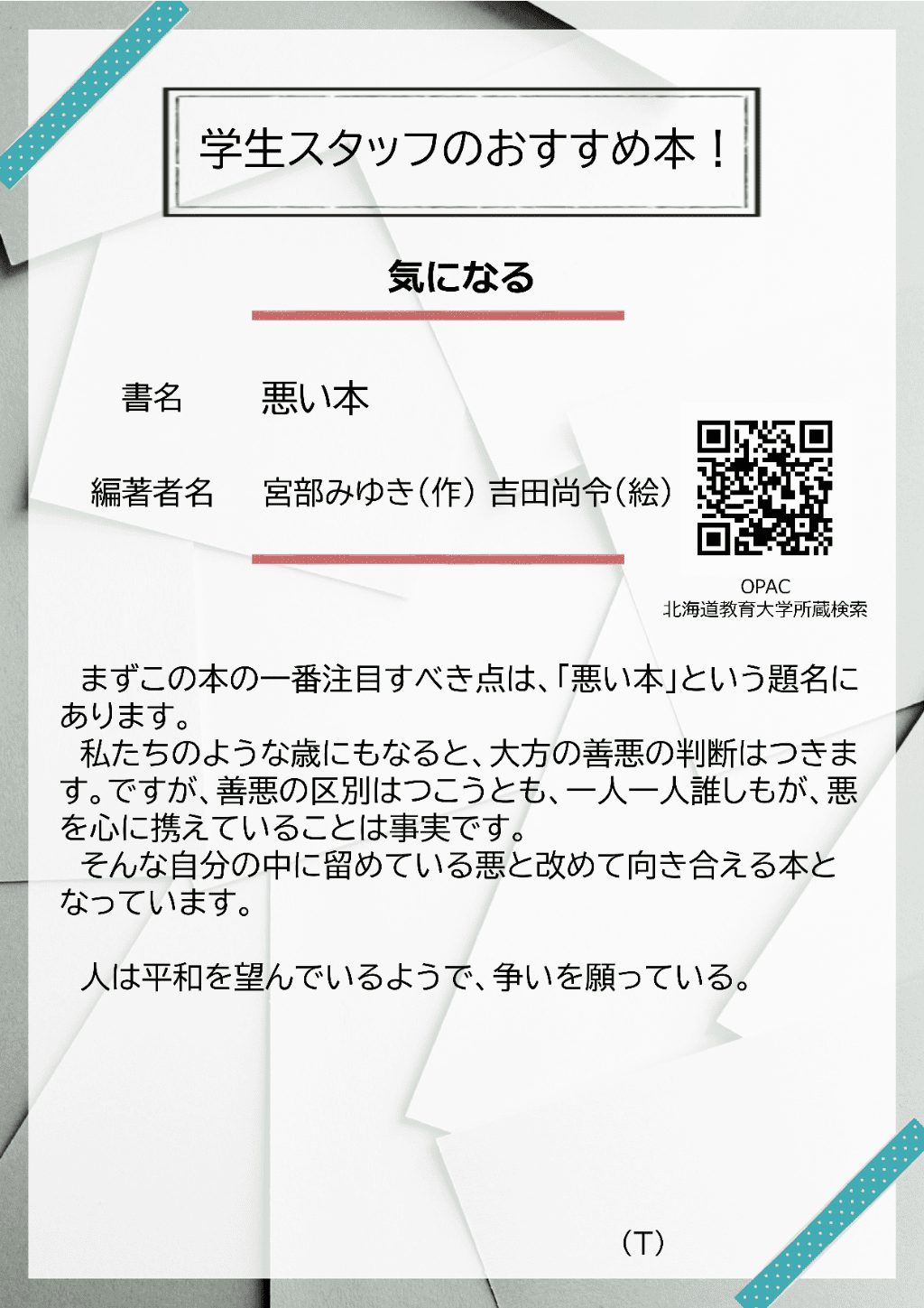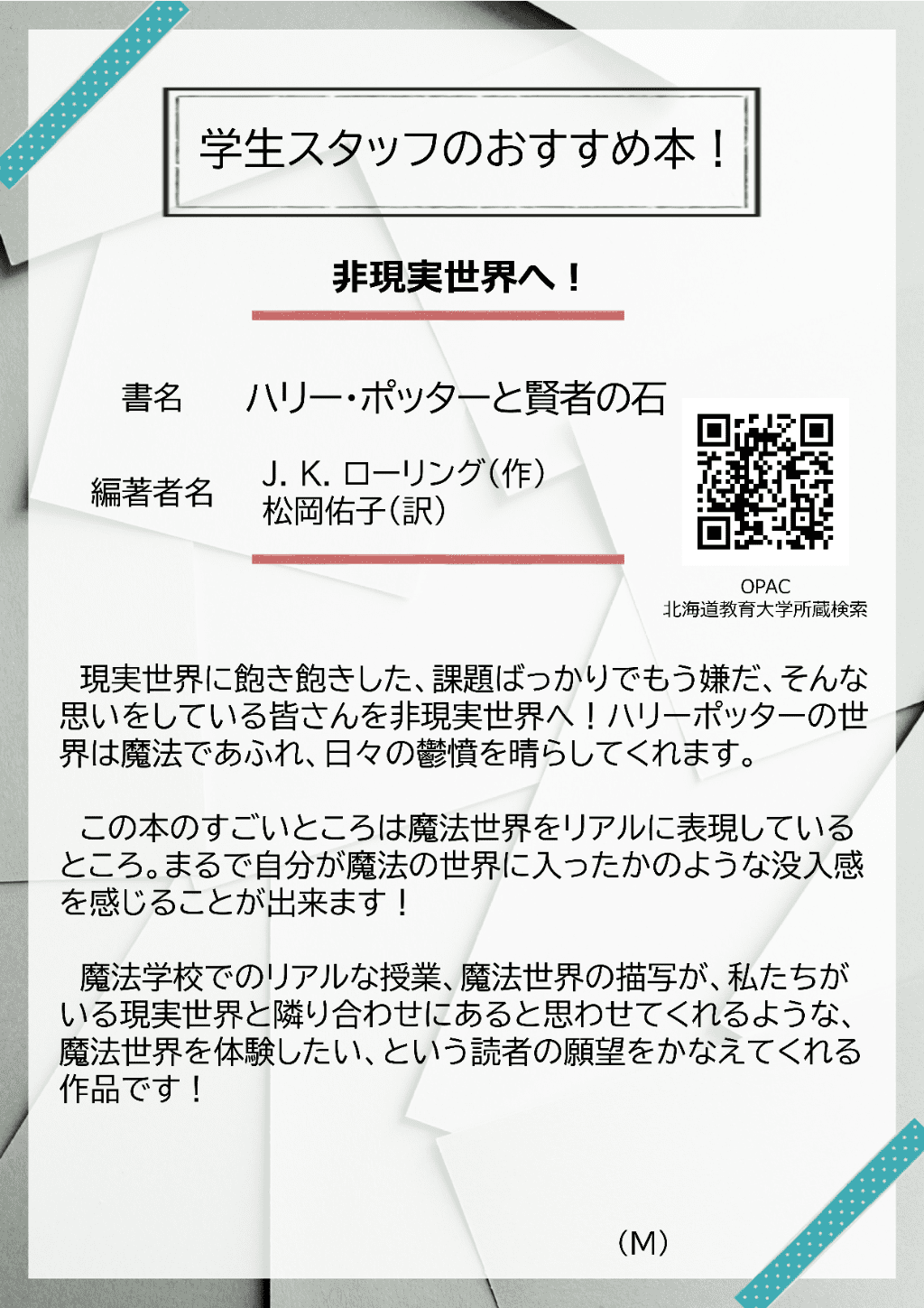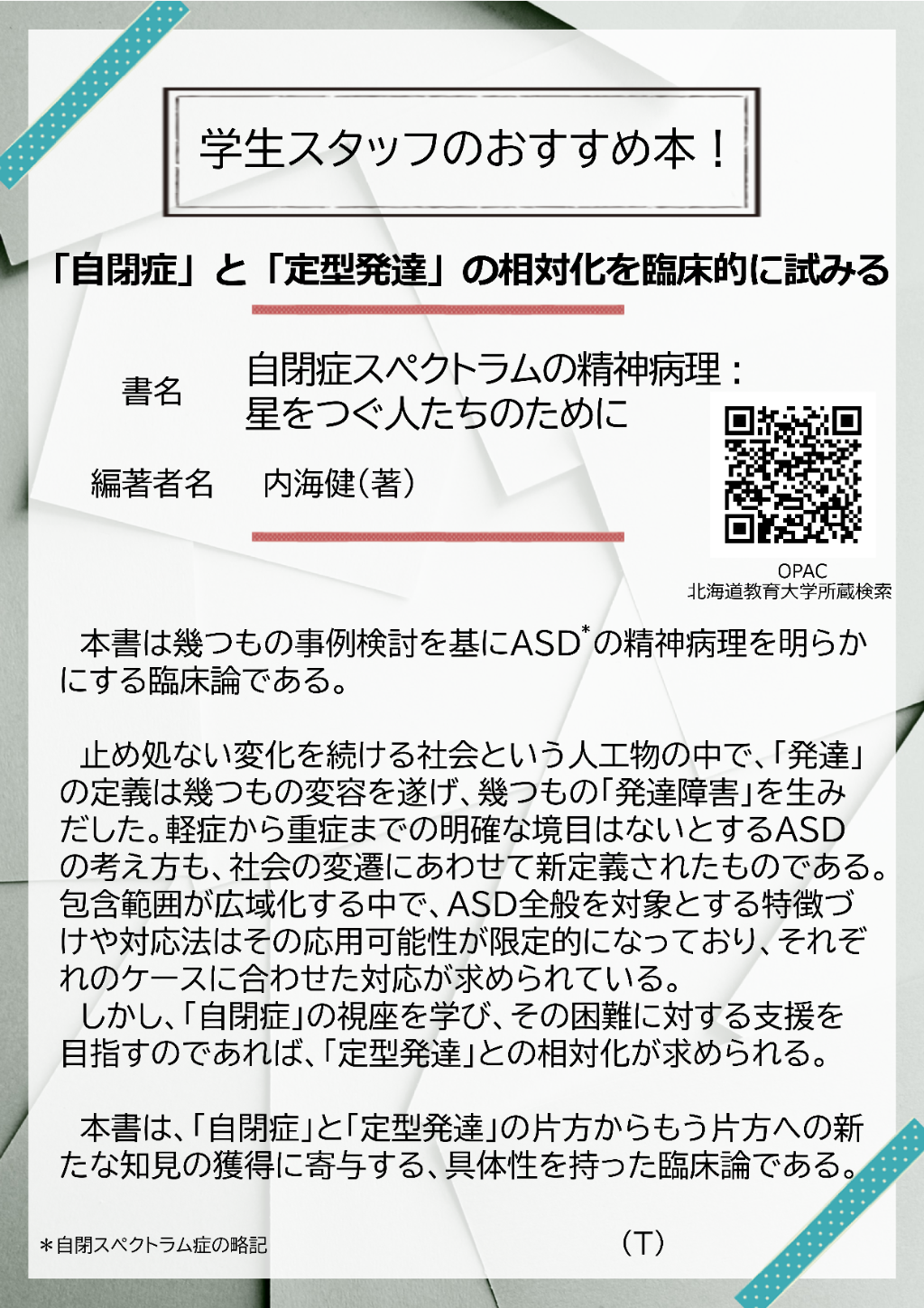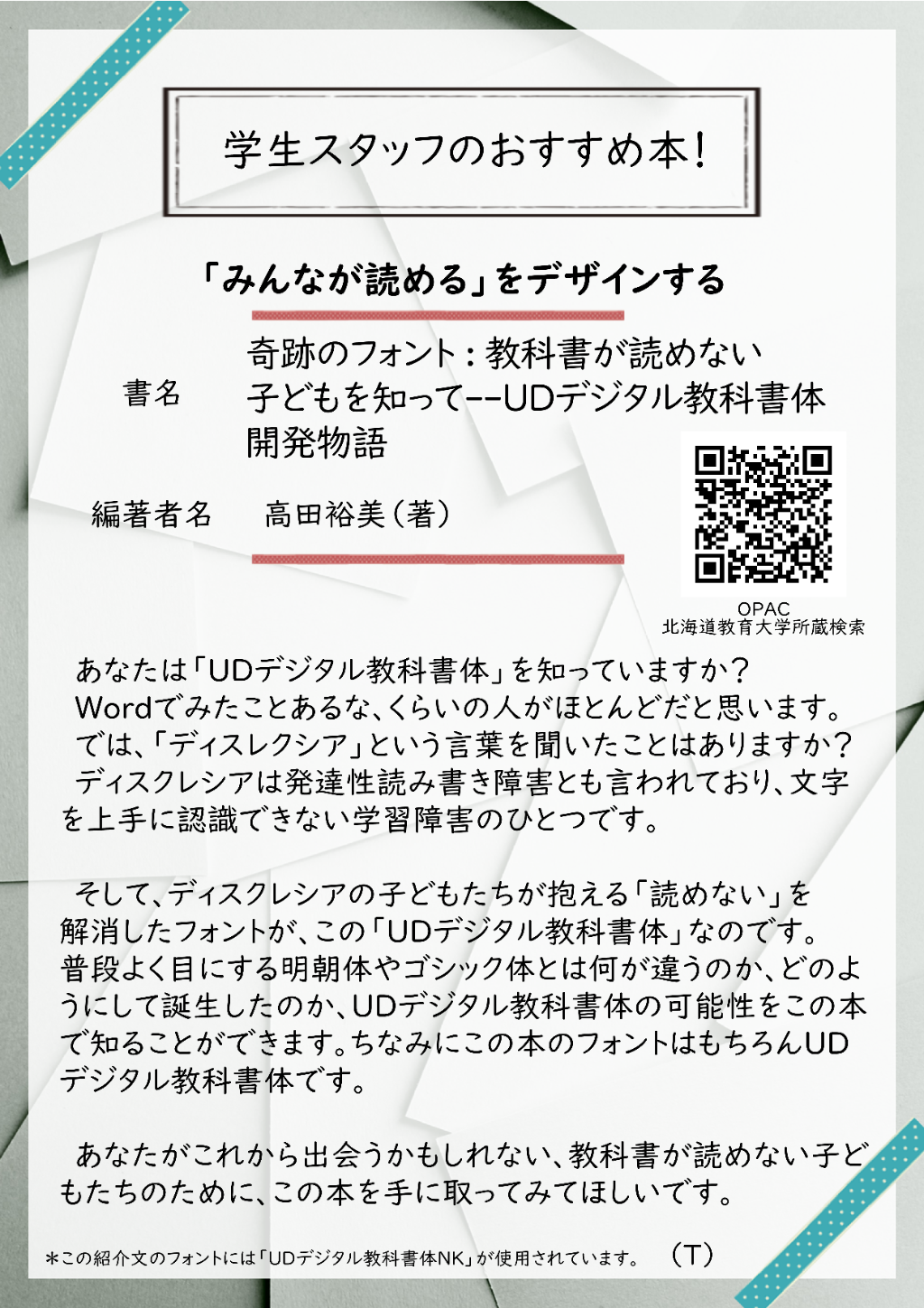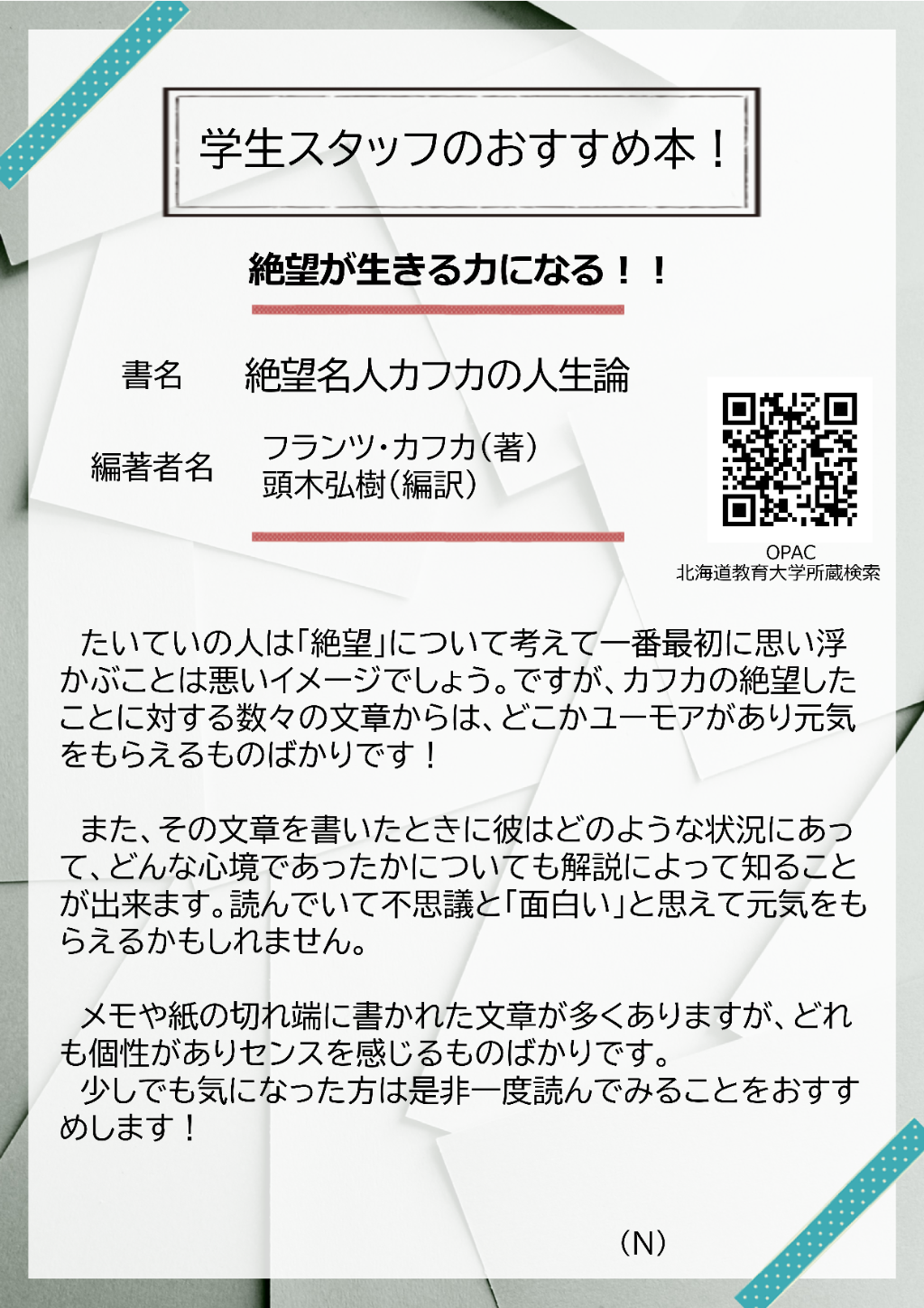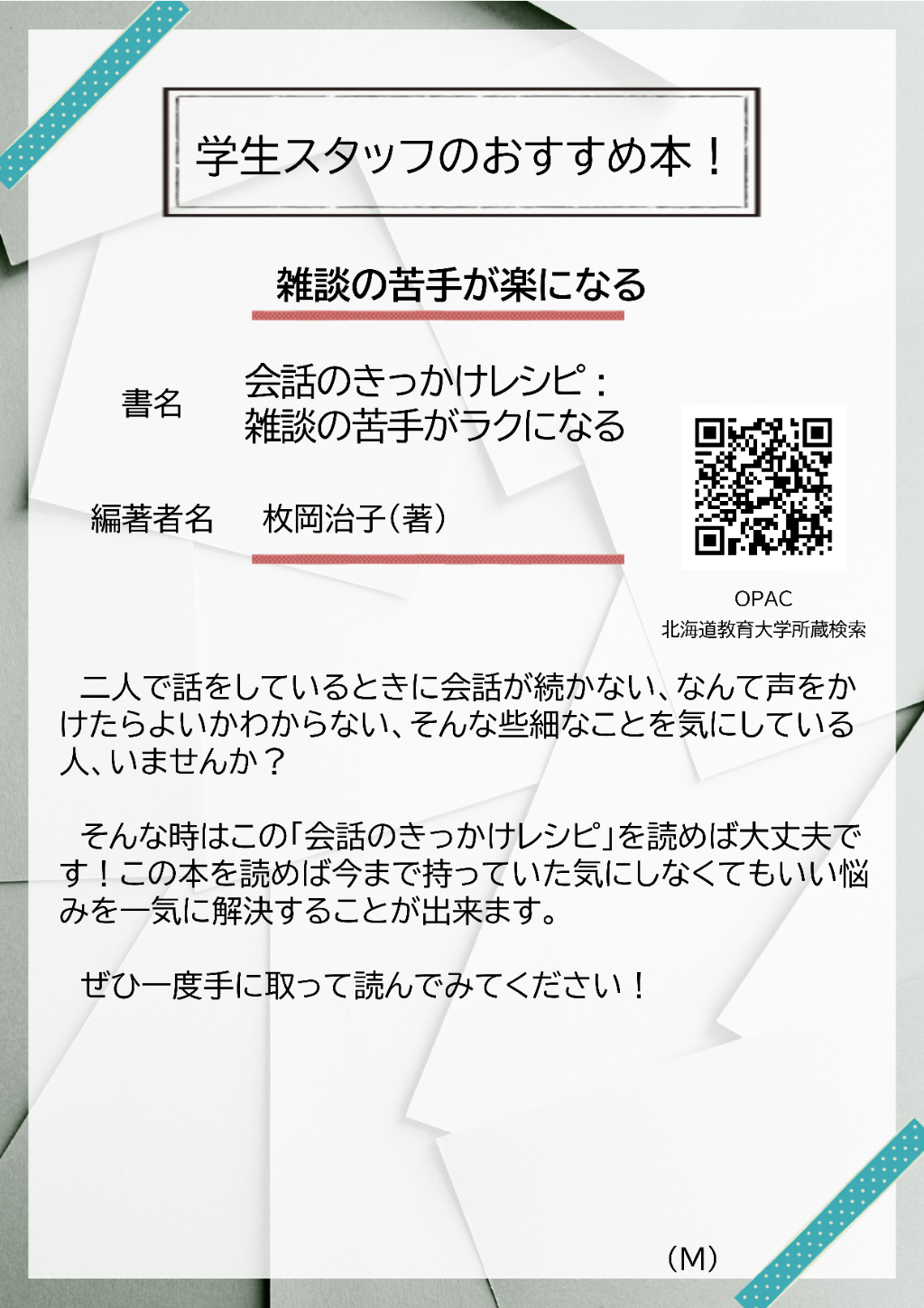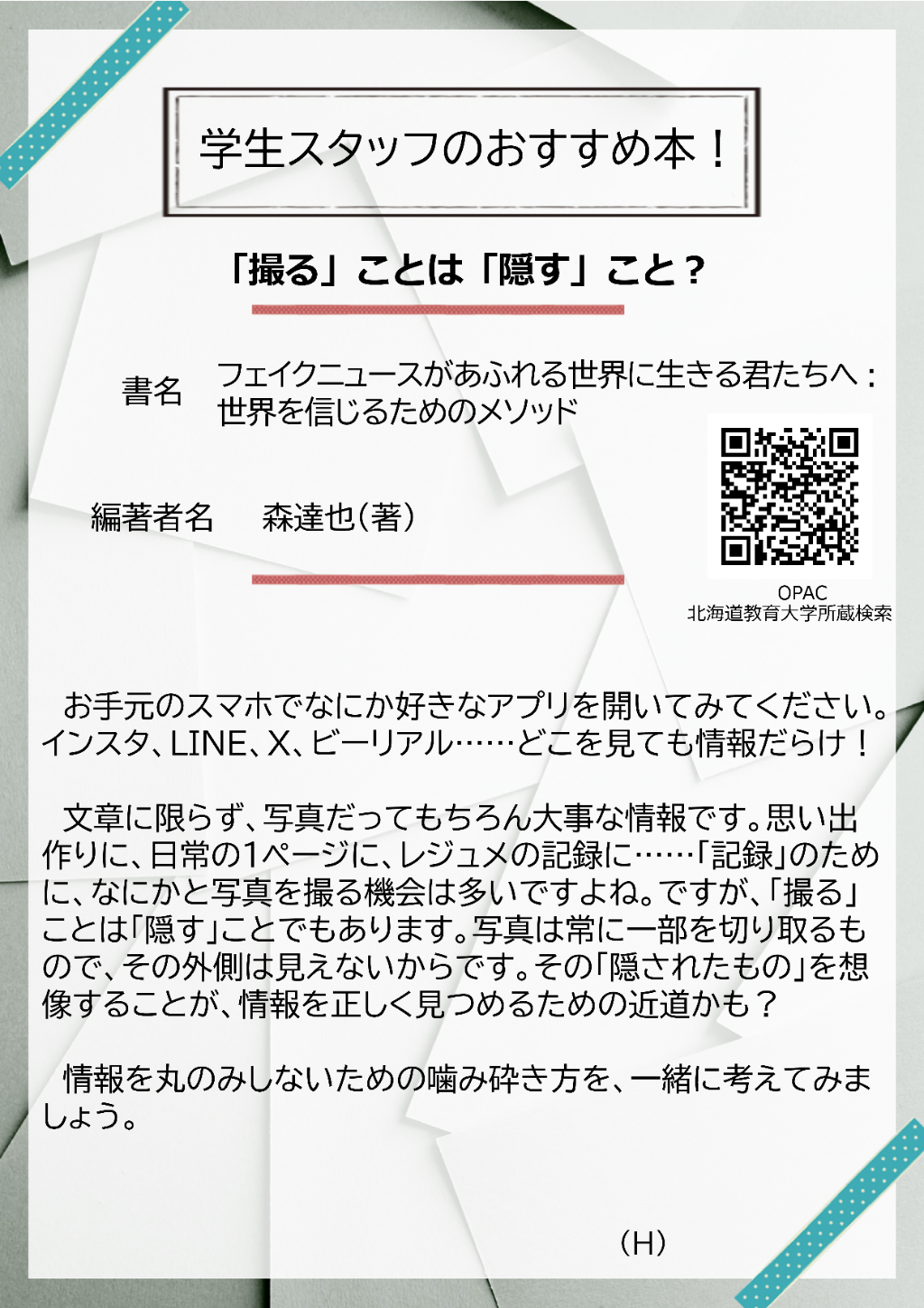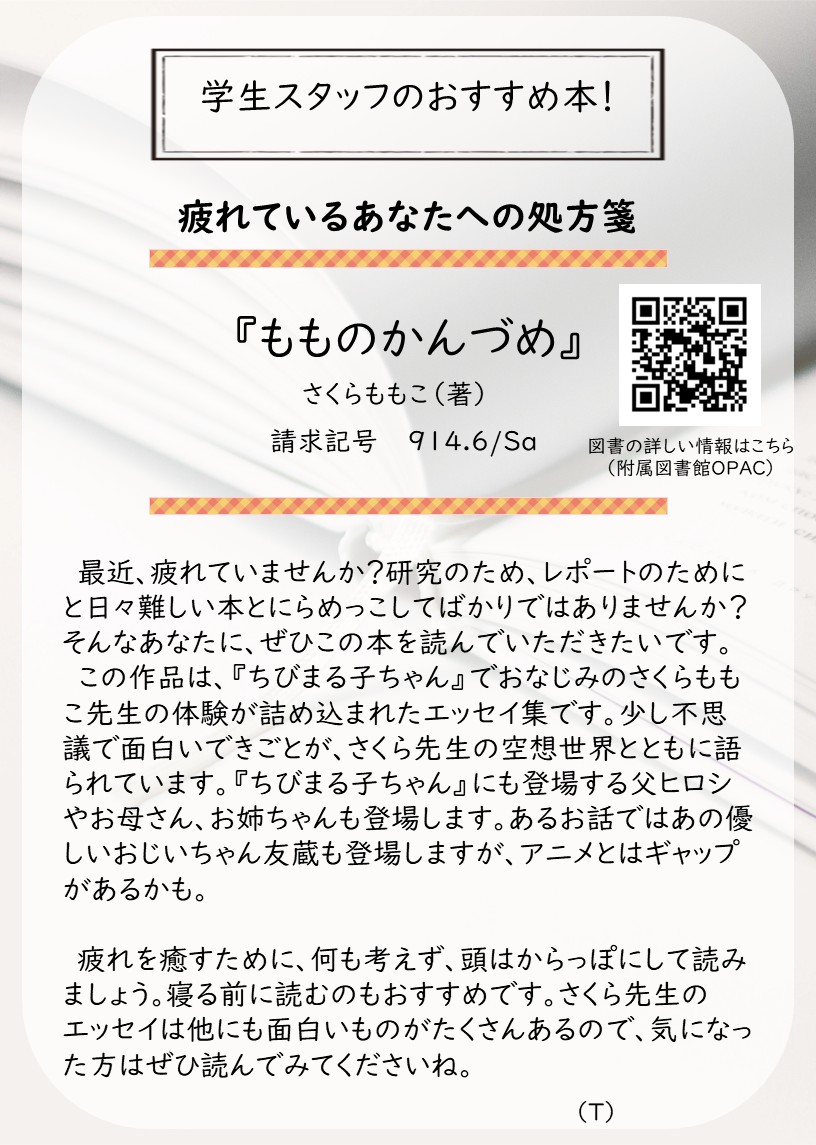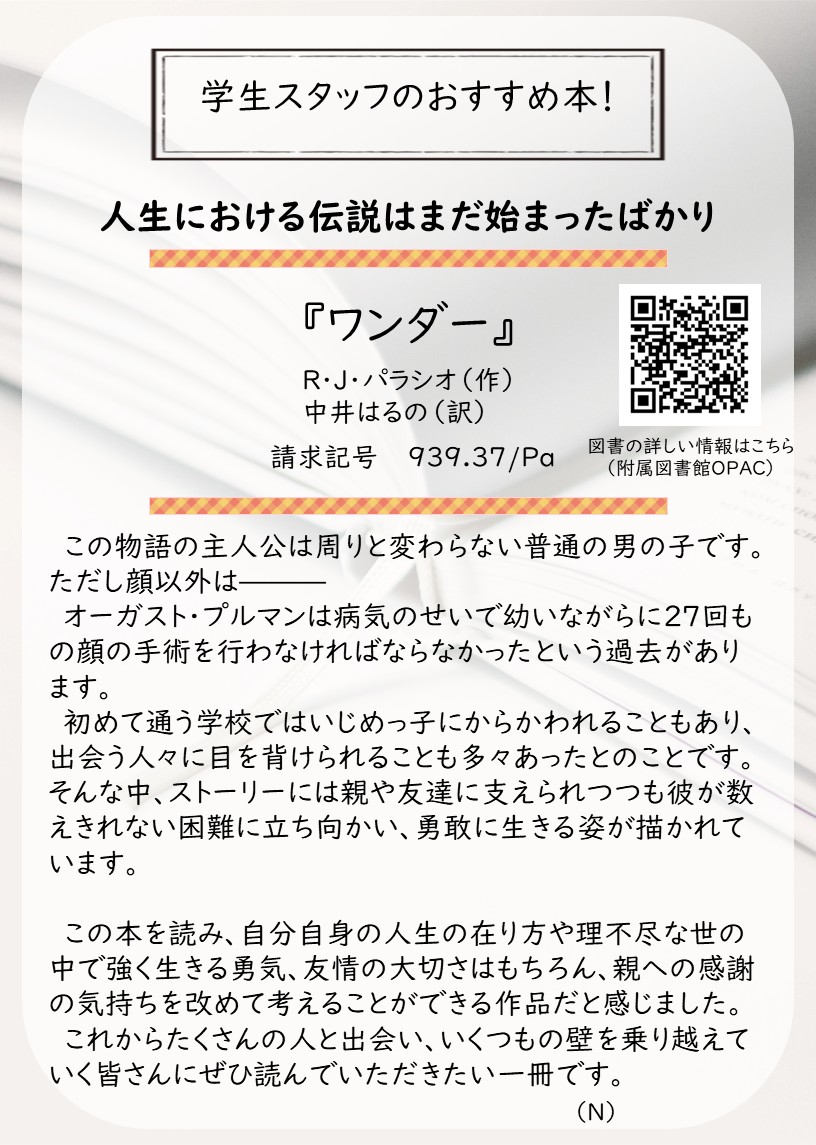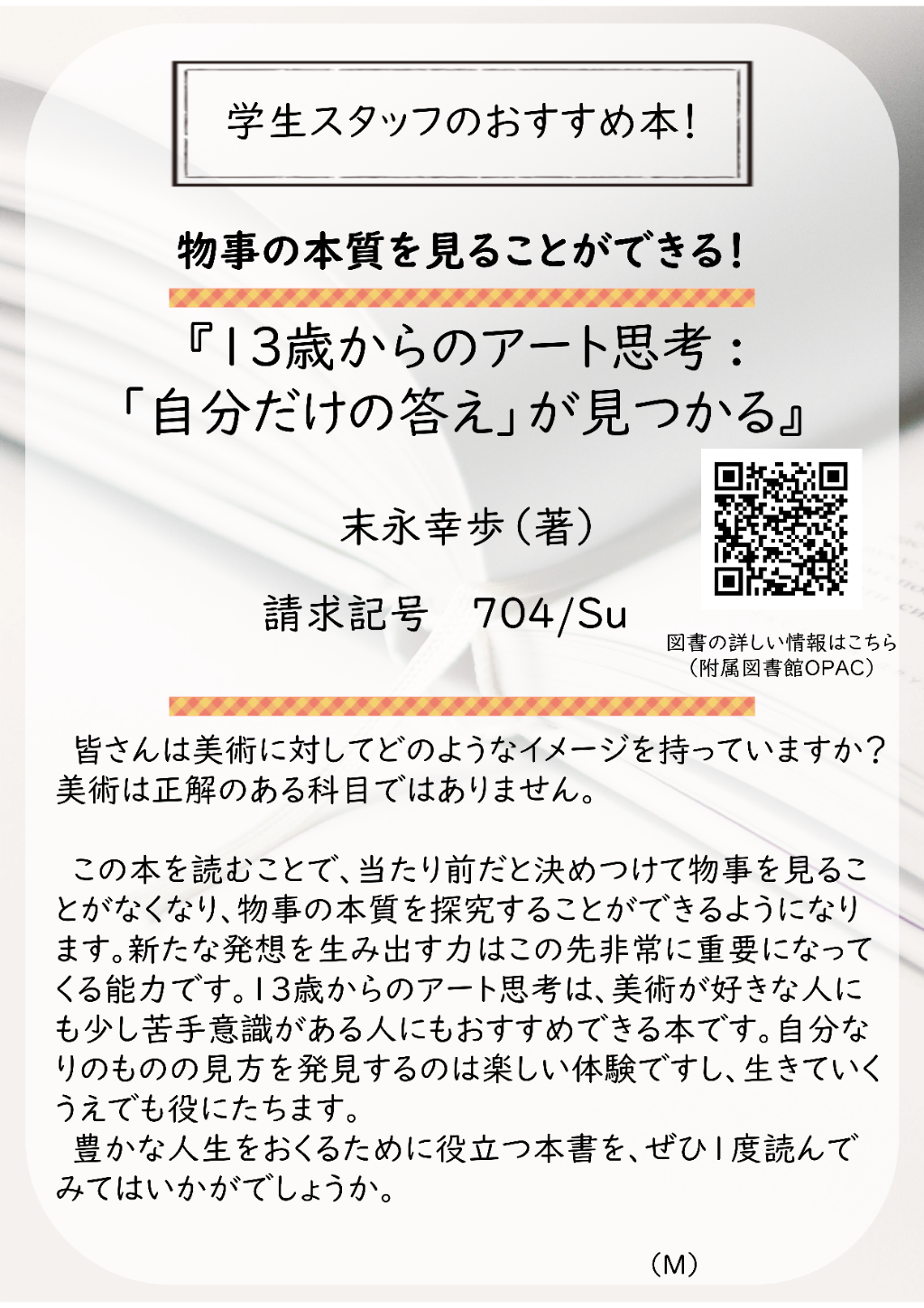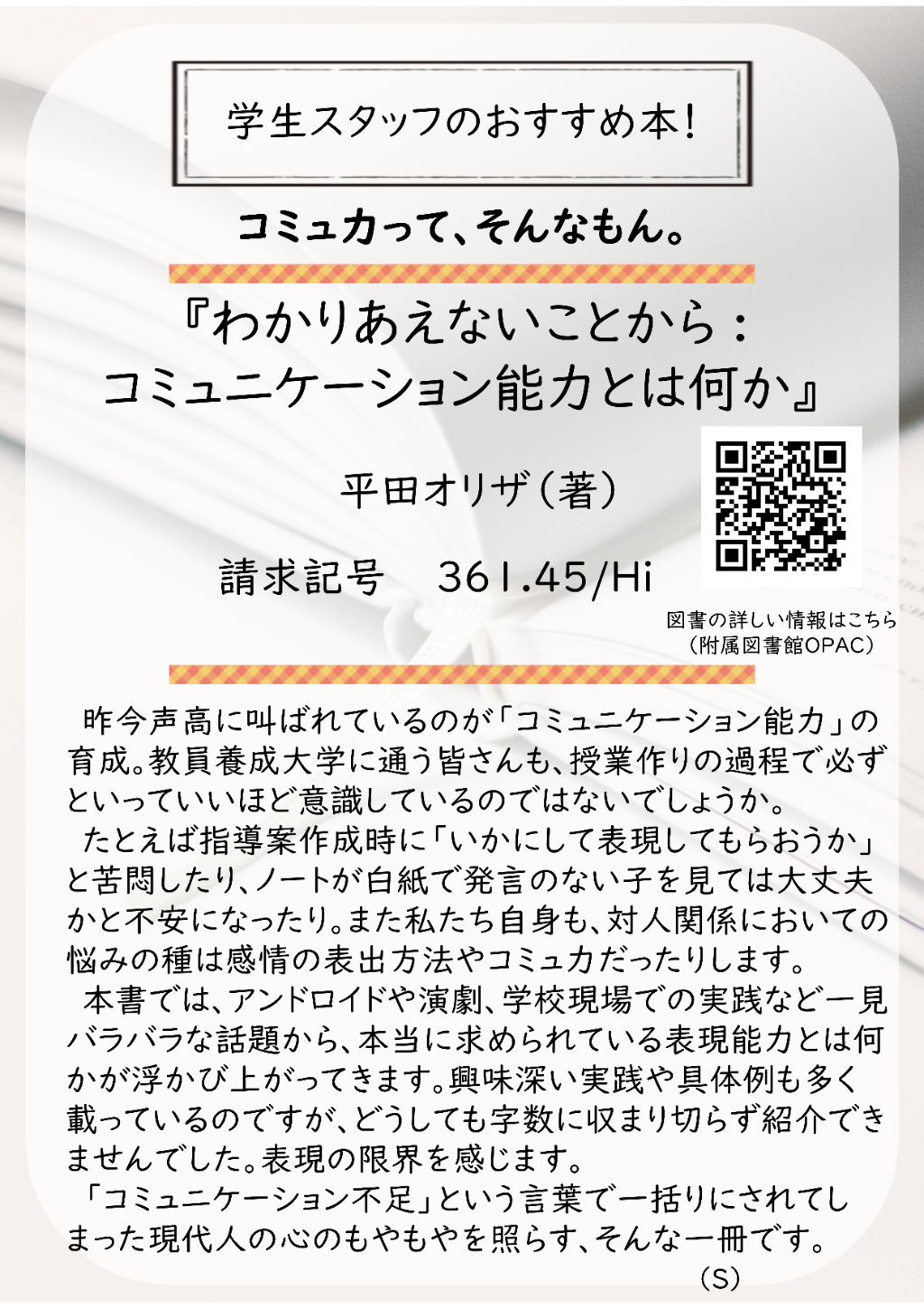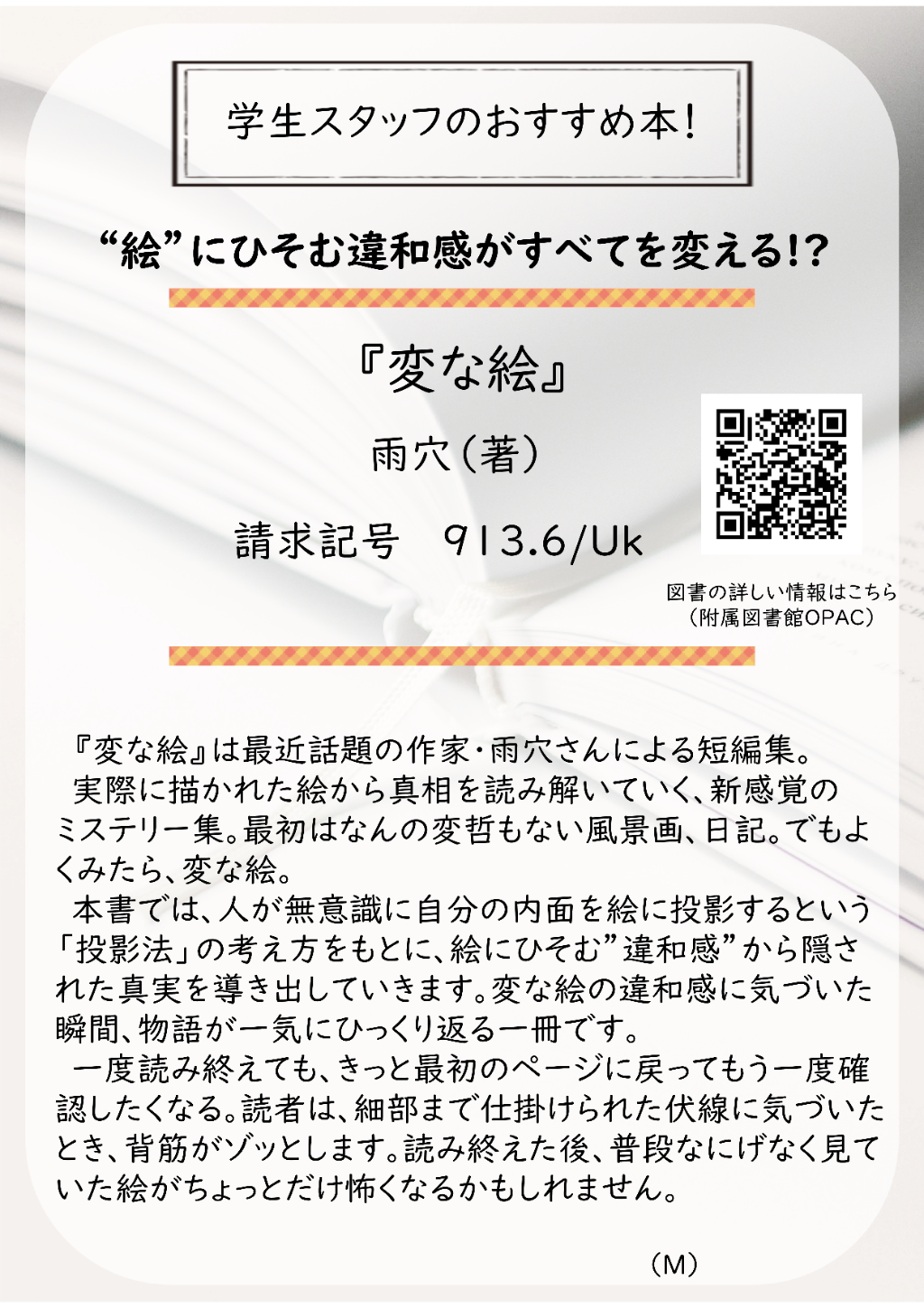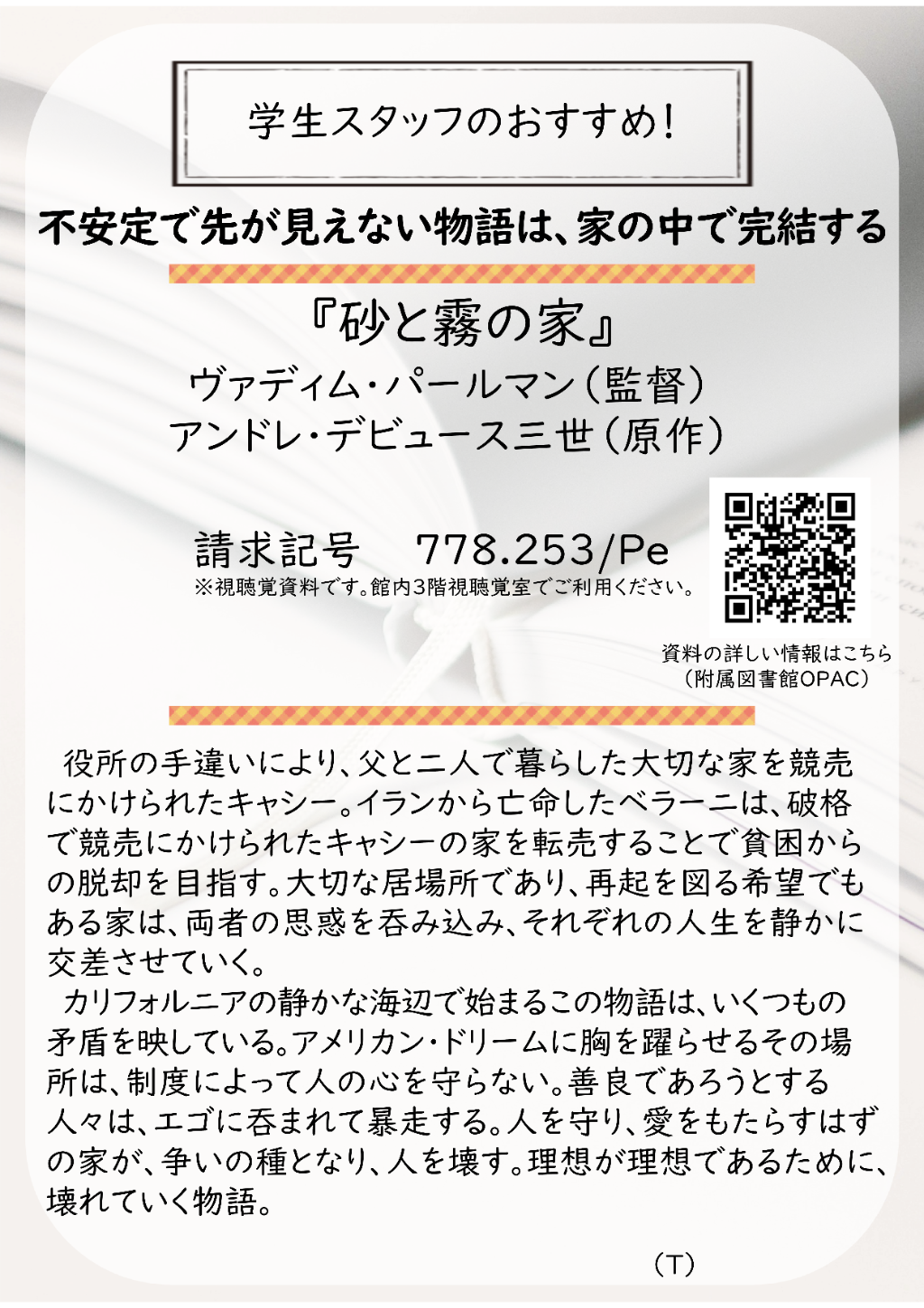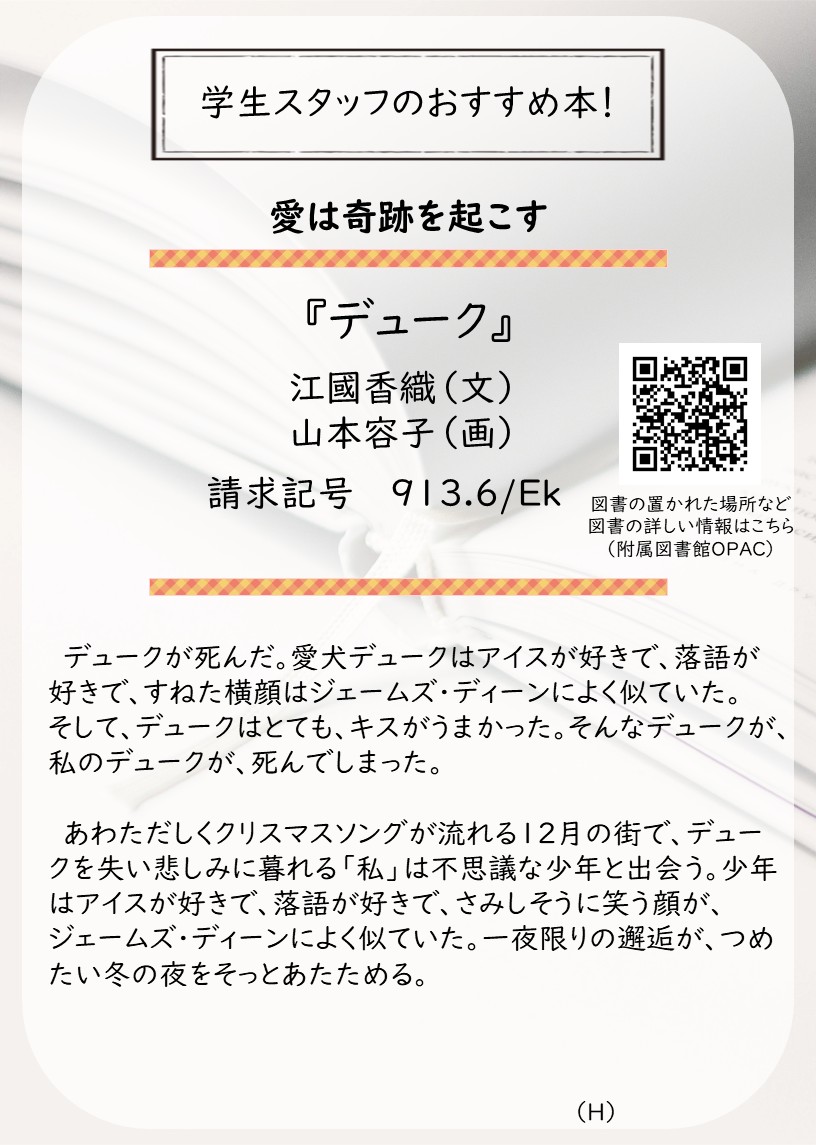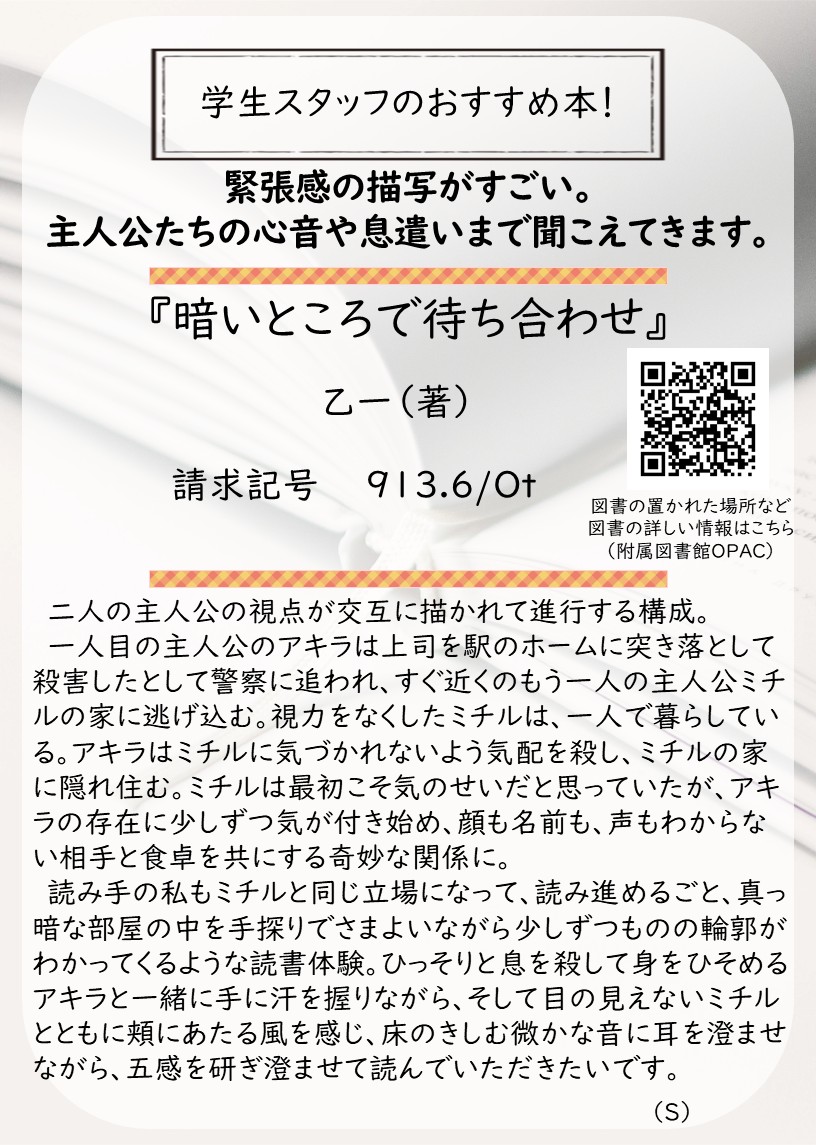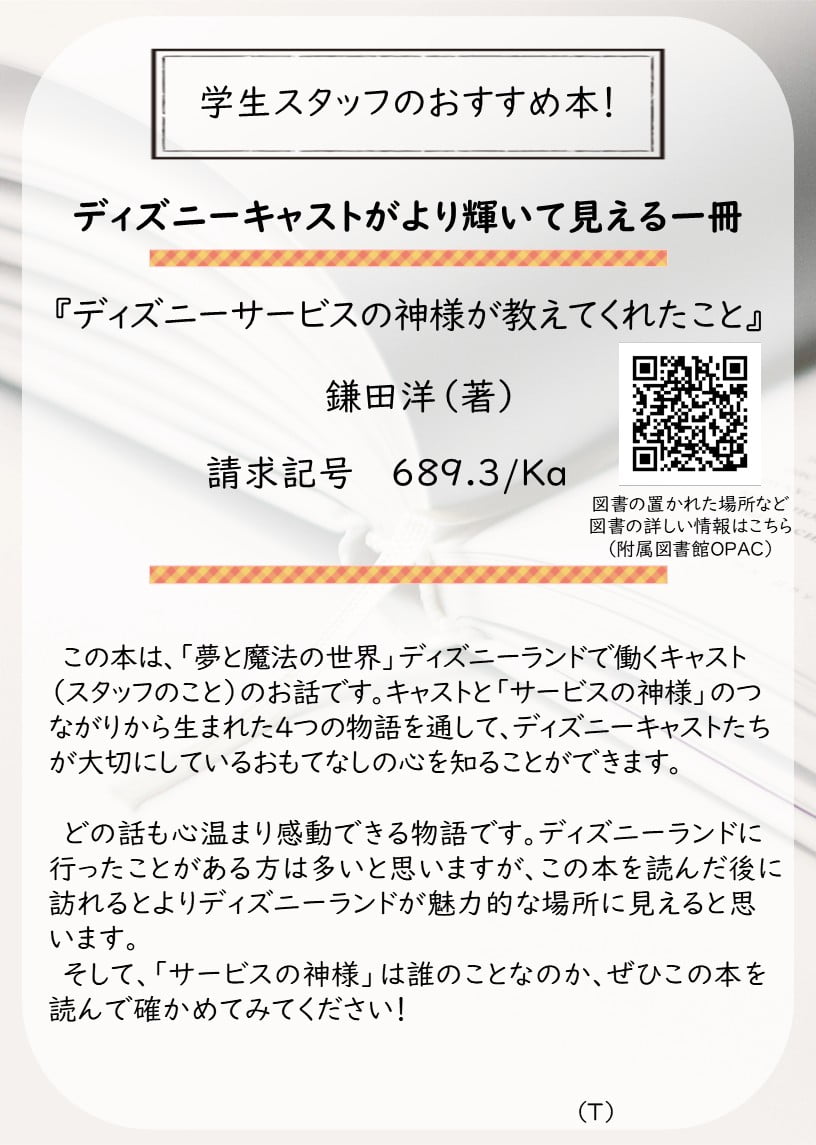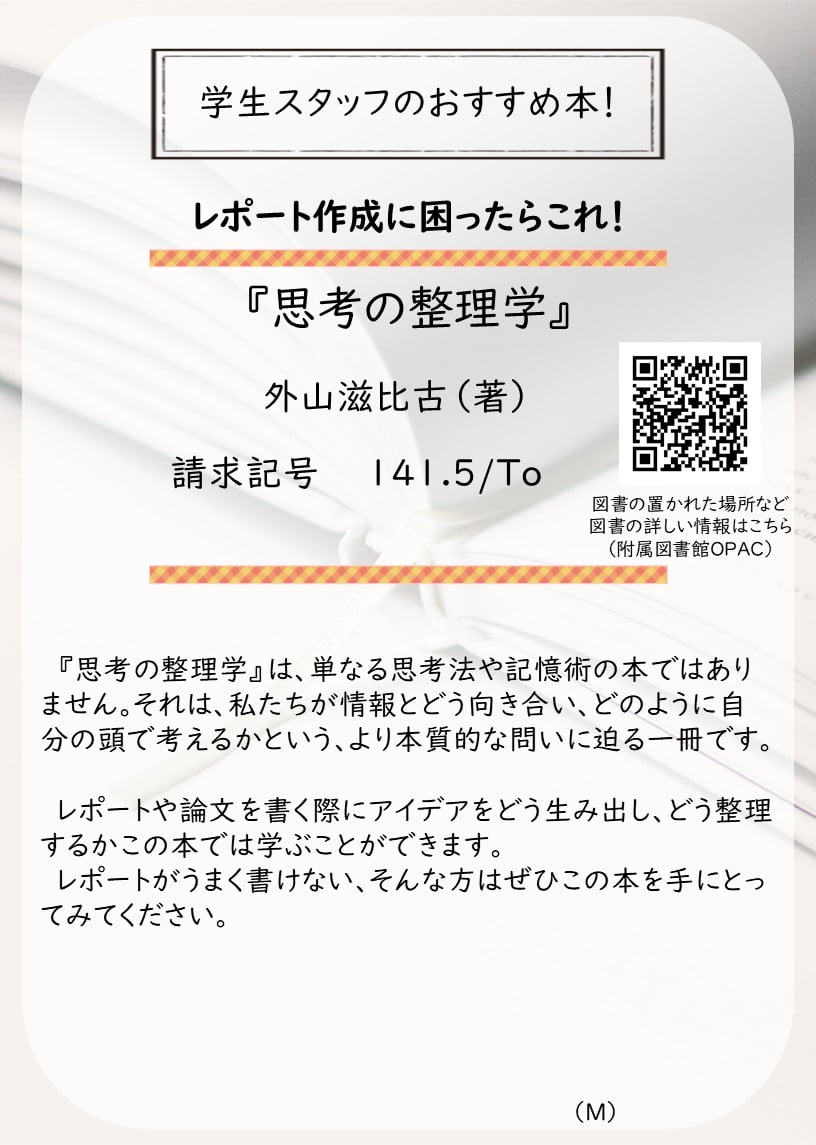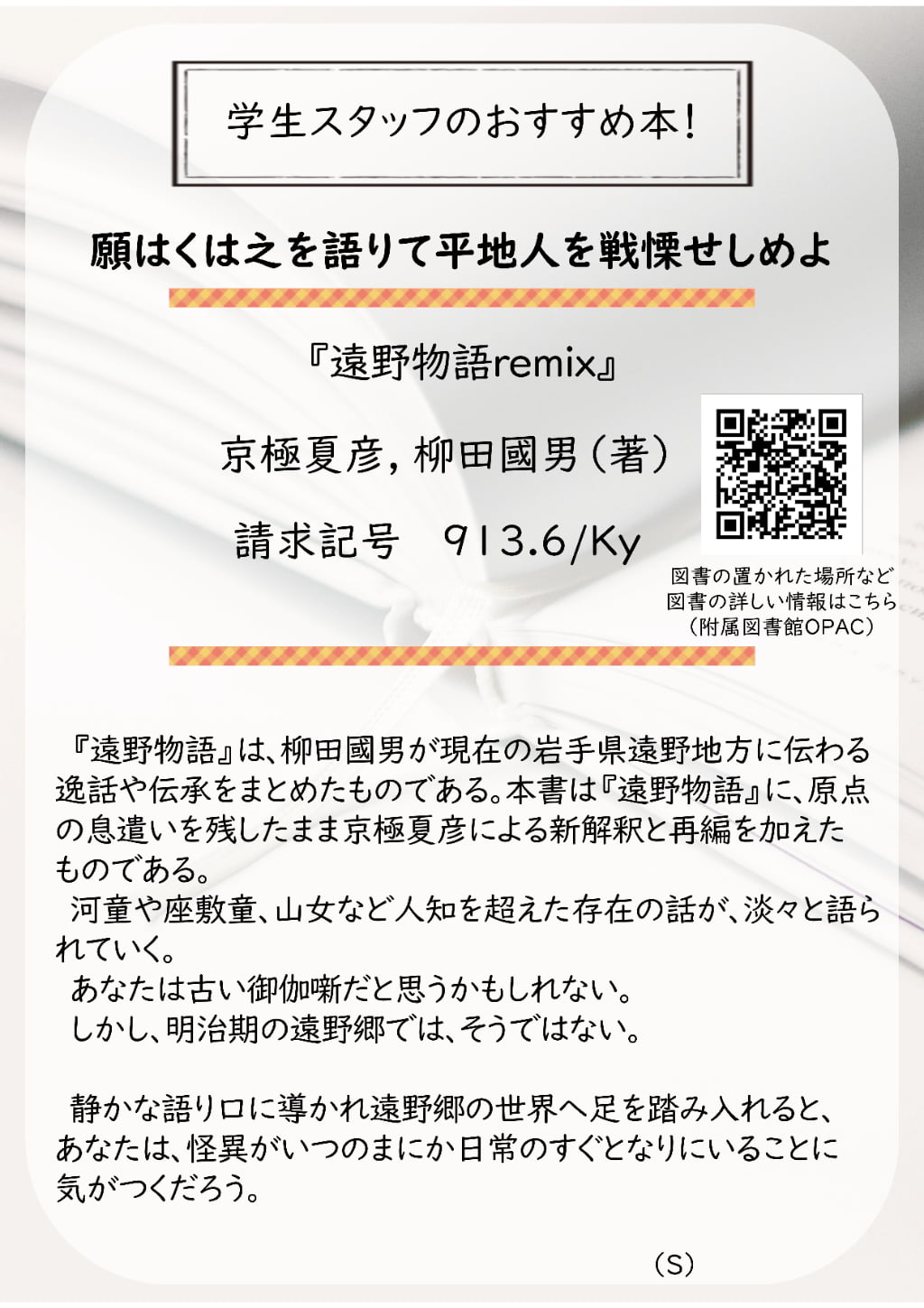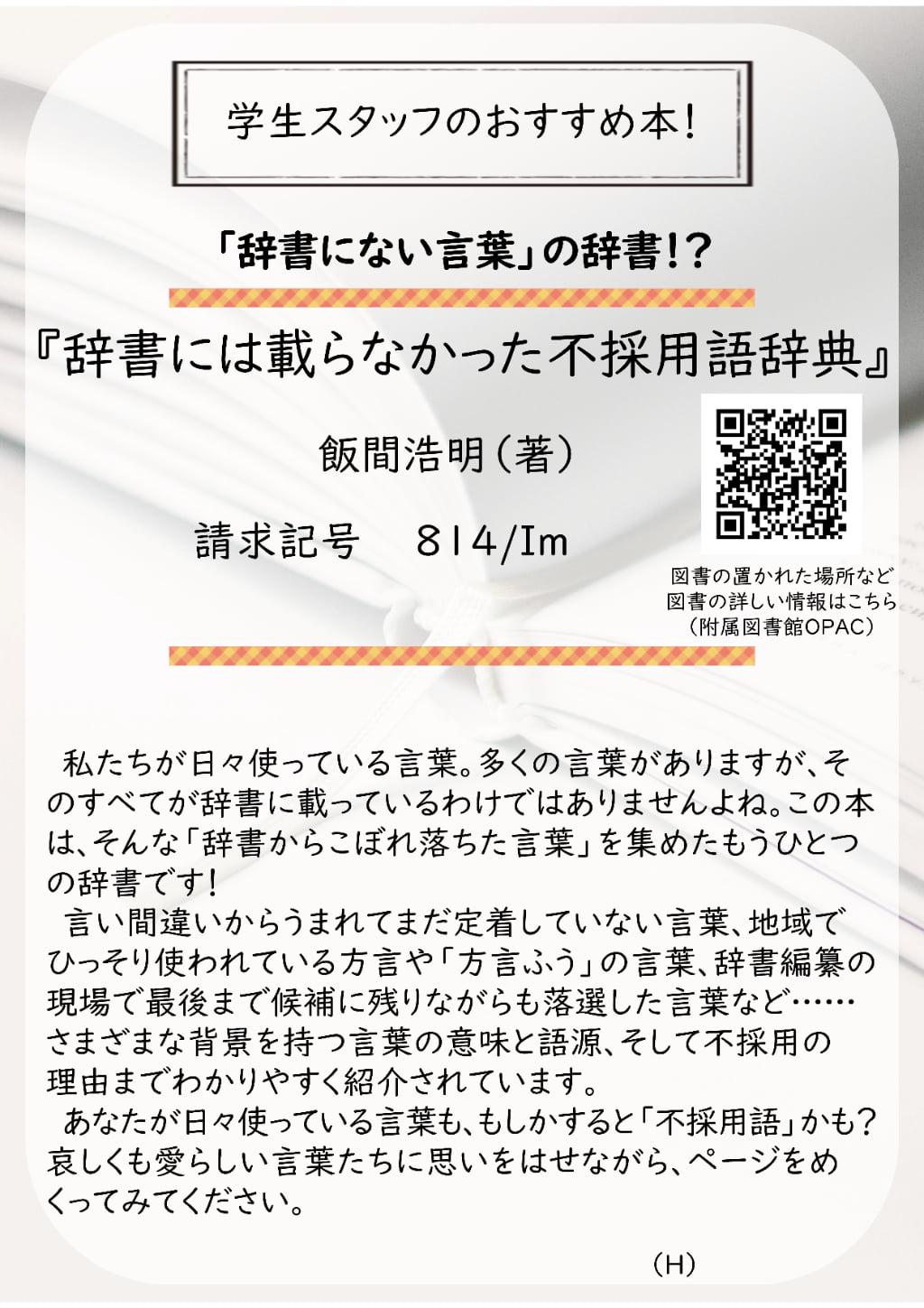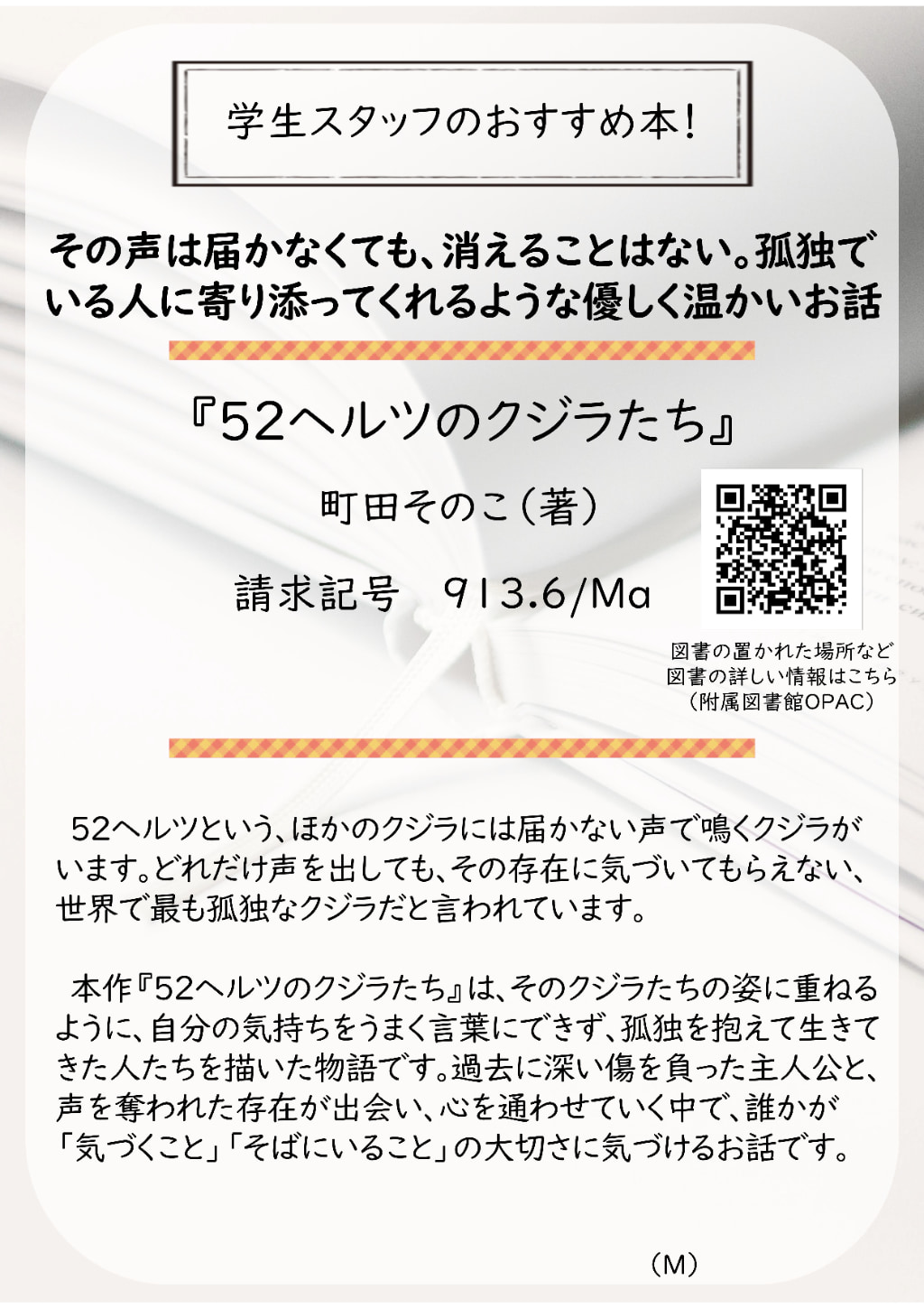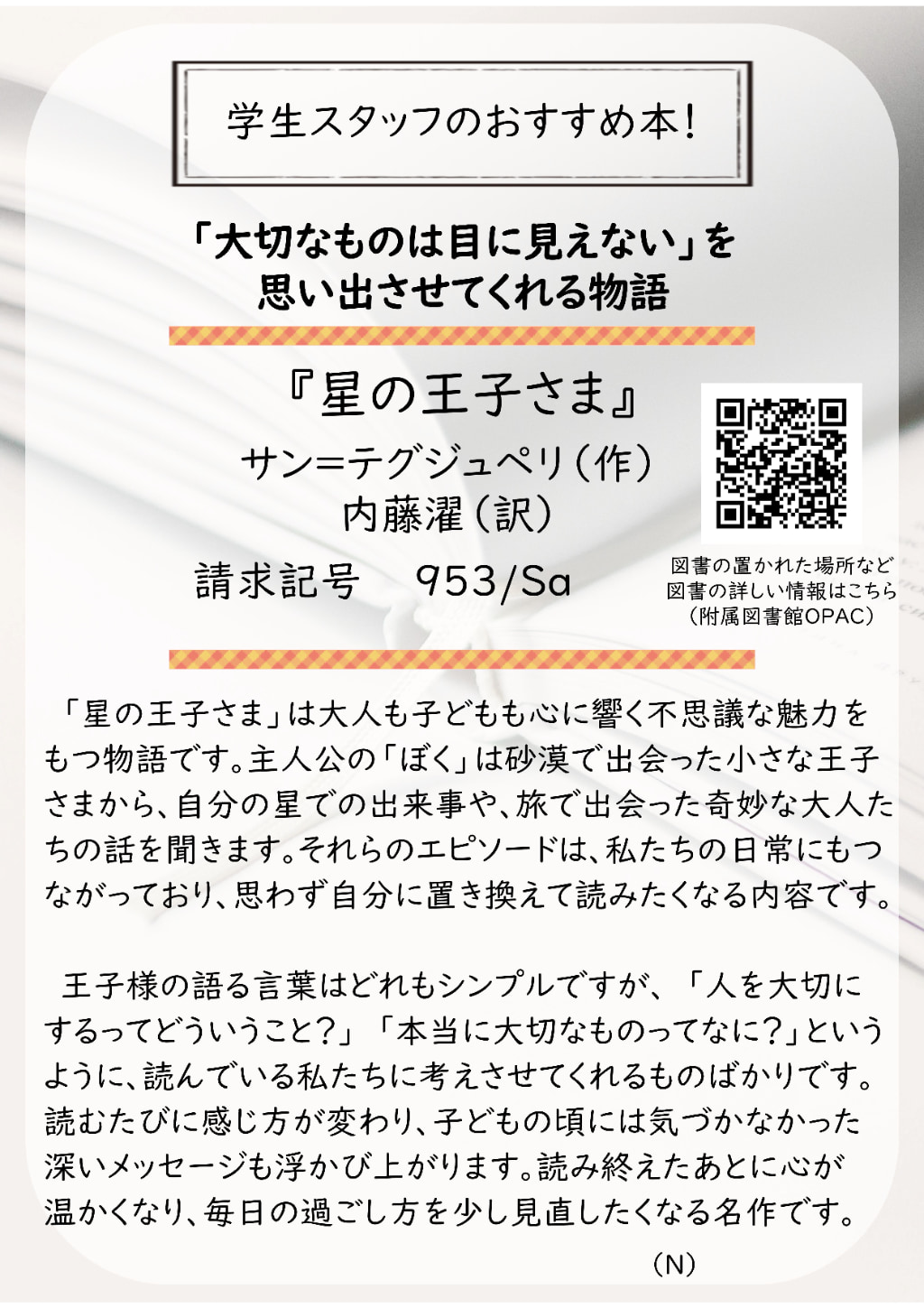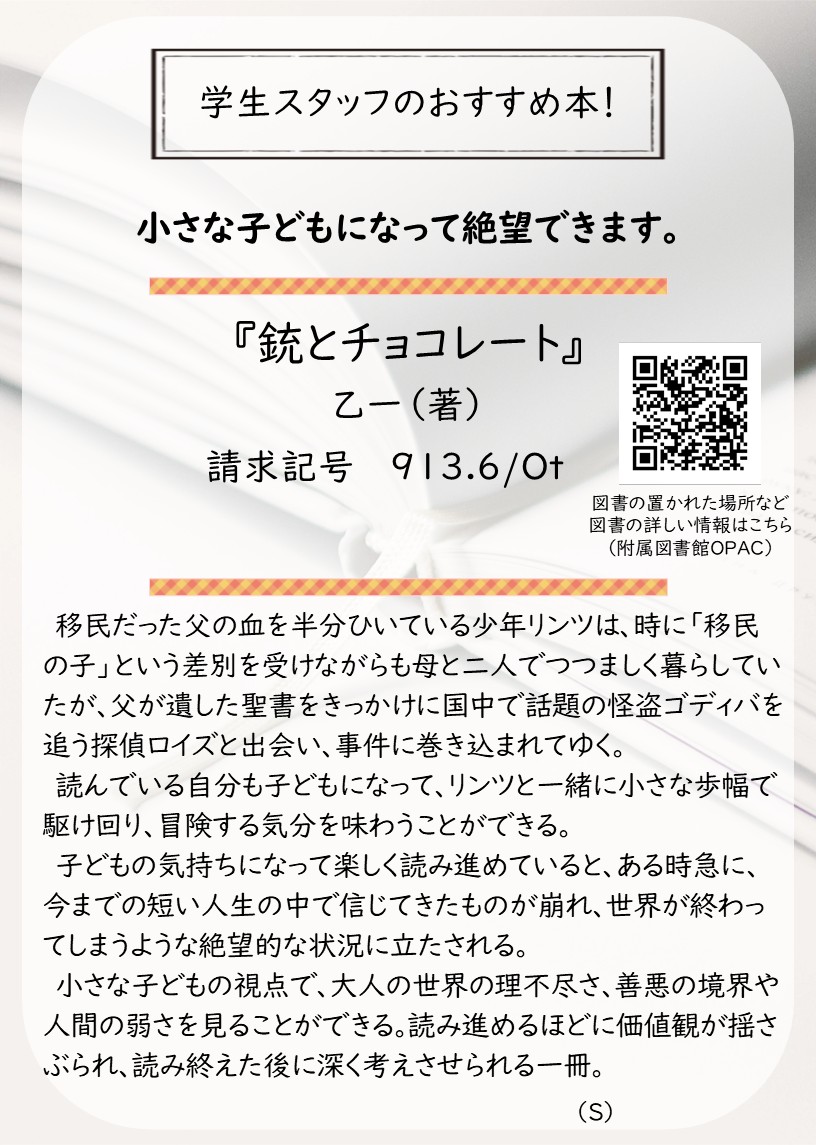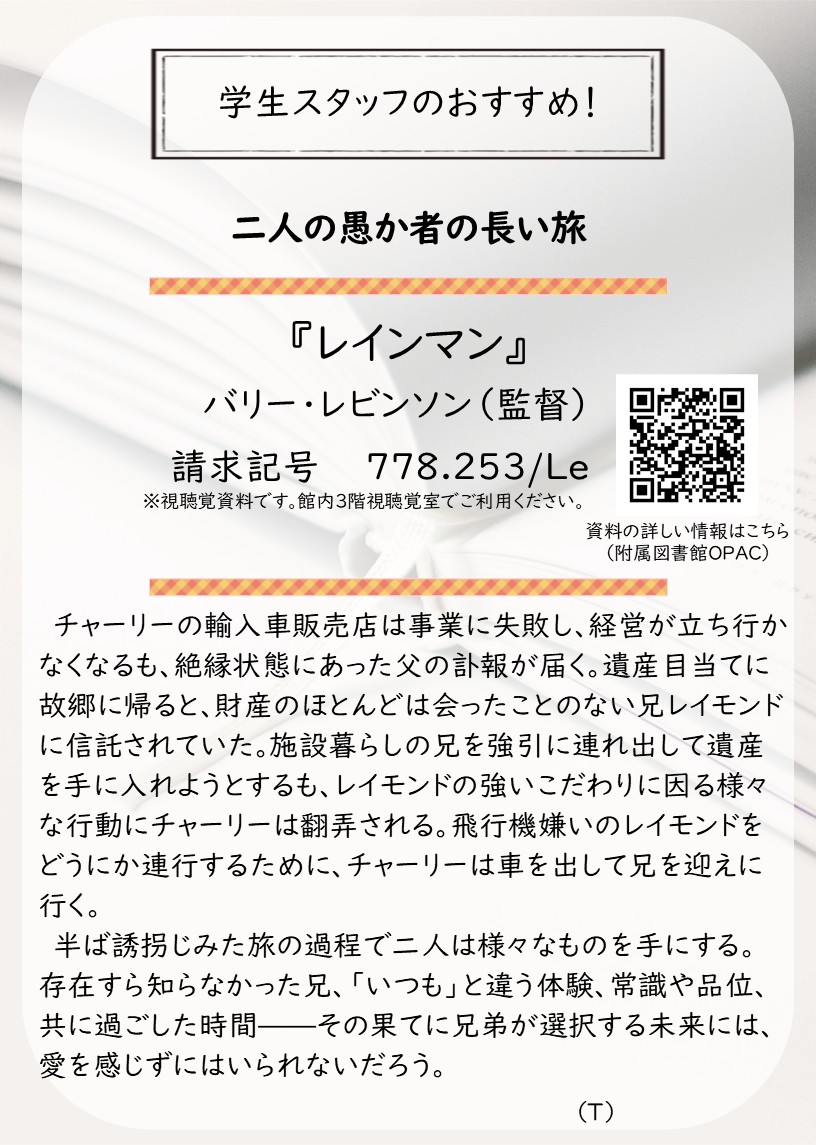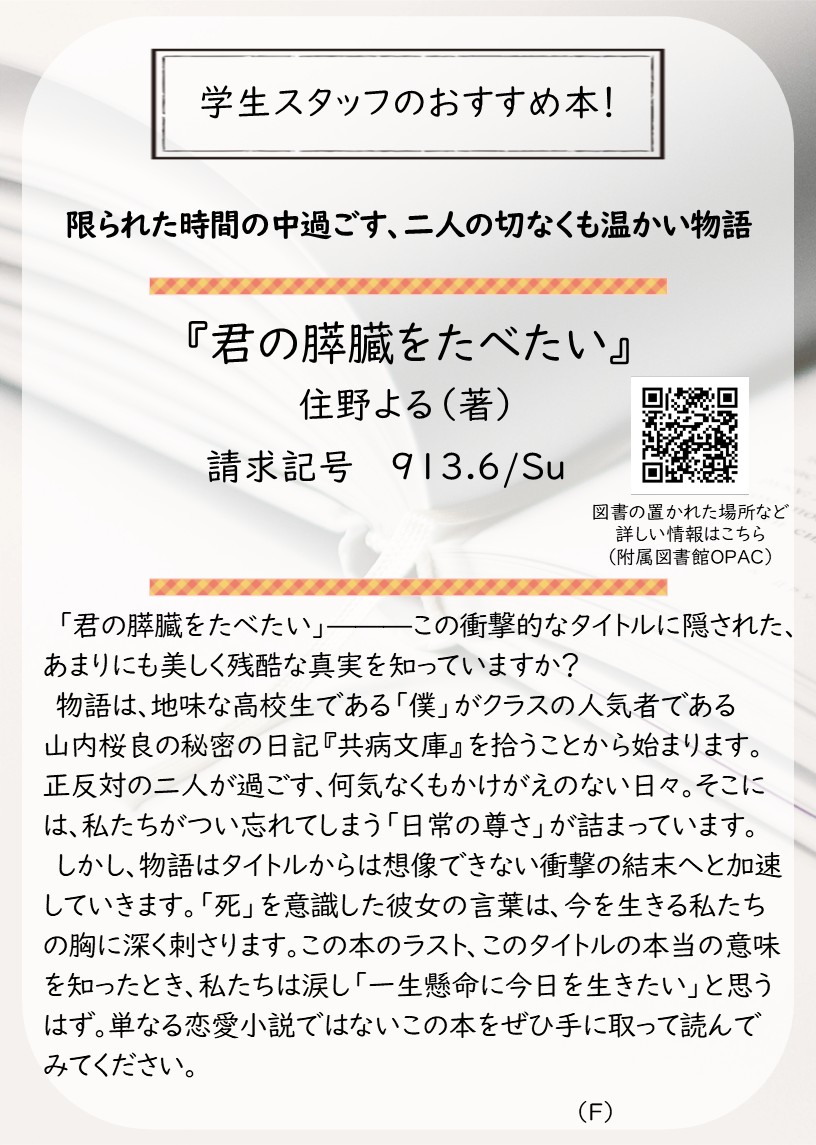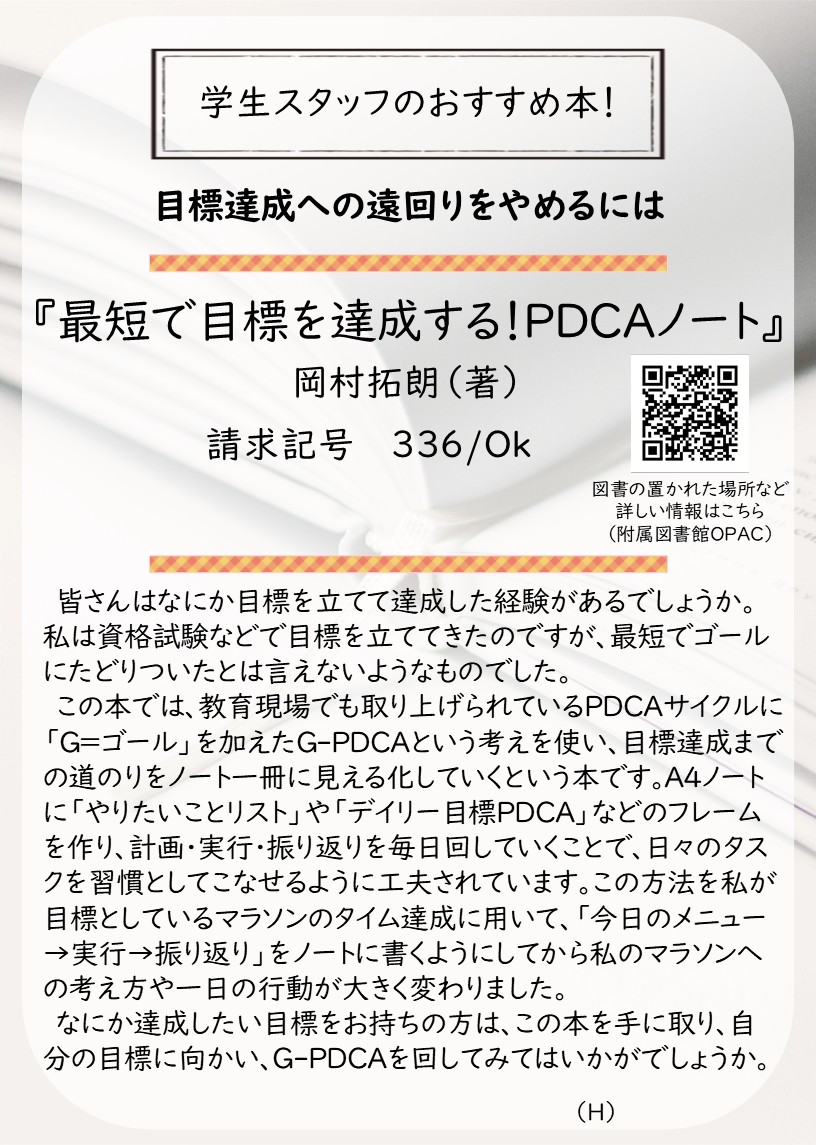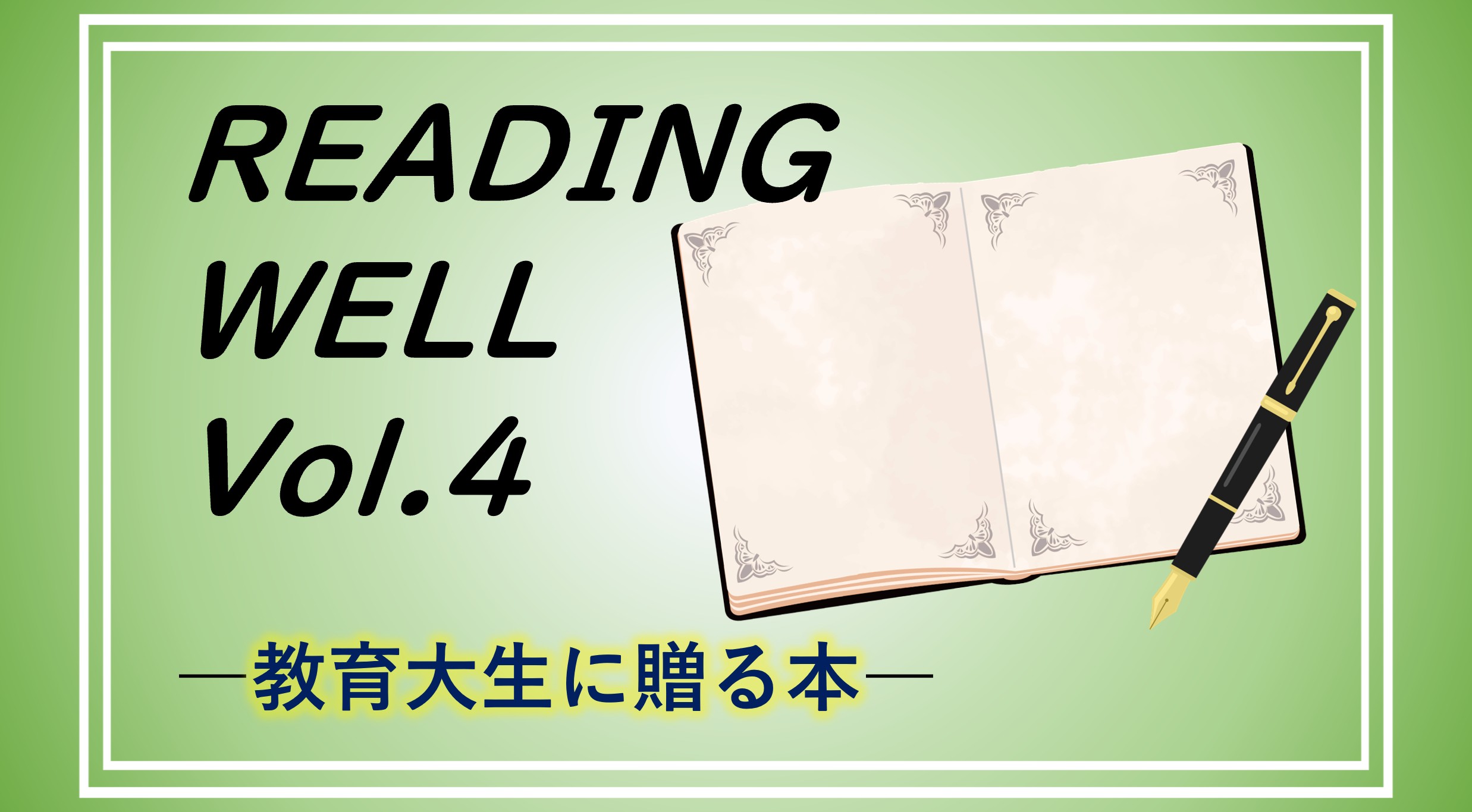札幌館では、学生スタッフが「皆さんに読んでほしい!」と思う、札幌館のおすすめ本を紹介する企画を実施中です。
紹介した本は、このページのほか、札幌館X(旧Twitter)にて公開しています。
どんな本を紹介するか、またどのような紹介文にするかは学生スタッフが自ら考えています。
月に一度、新しい本を紹介していく予定ですので、皆さんお楽しみに!
シーズン1(折りたたまれています。ここをクリック)
| おすすめ本(画像クリックで拡大) | ひとこと | |
|---|---|---|
| 1 |
夢の国は、戦略の国? by S ここをクリック大学1年生の時に初めて訪れたⅮランド(通称:夢の国)。見るものすべてが新鮮で、圧倒されていた私。なぜ夢の国はこんなにも人々を魅力するのか?そんな好奇心に駆られ、この本を手に取った。これは、経営学の視点から夢の国を捉え直した本である。 「ファストパスにはギャンブルの原理が使われている?!」 「夢の国はアルバイトが9割?!」 「あえて3分の1の不満を残す?!」 などなど。この本を読むと、夢の国の舞台裏に触れることが出来る。夢の国は、膨大な努力の上に成り立つ緻密な『戦略的国家』だとさえ感じるかもしれない。しかしだからこそ、夢の国は人の心を動かすのだ。この本は経営だけでない、人生において大切なことを学ぶことが出来る。ぜひあなたも、夢の国の深淵を覗いてみよう。 |
|
| 2 |
「話し方」は「聞き方」が一番大切!? by H ここをクリック「話すとき、どうしても緊張しちゃう……。」 「二人きりのとき、何話せばいいの?」 「もしかして、私の話ってつまらない?」 そんな悩み、皆さん感じたことはありませんか? 日常生活のあらゆる場面において、必要となる「会話」。コミュニケ―ションが大切なのはわかっているけれど、思っているよりも会話って、結構難しい……。常日頃よりそんな不安を抱えていた私が出会ったのが、この本でした。 まず目を引くのは、このタイトル「話し方が9割」。やっぱり話し方が重要だよなあ、そう思いながら読んでいくと、この本の主題がわかってきました。 それはつまり、「話し方」は「聞き方が9割」。聞き方を磨けば、話し方も自然と身についていくというのです。 皆さんもこの本を読んで、不安な会話を楽しいものにしてみませんか?
|
|
| 3 |
ちょっと食べてみたいかも…? by S ここをクリックゲテモノ料理といえば、カエルやワニが思い浮かびます。 私が生まれて初めて食べたゲテモノ料理はノースサファリ札幌の焼いた芋虫でしたが、気持ち的にも味的にも苦い思いをしました…… しかしそんな物とは比にならないくらい「ヤバい」料理が紹介されているのがこの本です。 筆者である高野秀行さんの実体験に基づいて、世界中のゲテモノ料理が書かれています。カエルのジュース、虫を具材にしたピザ、水牛の脊髄炒めなどなど…… 想像するだけで気分が悪くなりそうですが、高野さんの面白エピソードも書かれてあり、サクサク読めます。むしろ、美味しかったと聞いて食べてみたくなっちゃいました。 その地域の文化も垣間見ることができて、タメになる面白い一冊です。
|
|
| 4 |
シュレディンガーの妖怪 by K ここをクリックページ数の多さから「小説界の鈍器」と恐れられた妖怪大好き京極夏彦がこの薄さに収まりました。 しかし侮るなかれ、今日も京極夏彦ワールドは全開。独特な文体や緻密な構成力は隠しきれません。町田尚子さんの絵柄も相まってどこか懐かしいような、不気味なような、あの夏の夜の雰囲気がこの本には閉じ込められています。 今作は絵本作家と小説家がタッグを組んであなたの心臓を止めに来る「怪談えほんシリーズ」。他の作品も是非読んでみてください。近頃の厳しい暑さに打ち勝つためにも読むのも、秋の夜長に読むのも素敵な作品ばかりです。 ところで私がこの本を読んだ後、夜あまり眠れないのですがどうしたらよいでしょうか?
|
|
| 5 |
劇的な出会いなんていらない。 by S ここをクリックこの小説の裏テーマは「出会い」だ。 私たちは人とのかかわりの中で生きている。ありきたりな出会いの中に生きている。だからこそ、心のどこかで「劇的」な出会いを求めている。 「アイネクライネナハトムジーク」は、伊坂幸太郎好きな友人が教えてくれた珠玉の一冊である。異なる主人公による短編が数個収録された本であり、登場人物たちはみな「出会い」に思いを馳せている。そんなそれぞれの短編を読み進めるうちに、読者は不思議な感動を覚えていくだろう。最後の短編は必見である。 モーツァルトの楽曲「アイネクライネナハトムジーク」のように、春の胸の高鳴りを思わせる朗らかな小説だ。 「出会い」とはなにか?劇的な出会いよりも大事なこととは?読んだ後、あなたの心に灯がともる。
|
|
| 6 |
一度は食べてみたい置戸町の給食 by U ここをクリック北海道置戸町には「日本一の給食」と謳われるほどおいしいと評判な給食があります。 この町に住む佐々木十美さんは栄養士として、この町の子どものお腹を満たし健康を支えています。子どもたちに食材の「本物の味」を知ってもらうという佐々木さんの思いは、調味料や化学調味料を極力減らすということや、地元の安全な食品を使うということに繋がりました。 また子どものためにカレーを甘くしたり魚の骨を一本一本丁寧に取るということはせずに大人になっても通用する食習慣を持ってもらおうとした考えられた給食を提供しました。 そして地元の自然の温かみを知ってもらうために使用した「オケクラフト」という食器は、ものを大切に扱う気持ちを育て地元産業の発展にも貢献しています。 佐々木さんの人生や「食」に対する思いを辿ることで、どのように日本一の給食が誕生したかをこの一冊で知ることができます。
|
|
| 7 |
今よりもちょっと「しあわせ」になれる言葉 by Y ここをクリック儒教・道教・仏教の3つの思想を組み合わせて書かれた『菜根譚』。 原書は難しい言葉で書かれているけど、その内容は皆さんも知っている「くまのプーさん」が大事にしている簡単なことばかり。 自然を愛することや、友達を大切にすること、謙虚に生きること、時には全てを忘れてゆったりと過ごすこと― 当たり前のはずなのに、いつの間にか忘れてしまっていることも多いのではないでしょうか? 何かに悩んでいる時や落ち込んでいる時など、辛い気持ちになった時にこの本に書かれている言葉を思い出してください。 きっと「プーさん」が貴方に寄り添って支えてくれます。
|
|
| 8 |
『他人の靴を履く』からわかること by S ここをクリックこの本は、死んだはずの主人公「ぼく」が、自殺をはかった中学生「小林真」の体を借りて人生に再挑戦する物語です。 小林真としての生活をはじめ、周りの人々は誰もが良い人で幸せに満ちているものであるように感じていた主人公でしたが、次第に小林真を取り巻く環境は複雑であることに気づいていきます。 一見ファンタジー要素が強いように感じられますが、いじめや自殺、悪徳商法、不倫、援助交際など、現代社会のシビアな問題が散りばめられています。リアルで暗い描写も、著者森絵都のユーモア溢れる文章と設定で、どんどん惹き込まれていきます。 人は死んだらどうなるのか、他の人生を体験してみたい、といった誰もが一度は考えたことのあるだろうことを通じて題名の「カラフル」の意味を考えられる一冊になっています。
|
|
| 9 |
『金子みすゞ』の世界を味わう by H ここをクリック「みんなちがって、みんないい。」どんな方でも一度は耳にしたことのあるフレーズなのではないでしょうか。 この本は、金子みすゞの童謡43篇が収められた詩集です。 絵本のような薄さながら、誰もが知っているようなものから意外と知られていないものまで幅広い作品が収録されており、どの詩からも不思議とあたたかさを感じることができます。ひとつひとつが短いこともあり、毎日忙しくて本を読む時間がない方でも気軽に手に取ることのできる一冊です。 名前は知っているけれど、ちゃんと読んだことはないかも……という皆さん。この本から少しだけ、金子みすゞの世界を覗いてみませんか?
|
|
| 10 |
少しずつ、少しずつ沈んでいく by H ここをクリック太宰治、と聞いて、皆さんが思い浮かべるのはどんな小説でしょうか?「人間失格」?「走れメロス」?他にも様々な小説を執筆していますが、なかでもお勧めしたいのは、この「斜陽」です。 朝、食堂でスウプを一さじ、すっと吸ってお母さまが、 「あ」 と幽かな叫び声をお挙げになった。 こんな描写から始まり、ある貴族の没落を描くこの小説は、どうあがいても沈んでいく夕日のようであり、儚く衰える「美」と沈む間際の最後の強い輝きが感じられます。 ふと、寂しくなってしまったときに。何か嫌になってしまった夜に。ぜひ、手に取ってみてください。少しずつ、でも確実に「終わっていく」姿は、きっとあなたの心に寄り添ってくれるはずです。
|
|
| 11 |
本にまつわる○○ by S ここをクリック皆さんは、「こんな本があったらいいなあ」「こんな道具があったら読書がもっと楽しくなるのに」と思うことはありますか? そんな読書家の願いを叶えてくれるのがこの「あるかしら書店」です。この書店には、『カリスマ書店員養成所の1日』、『本が四角い理由』など、現実にありそうでない内容の本や本にまつわる道具が置かれています。 私が特に気になったのは『本のつつみ方』でした。皆さんも是非この本を読んでお気に入りの一冊を見つけてみてください。 また、面白いだけでなく、本とは何か、読書とは何かを再確認することができます。今、本から離れてしまっている人にも、きっと読書の素晴らしさを思い出させてくれるはずです。
|
|
| 12 |
弱くても僕は僕なんだから by S ここをクリック人間は、「どうして?」と考えることができます。 それ故に、身の回りに起こる悲しいこともすべて「どうして?」と考えてしまいがちです。 ですが、その「どうして?」という気持ちが時に自分自身を傷つけてはいませんか? この本は四コマ漫画の児童書で、イラストも和やかです。 ですがそのひとつひとつに深いメッセージ性があり、生きることに大切な考えに気づかされます。 ぜひ、自分なりの解釈を広げてみてください。 かけがえのない自分を愛せるように。 心をそっと解きほぐす、あなたに向けた本です。
|
|
| 13 |
なぜ「いじめ」はなくならないのか by Y ここをクリック「いじめは絶対にしてはいけない―。」 誰もが小さい頃から聞いてきた言葉。しかし実際には、一部の痛ましい事件がニュースに取り上げられているだけで、程度の差こそあれどどこでもいじめは発生している。いじめには予防や早期発見をはじめ適切な対処が必要であることは言うまでもないが、そもそもなぜいじめが発生するのか?そこには社会性動物の宿痾というべきものが絡んでいる。 本書では、ただ綺麗事を並べていじめを真っ向から否定するのではなく、脳科学の観点から分析し、その対処方法について考察されている。また、気づかぬ内にいじめを発生させかねない行動についても学ぶことができる。 教員志望者に限らず全ての人に手に取ってみてほしい一冊。
|
|
| 14 |
恋愛未満小説 by K ここをクリック表題作の「百瀬、こっちを向いて。」を始め、「なみうちぎわ」、「キャベツ畑に彼の声」、「小梅が通る」の4編の短編で構成されている小説です。 いわゆるボーイミーツガールのお話です。しかし、登場人物の多くが高校生ということもあり、若さゆえの葛藤や人付き合いの拙さが二人の関係性をより複雑にしていきます。その分、各話のラストを見ると何とも言えない気持ちになります。 また作者の中田永一さんは、ミステリー作家である乙一さんの別名義であるため、作品の中に小さなミステリーが潜んでいます。その恋愛?小説としての特殊さも面白さの一つです。 そんな”恋愛の持つ切なさすべてが込められた”みずみずしい小説を是非皆さん一度は手に取って見て下さい。
|
|
| 15 |
対人関係は「呼び方」で決まる by U ここをクリック自分の呼ばれ方、気になることはありませんか? あだ名で呼んでくる人や「~さん」と呼んでくる人、呼び捨てで呼んでくる人。この「呼び方」は無意識にかかわらず相手との距離をはかっていることがわかります。 『「あなた・きみ」よびは嫌われる?』『あだ名呼びは親近感三倍増!』『上司に好かれるためには「肩書き」で呼んではいけない』 この本では「呼び方」が人の心理にどのように作用するかを明らかにしながら、人間関係をよりよくするための「呼び方」を考えていきます。家庭、学校、友人関係、恋愛、アルバイト先、職場などなど様々なシーンで役に立つ人間関係攻略メソッドがこの一冊に集約されています。人との関係を更によくしたいあなたに向けた一冊です。
|
|
| 16 |
やさしいおいしさを味わえる by S ここをクリック都会の片隅にある商店街を入った路地裏に、深夜にだけひっそりと営業しているカフェがあります。それが「マカン・マラン」です。マカン・マランとはインドネシア語で「夜食」という意味。 店主は、元エリートサラリーマンにして、今はド派手なドラァグクイーンのシャールさん。ここには様々な悩みを抱える人が集まって来ます。店主のシャールさんは、自分と同じように傷ついた人々を元気づけるためにまかない料理を出し、自分の悩みとどう生きていくのか、現代社会における問題をそれぞれの視点から見ることができます。 マカン・マランで繰り広げられるあたたかくてやさしくておいしい物語を味わってみてはいかがでしょうか。
|
|
| 17 |
ストレス社会に生きるすべての人へ by Y ここをクリックストレス社会と言われる現代では、誰もが心の病気にかかってしまうリスクがある。特に、うつ病という言葉が広く認知されるようになって久しい。しかし、その前段階である「適応障害」についてはあまり知られておらず、ただの怠けだと勘違いしてしまう人も少なくない。だが、適応障害の状態にある人への対処を誤ると悪化し、最悪自殺や犯罪に及んでしまう恐れがある。 ・最近、環境や人間関係に変化があった ・些細な事や人の目が気になるタイプ ・プライドが高い、完璧主義な人 こんな人は適応障害に陥ってしまいやすい。自分自身や身の回りの人が当てはまると思った時、早期発見と適切な対処ができるようぜひ本書を手に取ってほしい。
|
|
シーズン2(折りたたまれています。ここをクリック)
| おすすめ本(画像クリックで拡大) | ひとこと | |
|---|---|---|
| 1 |
「キケン」の危険な奴ら by K ここをクリック一般的な工科大学のサークル「機械制御研究部」、通称「キケン」に所属するイカれたメンバーを紹介するぜ! 兵器を作り続け、家族に自宅から追い出され物置に住まわされた部長”上野”。空手は黒帯、鉄パイプを持った集団を殴り倒した副部長”大神"。以上だ!後は読みながら覚えてくれ。 とにかくキケンな奴らが犯罪スレスレのサークル活動や命がけの学祭、何でもアリのロボット大会などで一丸となって大暴れ!!こんな馬鹿な男子大学生っているの?!って思いながら読むと最高に面白い作品です。 そんなむさくるしくも愛くるしい「キケン」の皆さんをどうぞよろしくお願いします! |
|
| 2 |
「言葉」から自分を変える by H ここをクリック人間関係がなかなかうまくいかない。なぜかいつも友達を怒らせてしまう。後輩と話がかみあわない。こんな風に、コミュニケーションに悩んだことはありませんか? もしかすると、それは「言葉」が原因かもしれません。 日常的な挨拶から、ちょっとした返事、感謝や謝罪……私たちのコミュニケーションには、言葉が必要不可欠です。無意識的に使っている言葉を少し見直すだけで、さらに良い人間関係が築けるようになるかもしれません。この「言いかえ図鑑」で、言葉から自分を変えてみませんか?
|
|
| 3 |
ドーナツの穴の概念が覆る! by S ここをクリック皆さんは、「ドーナツの穴を残して食べてください」と言われたらどのように食べますか? この本では、大阪大学の様々な専門分野の教授たちが「ドーナツの穴を残す」という、正直不可能だと考えてしまう問いを真剣に考えています。学問の醍醐味の一つであろう「常識を疑い、当たり前だと考えてきたことを覆すこと」がこの問いを通して実感できるような一冊となっています。 そもそもドーナツの穴をどう捉えるのかという部分の趣向を凝らしたり、実験をしてみたりしながらドーナツの穴を残そうとする姿が面白く、かつさすが大学教授!と思えるような内容が描かれており、最後には問いに対する不可能だという常識が少し覆るかもしれません。 不可能を可能にする教授たちの熱き戦いがここにあります。
|
|
| 4 |
衝撃的にぶっ壊せ‼ by T ここをクリック例えば運動会。同じチームの仲間と互いに大きな声や拍手で応援し合いました。 例えば部活動の大会。大会出場選手に壮行会を開き、激励の言葉をかけて送り出しました。 例えば大学受験。家族や先生、友人たちが私たちの背中を押してくれました。 私たちは特別な行事がある時、いつも応援し合い、互いに勇気と希望を与えてきました。応援した者は次に別の人を応援し、応援された人はまた別の人を応援する…。そんな素敵な循環を行うことができる唯一のスポーツが、チアリーディングです。 誰よりも美しく、誰よりもきれいに演舞をする。お客さんから応援され、お客さんを応援する。初心者でも、体幹が無くても、ダンスができなくても、男子だけでも、誰かを応援することは できる。チアリーディングの世界へようこそ。
|
|
| 5 |
一生役立つ「伝わる技術」 by U ここをクリックある人気のある八百屋さんでは、普通では伝えないことをお客さんに伝えているそうです。 それは「今日おすすめしない野菜や果物」。この話をするとおすすめされなかった野菜や果物は売れ残ってしまいます。しかし八百屋さんはそれでいいそうなんです。その青果店ではほとんどが常連さんですが、もし美味しくない野菜や果物を買ってしまったら評判が落ち、次は近くのスーパーに行ってしまうかもしれない。だからできるだけ正直にお客さんに伝えているそうです。 この一冊にはこのような相手主体の「伝わる技術」が凝縮されています。自分なりの伝わる技術を見つけてみてはいかかでしょうか?
|
|
| 6 |
SNSで交錯する青春 by T ここをクリック高校生限定マッチングアプリ「オルタネート」が必須のウェブサービスとなった世界。それぞれ特別な思いを抱えた高校生の3人が、出会いや別れ、葛藤や挫折、そして苦悩しながら「オルタネート」で繋がっていく。 さまざまなSNSが普及する現代。私たちにとっても共感できる部分がたくさんあります。高校時代、いろいろな悩みを抱えていた方も多いのではないでしょうか? 親や友達、恋人との人間関係、夢を追うことの難しさ、自分とは何か、迷いながらも未来を切り開いていく姿に勇気をもらえます。もしかすると少し懐かしい気持ちになるかもしれません。 とてもさわやかで心温まる作品です。ぜひ手に取ってみてください。
|
|
| 7 |
人の秘密は知らない方がいい…? by S ここをクリック日記とは自分の日常の出来事を記録しておくもの。しかし、それだけではありません。誰にも知られたくないけど吐き出してしまいたいことを形として残しておけるもの、現実の世界では実現できないことを書いた物語のようなもの、そして時には誰かに読ませたい手紙のようなもの…どれも書く人の本当の気持ちが表れています。 あなたの周りにいる人は、日記にどんな秘密を隠しているのでしょうか。そしてそれを知ることは幸か、不幸か…? 短い4篇で出来ており、文字を読むのが苦手な方にもおすすめ。どんでん返しあり、ハートフルストーリーありの1冊です。
|
|
| 8 |
和紙が新たな分野で大変身を遂げる。 by U ここをクリックタイトルを見て和紙と携帯にどのような関係性があるのか疑問に思う方が大半でしょう。実は和紙の紙漉の技術が半導体洗浄に使う超純水を作る浸透膜に応用されたり、金箔打ちの技術が配線板の焼き付けに応用されたり、魔鏡の技術が半導体基板検査に応用されています。こうしてみると多くの日本の伝統技術が現代の日本の進化の為のヒントなっていることがわかります。 世界に冠たる日本の工業技術の背景には長い歴史を持つ伝統の技からヒントを得たものが多くあることがこの本からわかります。日本の伝統の技は工業だけでなく、自然の力を利用し、人々の生活を豊かにする方向にも広く使われています。 無限の可能性を秘める伝統技術に興味はありませんか?
|
|
| 9 |
究極の自己分析!! by S ここをクリック宿題、家の手伝い、部屋の掃除。やりたくないことだらけでゲンナリしていたぼくはいいことを思いついた。「ロボットを使ってぼくのニセモノを作ろう!」 しかし、ニセモノを作るのも一苦労。「ぼくはなまえとかぞくがある」「ぼくはすきなものときらいなものがある」などなど、たくさんの「ぼくは○○」で、ロボットに自分はどんな人なのかを説明する羽目に… 自分っていったいどんな人なんだろう?自分らしさを見失った人はぜひ手に取ってみてください。ヨシタケシンスケワールド全開の、ポップなのに心に響く、大人にこそ読んでほしい絵本です。
|
|
シーズン3(折りたたまれています。ここをクリック)
| おすすめ本(画像クリックで拡大) | ひとこと | |
|---|---|---|
| 1 |
スマホを触る時間を減らしたら豊かになれるはず。 by U ここをクリック みんなでご飯を食べてる時だってスマホを確認せずにはいられないし、会話よりメッセージの方が多い。アプリを切り替えて次々新しい刺激を求めて、少しでも暇だと思うとスマホを触ってしまう、という私達の脆弱性。直接人に会って話すという会話がどれほど重要なものなのかということがわかるおすすめの本です。 |
|
| 2 |
多分間違った出会い系サイトの使い方 by K ここをクリック 他人に紹介した本を読んでもらうということは非常に難しいことです。ましてや本を買ってもらうとなれば、尚更です。この本は、筆者が出会い系で会った様々な人に本を勧めた実体験からどうすれば他人に本を読んでもらえるかをまとめています。
|
|
| 3 |
勉強が楽しくなる工夫が盛りだくさん! by S ここをクリック 学校の学びや環境が合わず、悩んだことはありませんか?また、実際に悩んでいるこどもに出会った時にどんな支援や工夫をしたらよいのか悩んだことはありませんか? |
|
| 4 |
母に感謝を伝えたくなる by T ここをクリック ダニーという男の子がお母さんの誕生日のプレゼントをどれにしようか巡って、探していく物語です。簡易的な児童書で、ページ数も少なく、文章も少ないですが、この少ない情報の中に、親のありがたさや、家族愛に改めて気づかされます。
|
|
| 5 |
とりかえ・ばや/さいとうちほ著 ※こちらの資料は館内での閲覧に限ります 貸出はできません |
平安 ここをクリック 双子のきょうだいは顔がそっくり。内気でしおらしい男の子と、活発でわんぱくな女の子。父親はかねてから、「この二人をとりかえたいなぁ」と、嘆いていました。体は健康に成長しながらも性格はより女性らしく、男性らしく育つ双子は、ひょんなことから互いに入れ替わって宮廷で働くことになり… *身体の性と心の性が異なること 『デジタル大辞泉』第二版より抜粋 |
| 6 |
「なぜか頼られる」「恋愛下手」は、実はきょうだいが原因!? by T ここをクリック 皆さんに兄弟姉妹はいますか?いる方はどのような関係ですか?私は妹がいる2人姉妹で、毎日朝から晩まで熾烈なバトルが繰り広げられていました。
|
|
| 7 |
童心を思い出せる! by N ここをクリック これはデルトラ王国を舞台に、7つの宝石を取り戻すための壮大な冒険をする物語です。王国を救うために立ち上がったリーフとその仲間たちは魔境を巡り、影の大王によって奪われた宝石を集める旅に出ることを決心します。ファンタジーと冒険の要素が融合して、ワクワクできる作品です。 |
|
| 8 |
檻を作るのはだれ? by H ここをクリック 憲法はだれが守るものか、と聞かれてすぐに答えられますか? 少しでも言葉に詰まったならこれを読むことをおすすめします。
|
|
| 9 |
「顔で話す」意味が分かりますか? by U ここをクリック 皆さんはもう教育実習に行きましたか?半分の人は既に児童生徒に授業をしたのではないでしょうか。「授業楽勝だったわ!」なんて人はあんまりいないと思います。特に、みんな分かっているのかなといった話の伝え方の難しさを感じた人は多いのではないでしょうか。 |
|
| 10 |
人生とかいう「ゲーム」についての攻略本 by K ここをクリック あなたは「ゲーム理論」という言葉を知っていますか?
|
|
| 10 |
本の魅力を見つけたい! by S ここをクリック 世界中で普及し、今やない世界で生きるのは難しいと言えるまで私たちの生活に浸透しているインターネット。 |
|
| 11 |
気になる by T ここをクリック まずこの本の一番注目すべき点は、「悪い本」という題名にあります。
|
|
| 12 |
非現実世界へ! by M ここをクリック 現実世界に飽き飽きした、課題ばっかりでもう嫌だ、そんな思いをしている皆さんを非現実世界へ!ハリーポッターの世界は魔法であふれ、日々の鬱憤を晴らしてくれます。
|
|
| 13 |
「自閉症」と「定型発達」の相対化を臨床的に試みる by T ここをクリック 本書は幾つもの事例検討を基にASDの精神病理を明らかにする臨床論である。 |
|
| 14 |
「みんなが読める」をデザインする by T ここをクリック あなたは「UDデジタル教科書体」を知っていますか?
|
|
| 15 |
絶望が生きる力になる!! by N ここをクリック たいていの人は「絶望」について考えて一番最初に思い浮かぶことは悪いイメージでしょう。ですが、カフカの絶望したことに対する数々の文章からは、どこかユーモアがあり元気をもらえるものばかりです! |
|
| 16 |
雑談の苦手が楽になる by M ここをクリック 二人で話をしているときに会話が続かない、なんて声をかけたらよいかわからない、そんな些細なことを気にしている人、いませんか?
|
|
| 17 |
「撮る」ことは「隠す」こと? by H ここをクリック お手元のスマホでなにか好きなアプリを開いてみてください。インスタ、LINE、X、ビーリアル……どこを見ても情報だらけ! |
シーズン4
| おすすめ本(画像クリックで拡大) | ひとこと | |
|---|---|---|
| 1 |
疲れているあなたへの処方箋 by T ここをクリック最近、疲れていませんか?研究のため、レポートのためにと日々難しい本とにらめっこしてばかりではありませんか?そんなあなたに、ぜひこの本を読んでいただきたいです。 この作品は、『ちびまる子ちゃん』でおなじみのさくらももこ先生の体験が詰め込まれたエッセイ集です。少し不思議で面白いできごとが、さくら先生の空想世界とともに語られています。『ちびまる子ちゃん』にも登場する父ヒロシやお母さん、お姉ちゃんも登場します。あるお話ではあの優しいおじいちゃん友蔵も登場しますが、アニメとはギャップがあるかも。 |
|
| 2 |
人生における伝説はまだ始まったばかり by N ここをクリックこの物語の主人公は周りと変わらない普通の男の子です。ただし顔以外は——— オーガスト・プルマンは病気のせいで幼いながらに27回もの顔の手術を行わなければならなかったという過去があります。 初めて通う学校ではいじめっ子にからかわれることもあり、出会う人々に目を背けられることも多々あったとのことです。そんな中、ストーリーには親や友達に支えられつつも彼が数えきれない困難に立ち向かい、勇敢に生きる姿が描かれています。
|
|
| 3 |
物事の本質を見ることができる! by M ここをクリック皆さんは美術に対してどのようなイメージを持っていますか?美術は正解のある科目ではありません。 この本を読むことで、当たり前だと決めつけて物事を見ることがなくなり、物事の本質を探究することができるようになります。新たな発想を生み出す力はこの先非常に重要になってくる能力です。13歳からのアート思考は、美術が好きな人にも少し苦手意識がある人にもおすすめできる本です。自分なりのものの見方を発見するのは楽しい体験ですし、生きていくうえでも役にたちます。 豊かな人生をおくるために役立つ本書を、ぜひ1度読んでみてはいかがでしょうか。 |
|
| 4 |
コミュ力って、そんなもん。 by S ここをクリック 昨今声高に叫ばれているのが「コミュニケーション能力」の育成。教員養成大学に通う皆さんも、授業作りの過程で必ずといっていいほど意識しているのではないでしょうか。 「コミュニケーション不足」という言葉で一括りにされてしまった現代人の心のもやもやを照らす、そんな一冊です。
|
|
| 5 |
“絵”にひそむ違和感がすべてを変える!? by M ここをクリック『変な絵』は最近話題の作家・雨穴さんによる短編集。 実際に描かれた絵から真相を読み解いていく、新感覚のミステリー集。最初はなんの変哲もない風景画、日記。でもよくみたら、変な絵。 本書では、人が無意識に自分の内面を絵に投影するという「投影法」の考え方をもとに、絵にひそむ”違和感”から隠された真実を導き出していきます。変な絵の違和感に気づいた瞬間、物語が一気にひっくり返る一冊です。 一度読み終えても、きっと最初のページに戻ってもう一度確認したくなる。読者は、細部まで仕掛けられた伏線に気づいたとき、背筋がゾッとします。読み終えた後、普段なにげなく見ていた絵がちょっとだけ怖くなるかもしれません。 |
|
| 6 |
不安定で先が見えない物語は、家の中で完結する by T ここをクリック役所の手違いにより、父と二人で暮らした大切な家を競売にかけられたキャシー。イランから亡命したベラーニは、破格で競売にかけられたキャシーの家を転売することで貧困からの脱却を目指す。大切な居場所であり、再起を図る希望でもある家は、両者の思惑を吞み込み、それぞれの人生を静かに交差させていく。 カリフォルニアの静かな海辺で始まるこの物語は、いくつもの矛盾を映している。アメリカン・ドリームに胸を躍らせるその場所は、制度によって人の心を守らない。善良であろうとする人々は、エゴに吞まれて暴走する。人を守り、愛をもたらすはずの家が、争いの種となり、人を壊す。理想が理想であるために、壊れていく物語。
|
|
| 7 |
愛は奇跡を起こす by H ここをクリックデュークが死んだ。愛犬デュークはアイスが好きで、落語が好きで、すねた横顔はジェームズ・ディーンによく似ていた。そして、デュークはとても、キスがうまかった。そんなデュークが、私のデュークが、死んでしまった。 あわただしくクリスマスソングが流れる12月の街で、デュークを失い悲しみに暮れる「私」は不思議な少年と出会う。少年はアイスが好きで、落語が好きで、さみしそうに笑う顔が、ジェームズ・ディーンによく似ていた。一夜限りの邂逅が、つめたい冬の夜をそっとあたためる。 |
|
| 8 |
緊張感の描写がすごい。主人公たちの心音や息遣いまで聞こえてきます。 by S ここをクリック二人の主人公の視点が交互に描かれて進行する構成。 一人目の主人公のアキラは上司を駅のホームに突き落として殺害したとして警察に追われ、すぐ近くのもう一人の主人公ミチルの家に逃げ込む。視力をなくしたミチルは、一人で暮らしている。アキラはミチルに気づかれないよう気配を殺し、ミチルの家に隠れ住む。ミチルは最初こそ気のせいだと思っていたが、アキラの存在に少しずつ気が付き始め、顔も名前も、声もわからない相手と食卓を共にする奇妙な関係に。
|
|
| 9 |
ディズニーキャストがより輝いて見える一冊 by T ここをクリックこの本は、「夢と魔法の世界」ディズニーランドで働くキャスト(スタッフのこと)のお話です。キャストと「サービスの神様」のつながりから生まれた4つの物語を通して、ディズニーキャストたちが大切にしているおもてなしの心を知ることができます。 どの話も心温まり感動できる物語です。ディズニーランドに行ったことがある方は多いと思いますが、この本を読んだ後に訪れるとよりディズニーランドが魅力的な場所に見えると思います。 そして、「サービスの神様」は誰のことなのか、ぜひこの本を読んで確かめてみてください! |
|
| 10 |
レポート作成に困ったらこれ! by M ここをクリック『思考の整理学』は、単なる思考法や記憶術の本ではありません。それは、私たちが情報とどう向き合い、どのように自分の頭で考えるかという、より本質的な問いに迫る一冊です。
レポートがうまく書けない、そんな方はぜひこの本を手にとってみてください。
|
|
| 11 |
願はくは之を語りて平地人を戦慄せしめよ by S ここをクリック 『遠野物語』は、柳田國男が現在の岩手県遠野地方に伝わる逸話や伝承をまとめたものである。本書は『遠野物語』に、原点の息遣いを残したまま京極夏彦による新解釈と再編を加えたものである。 あなたは古い御伽噺だと思うかもしれない。 静かな語り口に導かれ遠野郷の世界へ足を踏み入れると、あなたは、怪異がいつのまにか日常のすぐとなりにいることに気がつくだろう。 |
|
| 12 |
「辞書にない言葉」の辞書!? by H ここをクリック 私たちが日々使っている言葉。多くの言葉がありますが、そのすべてが辞書に載っているわけではありませんよね。この本は、そんな「辞書からこぼれ落ちた言葉」を集めたもうひとつの辞書です! |
|
| 13 |
その声は届かなくても、消えることはない。孤独でいる人に寄り添ってくれるような優しく温かいお話 by M ここをクリック52ヘルツという、ほかのクジラには届かない声で鳴くクジラがいます。どれだけ声を出しても、その存在に気づいてもらえない、世界で最も孤独なクジラだと言われています。 本作『52ヘルツのクジラたち』は、そのクジラたちの姿に重ねるように、自分の気持ちをうまく言葉にできず、孤独を抱えて生きてきた人たちを描いた物語です。過去に深い傷を負った主人公と、声を奪われた存在が出会い、心を通わせていく中で、誰かが「気づくこと」「そばにいること」の大切さに気づけるお話です。 |
|
| 14 |
「大切なものは目に見えない」を思い出させてくれる物語 by N ここをクリック「星の王子さま」は大人も子どもも心に響く不思議な魅力をもつ物語です。主人公の「ぼく」は砂漠で出会った小さな王子さまから、自分の星での出来事や、旅で出会った奇妙な大人たちの話を聞きます。それらのエピソードは、私たちの日常にもつながっており、思わず自分に置き換えて読みたくなる内容です。 王子様の語る言葉はどれもシンプルですが、「人を大切にするってどういうこと?」「本当に大切なものってなに?」というように、読んでいる私たちに考えさせてくれるものばかりです。読むたびに感じ方が変わり、子どもの頃には気づかなかった深いメッセージも浮かび上がります。読み終えたあとに心が温かくなり、毎日の過ごし方を少し見直したくなる名作です。 |
|
| 15 |
小さな子どもになって絶望できます。 by S ここをクリック移民だった父の血を半分ひいている少年リンツは、時に「移民の子」という差別を受けながらも母と二人でつつましく暮らしていたが、父が遺した聖書をきっかけに国中で話題の怪盗ゴディバを追う探偵ロイズと出会い、事件に巻き込まれてゆく。 読んでいる自分も子どもになって、リンツと一緒に小さな歩幅で駆け回り、冒険する気分を味わうことができる。 子どもの気持ちになって楽しく読み進めていると、ある時急に、今までの短い人生の中で信じてきたものが崩れ、世界が終わってしまうような絶望的な状況に立たされる。 小さな子どもの視点で、大人の世界の理不尽さ、善悪の境界や人間の弱さを見ることができる。読み進めるほどに価値観が揺さぶられ、読み終えた後に深く考えさせられる一冊。 |
|
| 16 |
二人の愚か者の長い旅 by T ここをクリックチャーリーの輸入車販売店は事業に失敗し、経営が立ち行かなくなるも、絶縁状態にあった父の訃報が届く。遺産目当てに故郷に帰ると、財産のほとんどは会ったことのない兄レイモンドに信託されていた。施設暮らしの兄を強引に連れ出して遺産を手に入れようとするも、レイモンドの強いこだわりに因る様々な行動にチャーリーは翻弄される。飛行機嫌いのレイモンドをどうにか連行するために、チャーリーは車を出して兄を迎えに行く。 半ば誘拐じみた旅の過程で二人は様々なものを手にする。存在すら知らなかった兄、「いつも」と違う体験、常識や品位、共に過ごした時間——その果てに兄弟が選択する未来には、愛を感じずにはいられないだろう。 |
|
| 17 |
限られた時間の中過ごす、二人の切なくも温かい物語 by F ここをクリック「君の膵臓をたべたい」———この衝撃的なタイトルに隠された、あまりにも美しく残酷な真実を知っていますか? 物語は、地味な高校生である「僕」がクラスの人気者である山内桜良の秘密の日記『共病文庫』を拾うことから始まります。正反対の二人が過ごす、何気なくもかけがえのない日々。そこには、私たちがつい忘れてしまう「日常の尊さ」が詰まっています。 しかし、物語はタイトルからは想像できない衝撃の結末へと加速していきます。「死」を意識した彼女の言葉は、今を生きる私たちの胸に深く刺さります。この本のラスト、このタイトルの本当の意味を知ったとき、私たちは涙し「一生懸命に今日を生きたい」と思うはず。単なる恋愛小説ではないこの本をぜひ手に取って読んでみてください。 |
|
| 18 |
目標達成への遠回りをやめるには by H ここをクリック皆さんはなにか目標を立てて達成した経験があるでしょうか。私は資格試験などで目標を立ててきたのですが、最短でゴールにたどりついたとは言えないようなものでした。 この本では、教育現場でも取り上げられているPDCAサイクルに「G=ゴール」を加えたG-PDCAという考えを使い、目標達成までの道のりをノート一冊に見えるかしていくという本です。A4ノートに「やりたいことリスト」や「デイリー目標PDCA」などのフレームを作り、計画・実行・振り返りを毎日回していくことで、日々のタスクを習慣としてこなせるように工夫されています。この方法を私が目標としているマラソンのタイム達成に用いて、「今日のメニュー→実行→振り返り」をノートに書くようにしてから私のマラソンへの考え方や一日の行動が大きく変わりました。 なにか達成したい目標をお持ちの方は、この本を手に取り、自分の目標に向かい、G-PDCAを回してみてはいかがでしょうか。 |